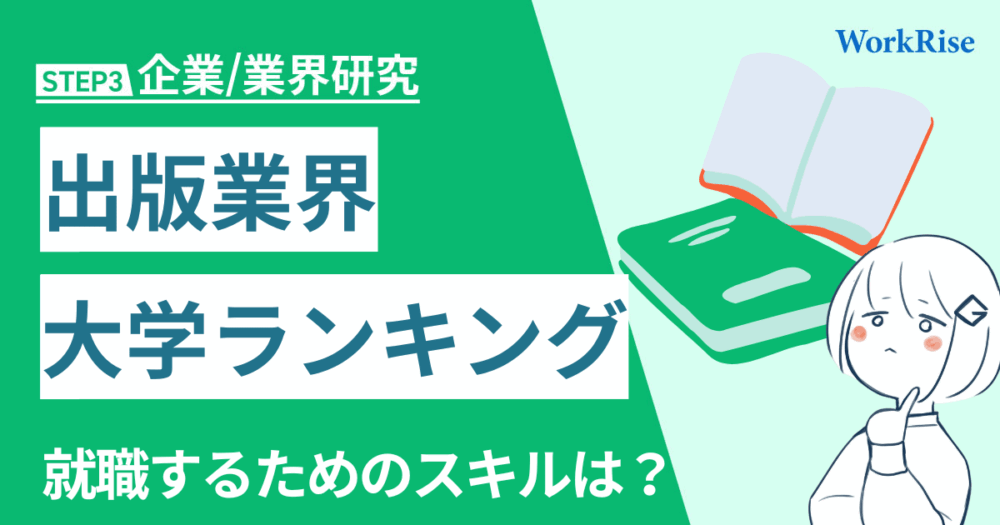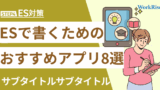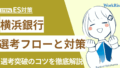出版社に就職する大学のランキングを知りたい!
こんにちは。26卒ライターのわかです。
就活を進める中で、出版社業界に就職できる大学について気になった経験があると思います。

出版社への就職を目指しているけど、どの大学が強いの?

出版社業界での仕事内容が知りたい!
といった思いがある方必見です!
この記事では、
- 出版社業界の全体像(大手・準大手)
- 出版社での具体的な仕事内容
- 出版業界の就職事情(難易度、年収、必要なスキルなど)
- 出版社に受かる人の特徴
- 出版社に就職するための具体的な方法
是非最後まで読んでください!
関連記事はこちらから!
出版社業界について紹介!
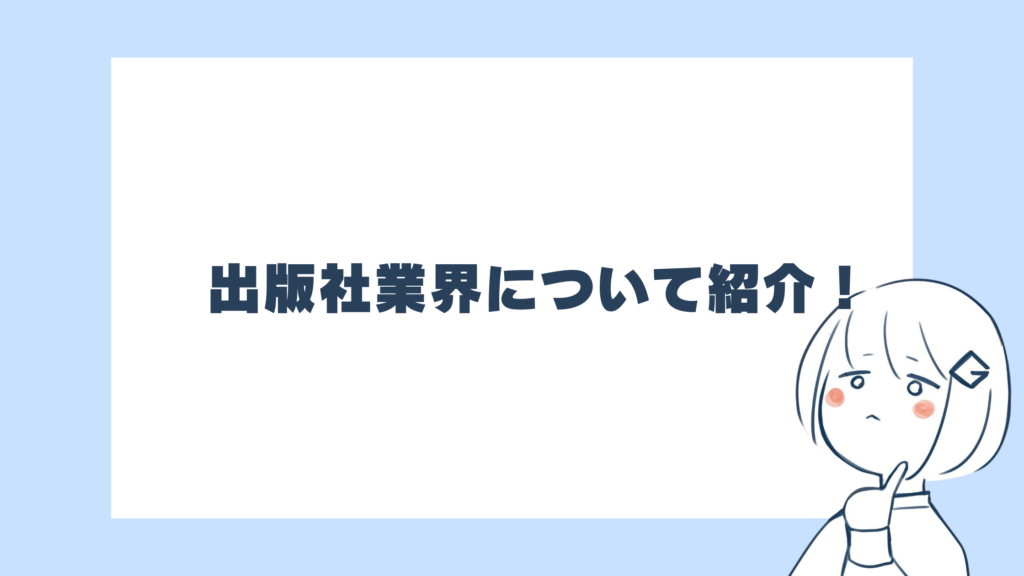

出版社業界って実際どんな感じなんだろう?
出版社について、なんとなくは知っていてもきちんと答えられない人が多いのではないでしょうか。
一口に出版社と言っても、それぞれ得意なジャンルや社風が違います。どんな会社があるのか、一緒に見ていきましょう!
出版社の大手三社
出版社の大手三社とは、講談社・集英社・小学館のことです。
これらの会社は、漫画、小説、雑誌など、幅広いジャンルで多くのヒット作を生み出しています。
講談社
講談社は、漫画雑誌『週刊少年マガジン』『モーニング』、文芸誌『群像』、週刊誌『FRIDAY』、少女漫画誌『なかよし』など、あらゆるジャンルの出版物を手がける総合出版社です。
誰もが知る人気作を多数生み出しており、エンターテインメント界を常にリードしています。
書籍事業だけでなく、アニメ化や映画化、ゲーム化といったメディアミックス事業にも積極的です。
最近では、『東京卍リベンジャーズ』や『ブルーロック』のように、漫画が原作でありながら、アニメや舞台でも大ヒットするような作品を多数手がけています。
講談社は、社員一人ひとりの発想力を大切にする社風があります。新しいことに挑戦したい、ジャンルの垣根を越えて面白いものを生み出したいと考えている人にぴったりの会社と言えるでしょう。

ジャンルを超えて、幅広い活動をしている出版社なんだね!
集英社
集英社といえば、『週刊少年ジャンプ』が有名ですよね!「友情・努力・勝利」をテーマにした数々の人気漫画を生み出し、日本の漫画文化を築き上げてきました。
ほかにも、『週刊ヤングジャンプ』や『りぼん』などの漫画雑誌、『non-no』『MORE』などのファッション誌、文芸誌『すばる』、小説雑誌『小説すばる』など、幅広い出版物を手がけています。
集英社の特徴は、「ヒット作を生み出すための徹底した熱意」です。編集者と作家が二人三脚で作品を作り上げるスタイルは、まさに職人技。 「面白い作品のためなら何でもやる」という情熱が、読者の心を掴む作品を生み出しているのです。

ヒットを作り出す熱意が強い出版社なんだね!
小学館
小学館は、『小学一年生』などの教育雑誌や図鑑、学習漫画から、『CanCam』などのファッション誌、漫画雑誌『ビッグコミック』、そして文芸書まで、多様な出版物を手がける総合出版社です。
特に教育分野に強く、幼い頃から触れる機会が多い会社なので、親しみやすいと感じる人もいるかもしれません。
また、『ドラえもん』『名探偵コナン』『ポケットモンスター』など、国民的キャラクターを多数生み出していることでも知られています。
キャラクタービジネスや版権事業にも非常に強く、出版という枠を超えた事業展開に力を入れています。
「本」という形だけでなく、多様なメディアでコンテンツを届けたい、と考えている人には、小学館はとても魅力的な会社です。

様々なメディアでコンテンツを届ける出版社なんだね!
準大手・中堅
出版社は大手三社だけでなく、準大手や中堅も個性的で魅力的な本を数多く出版しています。
特定のジャンルに特化していることも多く、そこでしかできない仕事があるかもしれません。
それでは、準大手・中堅の三社を見ていきましょう!
KADOKAWA
KADOKAWAは、書籍出版だけでなく、アニメや映画、ゲームなど、メディアミックスを積極的に展開している会社です。
ライトノベルや文庫本に強く、Webメディア事業も活発なので、新しいコンテンツビジネスに興味がある人には特におすすめです。
一つの小説を、コミック、アニメ、映画、ゲームなど、複数のメディアで展開していく「メディアミックス」戦略は、KADOKAWAの最大の強みです。このビジネスモデルは、作品の魅力を最大限に引き出し、より多くの人に届けるための手法として、他の出版社からも注目されています。
「出版」という枠に収まらない、新しいコンテンツの可能性を追求したい人は、ぜひチェックしてみてください。
文藝春秋
文藝春秋は、文芸誌『文學界』や雑誌『週刊文春』などで知られる、文芸書やジャーナリズムに強い老舗出版社です。文学作品やノンフィクションに携わりたいと考えている人には、ぜひチェックしてほしい会社です。
「芥川賞」「直木賞」という日本の文学界で最も権威ある賞の運営にも深く関わっており、文学界に大きな影響力を持っています。
文藝春秋で働くことは、日本の文化や社会に貢献することに直結すると言えるでしょう。ジャーナリズムやノンフィクションに興味がある人は、この会社の歴史と社風をぜひ調べてみてください。
新潮社
新潮社も、文芸書を中心に質の高い書籍を多く出版していることで有名です。『新潮文庫』は多くの人が一度は手にしたことがあるのではないでしょうか。純文学や翻訳文学に興味がある人にぴったりの会社です。
新潮社は、時代を超えて読み継がれるような「本物の本」を作り続けることにこだわっています。派手な宣伝は少なくても、内容で勝負する姿勢は、多くの読者から信頼されています。
「本」そのものの価値を大切にしたい、という想いがある人にとっては、新潮社は理想的な職場になるはずです。
具体的に何をする?出版社に就職後の仕事内容一覧
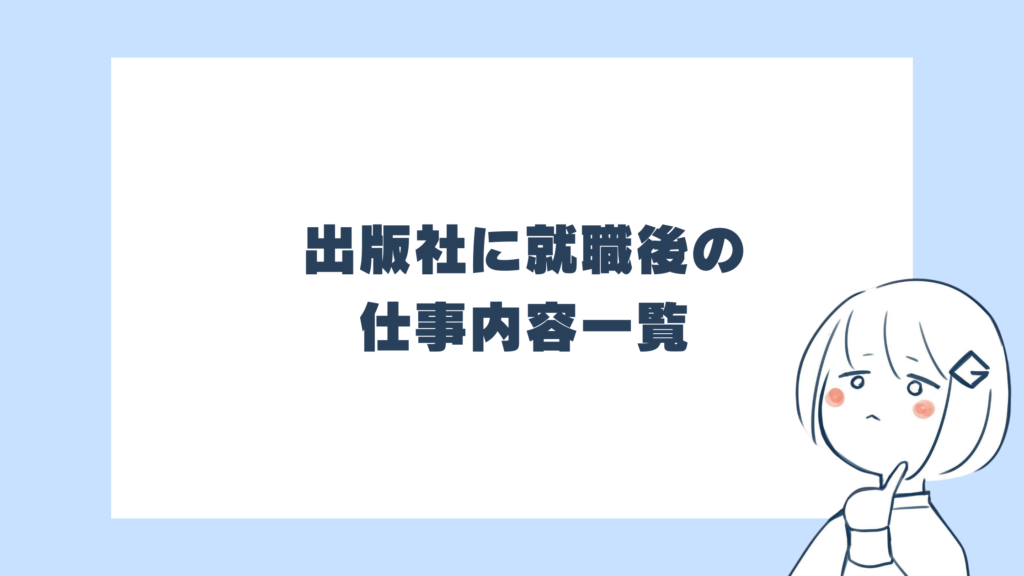

出版社に就職するなら、編集者になるのかな?
「出版社で働く」と聞くと、「編集者」の仕事だけを想像しがちですが、実はたくさんの職種があります。どの部署も、本を読者のもとに届けるためには欠かせない大切な役割を担っているんですよ。
それでは、出版社に就職後の仕事内容を見ていきましょう!
編集
編集者は、作家さんと一緒に作品を作り上げる、出版社の花形とも言える仕事です。企画の立案から、原稿の執筆依頼、校正、そして最終的な出版物の完成まで、すべての工程に関わります。作家さんの才能を最大限に引き出し、魅力的な本を生み出すことが編集者の使命です。
とある編集者の一日を見てみましょう。
- 9:30 出社
- メールチェックや、売上データを確認し、今日のタスクを整理します。
- 10:00 企画会議
- チームで新しい企画についてブレインストーミング。面白そうなアイデアが出たら、具体的に形にできないか検討します。
- 11:00 作家と打ち合わせ
- 作家さんと喫茶店で会い、次の作品の方向性やプロットについて話し合います。
- 13:00 昼食
- 書店を巡り、他の出版社の本をチェックすることも。
- 14:30 校正作業
- ゲラ(印刷前の試し刷り)を読み込み、誤字脱字や表現の不備がないか細かくチェックします。
- 16:00 デザイナーと打ち合わせ
- 本の表紙デザインについて、デザイナーにイメージを伝えます。
- 17:00 原稿整理
- 作家さんから届いた原稿を読み込み、構成や表現について赤字を入れます。
- 19:00 退社
- 企画が詰まっている時や締め切り前は、もっと遅くなることもあります。
このように、編集者は常に「面白いもの」を追求し、多くの人とコミュニケーションを取りながら本を作り上げていきます。
デジタル・通販
最近では、電子書籍やオンラインストアの重要性が増しています。デジタル・通販部門は、電子書籍の制作・配信、自社ECサイトの運営、デジタルマーケティングなど、デジタルを活用して本を広めるための仕事を行います。新しい技術やトレンドに敏感な人に向いています。
電子書籍の市場は年々拡大しており、出版社のデジタル部門は、これからの成長を担う重要な部署です。ただ単に紙の本を電子化するだけでなく、電子書籍ならではの表現方法を模索したり、SNSを活用した新しいプロモーションを企画したりします。
版権
版権(ライツ)部門は、出版物の二次利用を管理する仕事です。
例えば、人気漫画がアニメ化されたり、小説が映画化されたりする際、著作権の許諾や契約交渉を行います。作品の可能性を広げる、非常にやりがいのある仕事です。
「この小説、映画化したら面白そうだな」「この漫画、舞台にしたらどうだろう?」そんな風に考えられる人には、版権の仕事はとても向いています。
作家や原作者の想いを大切にしながら、作品の新しい可能性を切り開いていく、夢のある仕事です。
営業
営業の仕事は、書店や取次(出版物を書店に卸す問屋)に対して、自社の出版物を売り込むことです。書店の売場づくりを提案したり、どの本を何冊置いてもらうか交渉したりします。
「この本は、ぜひこの棚に置いてほしいんです!」「この小説、絶対に売れますから、平積み(表紙を見せて陳列すること)にしてください!」といった熱意のあるプレゼンで、書店員さんの心を動かすのが営業の腕の見せ所です。
営業は、本が読者の手に届くための最後の砦とも言える重要な仕事です。
管理
管理部門は、人事、経理、総務など、会社全体の運営を支える縁の下の力持ちです。社員が働きやすい環境を整えたり、会社の予算を管理したりします。
地味な仕事に思えるかもしれませんが、この部署がないと会社は成り立ちません。縁の下の力持ちとして、会社を支えたいと考える人には、とても向いている仕事です。
出版社への就職は難しい?出版業界の実態
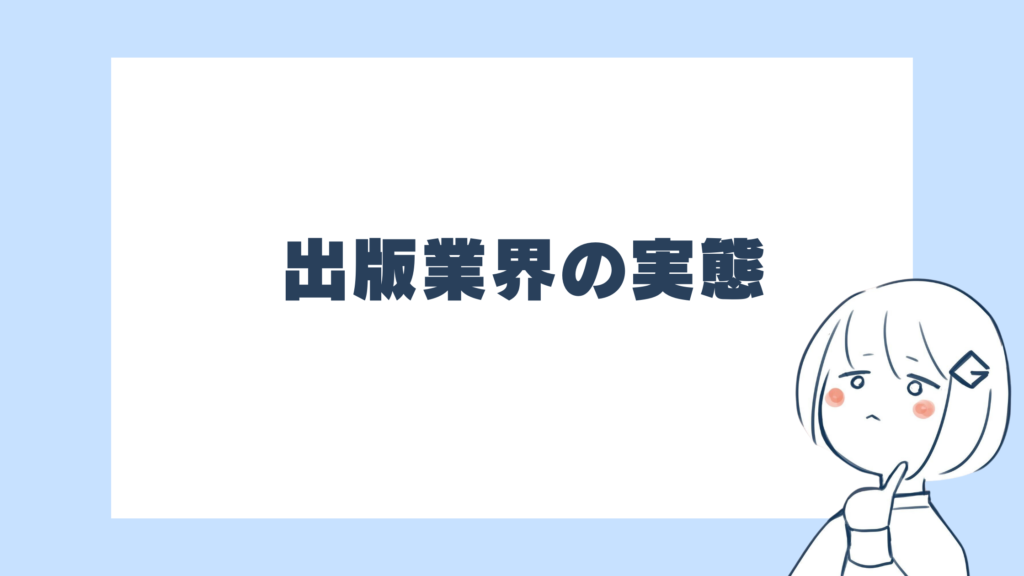

出版社への就職は難しいのかな?出版業界の実態ってどうなんだろう?
出版社への就職は、一般的に「難関」だと言われています。
なぜ難しいのか、また、出版業界の実態はどんなものでしょうか。
具体的なデータを見ながらその理由を探ってみましょう。
出版業界の新卒離職率
厚生労働省の「新規学卒者の離職状況調査」(2023年発表)によると、出版業界の新卒3年以内の離職率は約28%です。これは、大卒全体の平均離職率約31%と比較しても、ほぼ同じ水準です。
「出版社は激務で離職率が高い」というイメージがあるかもしれませんが、データを見るとそこまで特異な業界ではないことがわかります。ただ、部署や職種によっては残業が多くなることもあるので、体力とストレス耐性が必要になるかもしれません。
出版業界の平均年収
国税庁の「民間給与実態統計調査」(2023年発表)によると、出版業界の平均年収は約450万円〜600万円とされています。これは、日本全体の平均年収約460万円を上回る水準です。
ただし、年収は会社の規模や職種、経験年数によって大きく変動します。大手出版社では、年収800万円〜1000万円を超えるケースもあるようです。一方で、中小出版社では平均よりも低くなることもあります。
出版業界の就職に有利な資格
出版業界への就職に「必須」の資格はありません。しかし、以下のような資格は、選考であなたの熱意をアピールする上で有利に働く可能性があります。
- 日本語検定:日本語の知識や語彙力を証明できます。
- 校正技能検定:誤字脱字をチェックする「校正」のスキルを証明できます。
何より大切なのは、資格よりも「本が好き」という熱意と、それを仕事に活かせるスキルです。資格は、あなたの熱意を客観的に示すためのツールだと考えましょう。
出版社業界の就職に強い学部
特定の学部が有利ということはありません。文学部や経済学部、法学部、社会学部など、幅広い学部から内定者が出ています。
大切なのは学部ではなく、大学生活で何を学び、どんな経験をしたかです。例えば、文学部で培った読解力や分析力は編集の仕事に活かせますし、経済学部で学んだ市場分析の知識は営業や企画の仕事に役立ちます。
出版業界に学歴フィルターはあるの?
「出版社は学歴フィルターがある」という噂を聞いたことがあるかもしれません。確かに、大手出版社では難関大学の出身者が多い傾向にあります。
しかし、学歴だけで合否が決まるわけではありません。企業の人事担当者は、ESや面接を通じて、あなたの個性や熱意、潜在能力を見ています。学歴はあくまで一つの情報であり、それよりも「なぜ出版業界で働きたいのか」「入社後、何を成し遂げたいのか」というあなたの熱い想いが重要です。
出版社の就職難易度ランキングは?
正確な就職難易度ランキングはありませんが、新卒採用人数が少なく、応募者が非常に多いため、大手出版社は軒並み難易度が高いと言えるでしょう。
例えば、大手出版社の倍率は数百倍になると言われています。そのため、大手出版社一本に絞るのではなく、中堅や専門出版社も視野に入れることで、チャンスは格段に広がります。
出版社への就職大学ランキング
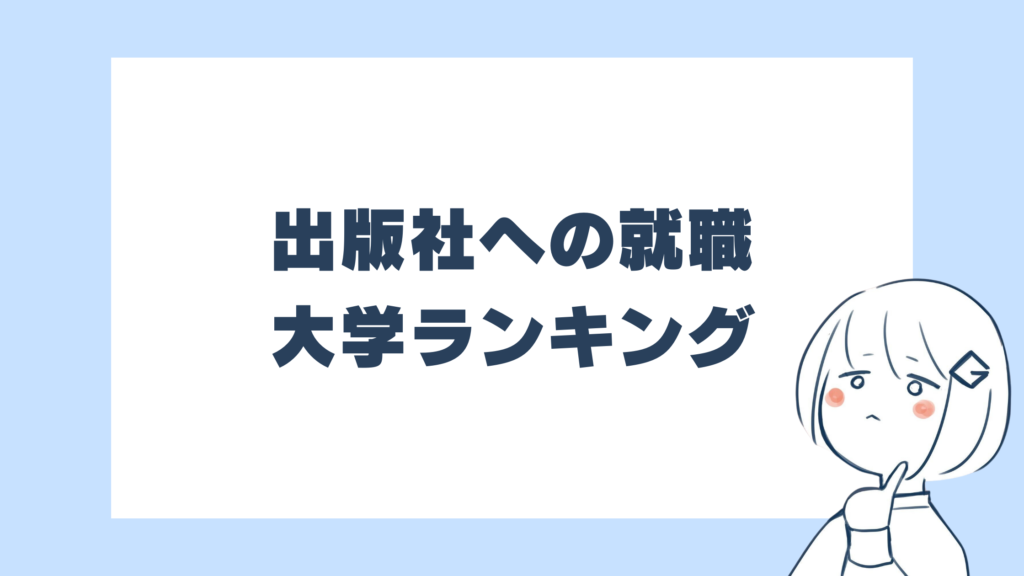

出版社に就職する大学ランキングも知りたい!
大手出版社は採用人数が少ないため、正確な「ランキング」を出すのは難しいです。
しかし、過去の採用実績を見ると、特定の大学から多く採用されている傾向があるのは事実です。ここでは、各社の採用実績を参考に、どのような大学が強いのかをご紹介します。
集英社の採用大学ランキング
| 1位 慶応義塾大学 | 2人採用 |
| 1位 法政大学 | 2人採用 |
| 1位 青山学院大学 | 2人採用 |
| 4位 北海道大学 | 1人採用 |
集英社は、早稲田大学からの採用が最も多いことで知られています。その他、東京大学や慶應義塾大学といった難関大学からの採用も目立ちます。
しかし、集英社は「大学名は選考に一切関係ありません」と公言しているんですよ。これはつまり、学歴フィルターがない、ということ。
もちろん、難関大学の学生が多いのは事実ですが、それは彼らが大学で培った論理的思考力や、専門的な知識、そして何より「面白いもの」を追求する力を持っているからだと考えられます。
講談社の採用大学ランキング
| 1位 東京大学 | 4人採用 |
| 2位 上智大学 | 3人採用 |
| 2位 慶応義塾大学 | 3人採用 |
| 2位 早稲田大学 | 3人採用 |
講談社も、早稲田大学がトップクラスの採用実績を誇ります。次いで、東京大学や慶應義塾大学、同志社大学、京都大学など、東西の有名大学が並んでいます。
特に早稲田大学は、マスコミ就活に強いと言われているので、この結果は納得です。また、関西圏の大学からも多くの採用実績があるのが、講談社の特徴です。
小学館の採用大学ランキング
| 1位 京都大学 | 2人採用 |
| 1位 早稲田大学 | 2人採用 |
| 3位 筑波大学 | 1人採用 |
| 3位 東京大学 | 1人採用 |
小学館は、京都大学や早稲田大学、慶應義塾大学といった大学からの採用が多いです。一方で、東京外国語大学や成城大学、帝京大学といった、幅広い大学から採用している実績も見られます。
小学館もまた、学歴だけでなく、学生一人ひとりの個性や熱意を重視していることがうかがえます。
KADOKAWAの採用大学ランキング
| 1位 早稲田大学 | 6人採用 |
| 2位 東京大学 | 3人採用 |
| 3位 京都大学 | 2人採用 |
| 3位 慶応義塾大学 | 2人採用 |
KADOKAWAは、早稲田大学からの採用が非常に多いです。それに加えて、東京大学、慶應義塾大学、上智大学、一橋大学など、難関大学が上位を占めています。
KADOKAWAは、出版だけでなく、アニメやゲームなど多角的な事業を展開しているため、出版に加えて幅広い分野に興味を持つ学生が多いのかもしれません。
出版社の就職に強い大学一覧~国立編~
国立大学では、東京大学や京都大学、一橋大学、大阪大学などが、出版業界への就職に強いと言われています。
これらの大学は、学術的な知識だけでなく、論理的思考力や知的好奇心を高く評価される傾向があります。
出版社の就職に強い大学一覧~関西編~
関西では、京都大学、大阪大学、神戸大学といった国立大学に加え、同志社大学、立命館大学、関西大学、関西学院大学といった、いわゆる「関関同立」が強く、多くの出版社に人材を送り出しています。
出版社は関東に本社があることが多いですが、様々な関西地方の大学の人が入社をしています。
出版社の就職に強い大学一覧~関東編~
関東では、東京大学、早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、明治大学、青山学院大学、立教大学といった、難関私立大学が強く、出版社への就職実績が豊富です。
一方で、難関大学以外の大学の名前も見られることがあります。難関大学だけを採用しているというわけではありません。
出版社に受かる人の特徴6選!
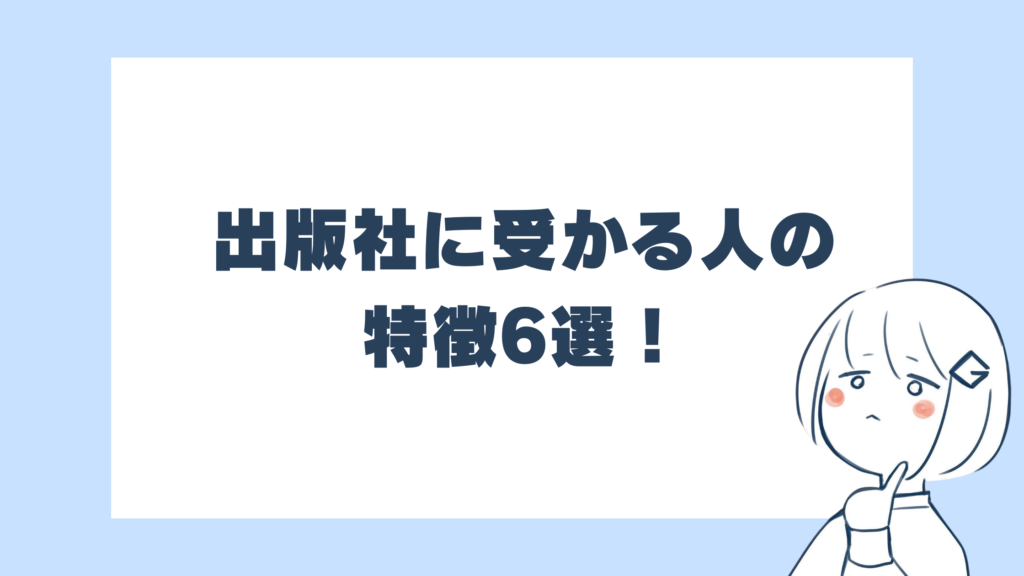

出版社ってどんな人が受かるのかな?
出版社に内定をもらうためには、どのようなスキルや素質が求められているのかを知ることが重要です。
また、学歴だけでなく、選考で評価される「人物像」もあります。
どんな人が受かるのか、詳しく見ていきましょう!
①コミュニケーション能力が高い
出版社は、作家やデザイナー、印刷所、書店など、多くの人と協力して一つの本を作り上げます。そのため、円滑な人間関係を築くための高いコミュニケーション能力が求められます。
相手の意図を汲み取り、自分の考えを正確に伝え、時には交渉する。そんな力が、本というチームプレーで非常に大切なのです。
具体的には、以下のような場面でのコミュニケーション力が求められます。
- 著者とのやりとり:執筆の進行状況を確認し、締め切りを守らせるための調整。
- 社内調整:デザイン部や営業部と協力して、出版物のコンセプトに合ったプロモーションや製品化を推進。
②企画力=入社後やりたいことが明確
「こんな本を作りたい!」「こんな企画を立ち上げたい!」という明確なビジョンを持っている人は、出版社にとって非常に魅力的です。
面接で「もし入社したら、どんな本を作りたいですか?」と聞かれたときに、「まだわからないです…」ではなく、具体的な企画案を話せると、あなたの熱意が伝わります。
企画力がある人は、次のような特性を持っています。
- トレンドの読み取り:社会の動きや読者のニーズを敏感に察知し、人気を集めそうなテーマを見つけ出す力。
- 実行力:斬新なアイデアを実現するために、著者や協力者を巻き込みながらプロジェクトを進行させる力。
出版社の採用面接では「どんな本を作りたいか?」や「どういった読者にアピールしたいか?」という質問が頻繁にされます。
自分が入社後にどんな企画を担当したいのか、具体的なビジョンを持っていることが重要です。
③体力がありストレス耐性が強い
出版業界は、締め切り前は残業が多くなったり、予期せぬトラブルが発生したりと、タフな場面に直面することがあります。
そんな状況でも乗り越えられる体力とストレス耐性は、非常に重要な資質です。学生時代に何かに熱中して、最後までやり遂げた経験があれば、それをアピールしましょう。
日々の業務での例
- 締め切り対応:原稿の進行が遅れているときでも、冷静に対処しながらスケジュールを調整する。
- 長時間作業:編集や校正作業での長時間の集中を維持し、ミスを防ぐ。
④論理的思考力のある人
企画の意図を論理的に説明したり、問題点を分析して解決策を考えたりする力が必要です。
「なぜこの企画が面白いのか?」「この本は誰に、なぜ読まれるのか?」といったことを、感情論ではなく、データや根拠に基づいて考えられる人は、出版社で活躍できます。
特に、著者や他の部署と協力し、出版物の方向性を明確にするためには、データや事実に基づいた分析力が必要です。
具体例としては
- マーケットリサーチ:ターゲット層に関するデータを分析し、作品の売れ行き予測や宣伝方針を決定。
- 説得力のある提案:編集会議で、他のチームメンバーを納得させるために、自分の企画を論理的にプレゼンする力。
などです。
⑤言語能力・言語化力が高い人
本という「言葉」を扱う仕事なので、語彙力や文章力はもちろん、自分の考えを正確に言葉にして伝える言語化力も大切です。
これは、ES(エントリーシート)や面接でも試されます。日頃から、自分が感じたことや考えたことを、人に伝わるように言葉にする練習をしてみてください。
また、翻訳書籍や外国のコンテンツに関わる場合、英語などの外国語のスキルも有利に働きます。
⑥情報収集能力が高い人
世の中のトレンドや読者のニーズをいち早くキャッチし、それを企画に活かすことが求められます。
日頃から幅広い分野にアンテナを張り、情報収集を怠らない人が向いています。書店はもちろん、SNSやニュースサイト、YouTubeなど、さまざまな媒体から情報を得る力を身につけましょう。
具体的には
- 現場調査:新たな読者層やジャンルの可能性を探るために、徹底したリサーチを行い、企画に活かす。
- 他業界の事例を取り入れる:他の業界やメディアで成功した企画や戦略を応用し、新たなビジネスモデルを模索する。
などが挙げられます。
出版社に就職するための必勝法
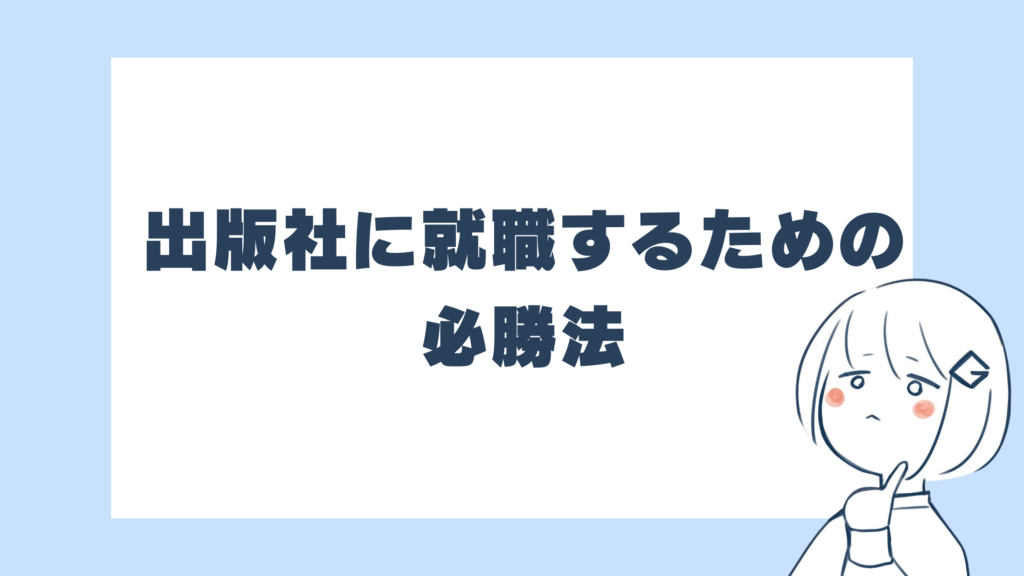

ランキングも高学歴の大学ばかりだし、就職は難しいのかな…
諦めないでください!確かに、大手の出版社への就職は難しいですが、学歴がすべてではありません。
出版社に就職するためには、一般的な就職活動と同様に事前準備が非常に重要です。
加えて、出版業界特有のスキルや経験も求められるため、しっかりと戦略を立てることが必要です。
ここでは、出版社に就職するための具体的な必勝法を6つ紹介します!
しっかり準備して出版社への就職をつかみましょう!
①出版社でアルバイト・インターンをする
出版社でのアルバイトやインターンは、就職活動において大きなアドバンテージになります。実際に現場で働くことで、仕事の面白さや大変さ、そして社風を肌で感じることができます。
ESや面接でのアピール方法
- 「アルバイトで〇〇さんのアシスタントをしていた際、校正作業の正確さを褒められました。この経験から、地道な作業にも粘り強く取り組む力を身につけました。」
- 「インターンで企画会議に参加し、自分のアイデアが採用される喜びを感じました。この経験から、読者のニーズを捉える企画力を磨きたいと強く思うようになりました。」
このように、具体的なエピソードを交えることで、説得力が増します。
②企画力を磨いておく
出版社では、常に新しい企画が求められます。日頃から「こんな本があったら面白いな」と考えるクセをつけましょう。
企画力を磨くためのトレーニング
ターゲットを明確にする:「誰に」「何を」「どうやって」伝えたいのかを考える練習をします。
企画ノートを作る:電車の中やカフェで気になったこと、面白いと思ったこと、読者になったら嬉しい本をメモしておきましょう。
市場調査をする:書店に足を運び、どんな本が売れているのか、どんな本が読者に求められているのかを分析しましょう。
③興味や関心の幅を広く持っておく
世の中のトレンドや読者のニーズをいち早くキャッチし、それを企画に活かすことが求められます。好奇心旺盛な人は、出版社で重宝されます。
アンテナを張る方法
異分野のニュースを読む:ゲーム、アニメ、映画、音楽、アートなど、幅広い分野のニュースに目を通しましょう。
書店巡り:大型書店だけでなく、個人経営の小さな書店にも足を運んでみましょう。
SNSのフォロー:好きな作家や編集者、書店のSNSアカウントをフォローして、情報収集をします。
④文章力を磨いておく
本という「言葉」を扱う仕事なので、語彙力や文章力はもちろん、自分の考えを正確に言葉にして伝える力も大切です。
文章力向上の方法
日記:毎日5分でもいいので、その日にあったことや感じたことを書き出すクセをつけましょう。
ブログやSNSでの発信:自分の好きなことや考えたことを、定期的に文章にしてみましょう。
読書:とにかくたくさんの本を読みましょう。小説、漫画、雑誌、ノンフィクション、なんでもOKです。
⑤大手でなく中堅出版社を狙う
大手出版社は確かに憧れの的ですが、倍率が非常に高いのが現実です。中堅や専門出版社にも、魅力的な会社はたくさんあります。
中堅出版社の魅力
働き方:大手のような激務ではなく、自分のペースで仕事ができる会社も多いです。
少数精鋭:社員数が少ないため、一人ひとりの裁量権が大きく、若いうちから大きな仕事を任されるチャンスがあります。
特定のジャンルに特化:特定の分野に特化した出版社であれば、自分の「好き」を突き詰めることができます。
⑥関連資格を取って熱意を示す
必須ではありませんが、日本語検定や校正技能検定といった資格を取得することで、「本に関わる仕事がしたい」という強い熱意をアピールできます。
ESや面接では、資格の有無だけでなく、「なぜその資格を取ろうと思ったのか」「資格の勉強を通じて何を学んだのか」を具体的に話すことが重要です。
【まずは、就活アプリをいれてみよう!】おすすめ就活アプリを紹介!
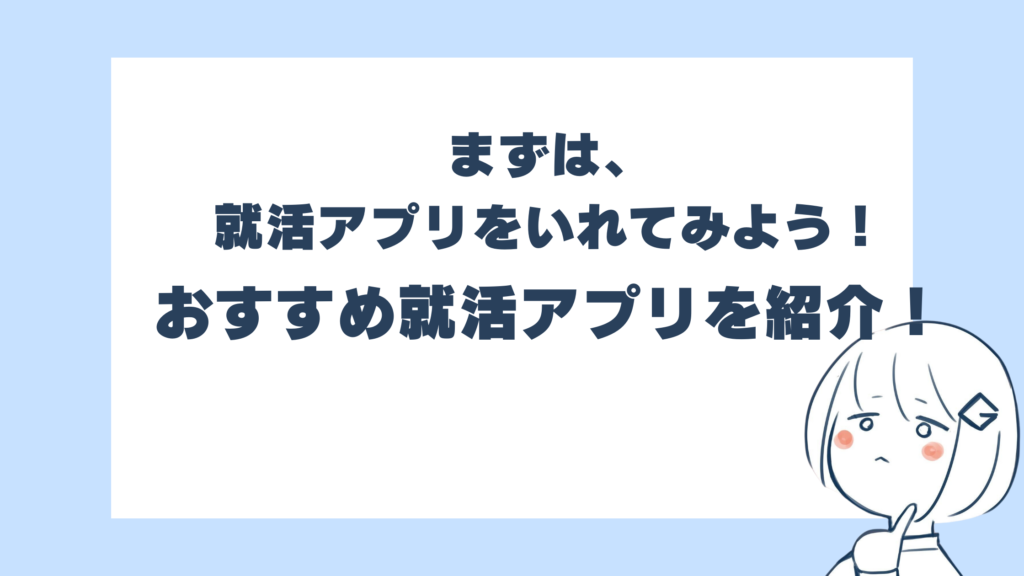
就活をスムーズに進めるために、まずは就活アプリを活用することをおすすめします。
エントリー管理や企業の情報収集、スケジュール管理など、効率的に就活を進めるために役立つ機能が満載です。
多くの就活生が利用しているアプリを導入し、効率よく準備を進めましょう。
就活アプリについてもっと知りたい方はこちら!
【まずは、就活サイトを使ってみよう!】おすすめ就活サイトを紹介!
Lognavi
Lognaviは知的検査も含めた適性検査を行うことができる就活サイトです。
適性検査はよくあるWebテストに近い形式になっていて、知的検査の偏差値も分かります。
そして、最大の特徴が、適性検査の結果をもとに相性が良い企業を紹介してくれることです。
適性検査後に、自動でマッチング度の高い企業を紹介してくれます。
また、同じ学校や同じ企業を志望する人とコミュニティで繋がることができるため、情報共有にも有利な就活サイトです。
知的検査も含めたWebテストがアプリ内で受験できるので、最も選考免除の特典が多いスカウトアプリです。
【15万人が利用】適性診断で相性が良い企業が見つかる就活アプリ!【Lognavi】

就活会議
就活会議は、企業情報が確認できるだけでなく、内定者のESや面接情報が口コミで確認できる就活サイトです。
また、従業員からの社内の評価や、実際の雰囲気なども確認できるため、自分に合わない企業の回避にもつなげることができます。
インターンシップの案内やスカウトも数多く届くサイトです。
企業の雰囲気や内容、選考に通るコツなどを知りたい人にオススメのサイトです!
Matcher
Matcherは、4万人以上の社会人が登録している最大手のOB/OG訪問サイトです。
最大の特徴は、同じ大学出身でないOB・OGとも話せることで、これにより業界や職種の幅を広げて情報収集ができます。
使い方もとても簡単で、検索画面から「プランのもっと詳しく」を選択し、「このプランに申し込む(学生)」を選択するだけで申し込みができる手軽さが魅力です。
また、Matcherの大きな特徴として、カジュアルでフランクな雰囲気の募集が多いことが挙げられます。
社会人は「就活相談に乗る代わりに○○してください」という構文で面談募集をしているのですが、この「○○してください」の部分が「オススメのドラマを教えてください」といった気軽な内容になっているため、初めてOB/OG訪問をする就活生でもハードルが低く感じられます。
緊張せずにリラックスして話ができる環境が整っているので、OB/OG訪問初心者には特におすすめです。
国内最大級のOB・OG訪問支援サービス【Matcher(マッチャー)】
まとめ
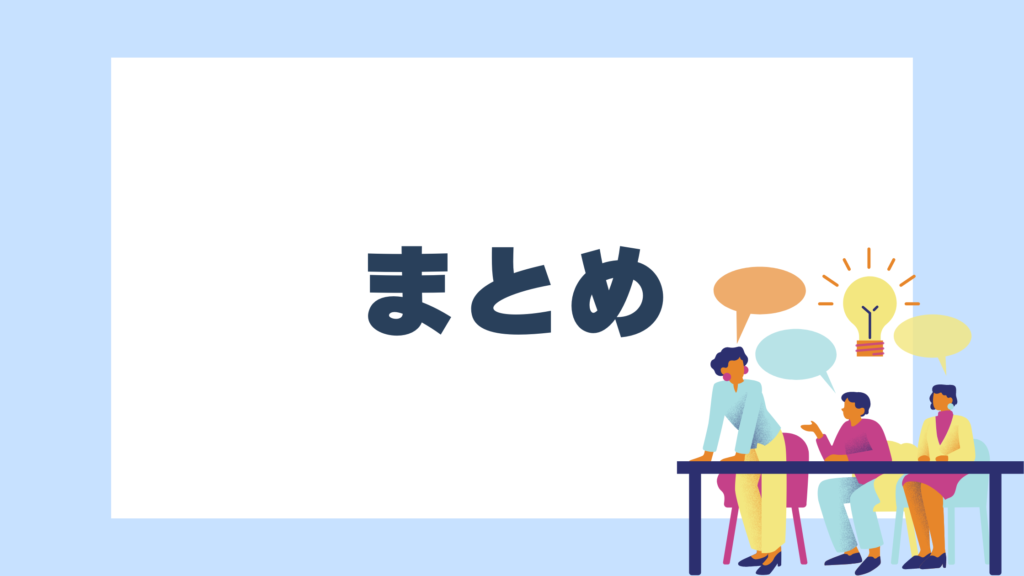
出版社に就職するための必勝法は、多岐にわたる経験とスキルの習得が鍵です。
また、幅広い知識と興味を持ちながら、自分の強みをアピールできる戦略を立てることが大切です。
ここで出版社に就職するための必勝法を振り返りましょう!
- 出版社でアルバイト・インターンをする
- 企画力を磨いておく
- 興味や関心の幅を広く持っておく
- 文章力を磨いておく
- 大手でなく中堅出版社を狙う
- 関連資格をとって熱意を示す
加えて、資格の取得や中堅出版社を視野に入れた柔軟なアプローチも、競争率の高い出版業界で内定を勝ち取るための重要なステップです。
これらを踏まえて出版社への内定をつかみ取りましょう!

目指せ、納得内定!