こんにちは!27卒のkenichiです!
この記事を開いてくださった就活生の皆さんは、
- いつからWebテストの対策をしたらいいか
- 最短で合格点を取る方法が知りたい
と悩んでいるのではないでしょうか?
勉強って普通にめんどくさいし楽にできるならやりたいですよね…
この記事では
- Webテスト対策はいつから?どのぐらい?
- 高得点が取れるレベル別勉強法
を紹介していきます!
ぜひ最後までお読みください!
Webテストに関する記事はこちら!
【例文】webテストの締切が過ぎた!受け忘れた時のメール – WorkRise 学生が学生に届ける就活メディア
【完全ガイド】WebテストCABは難しすぎ?電卓は使える? – WorkRise 学生が学生に届ける就活メディア
Webテスト「玉手箱」完全対策!監視型の見分け方も – WorkRise 学生が学生に届ける就活メディア
Webテスト対策はいつから始めるのがベスト?
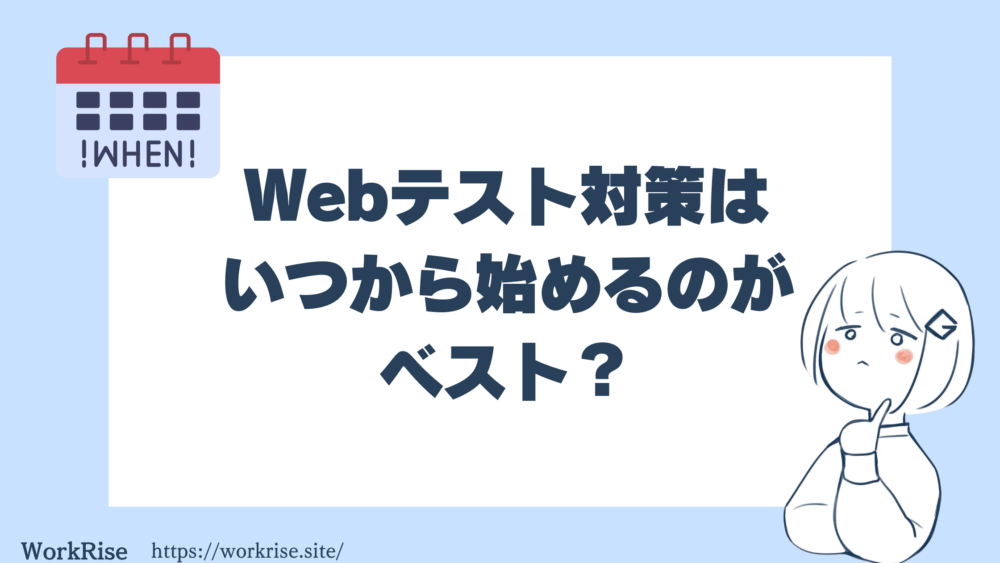
理想的な開始時期は、就活が本格的に始まる前の3〜4カ月です。
Webテストは単純な対策だけでなく、問題を正確に解くスピード感が大事になってきます。なので、1カ月前からの準備となってくると、知識として頭に入っても本番でミスが多くなります。
最低でも、テスト1週間前には時間配分の練習をしておきましょう!

問題に時間をかけすぎないようにしないと…
Webテストの種類と対策の優先度
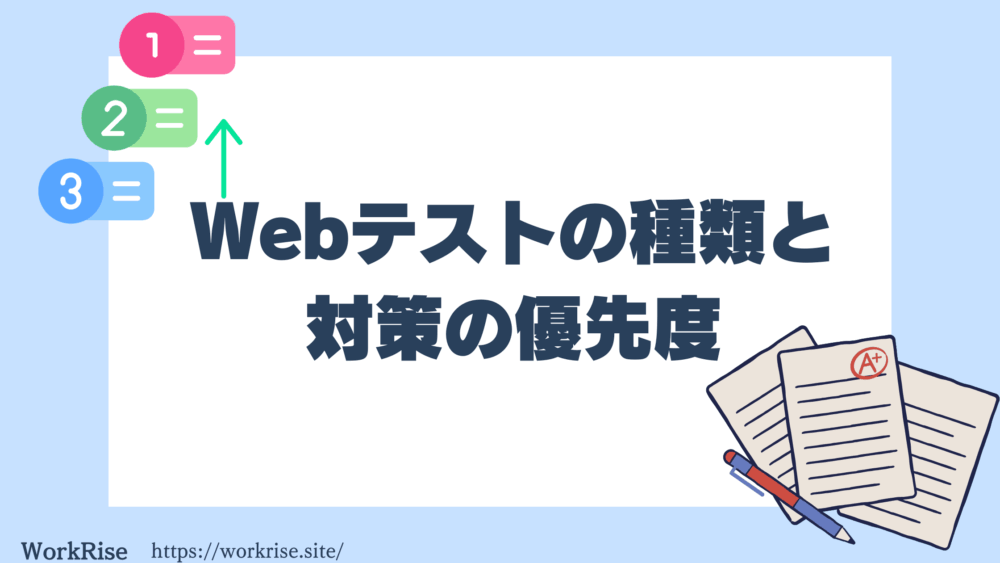
Webテストといっても種類がかなりあります。企業によってはもらったURLを開いて初めてどのテストがわかるケースもあるので、複数のテストを同時に対策する必要があります。でも…

どれからやったらいいか…
という人が多いと思います。
ここからは、企業によく採用されるWebテスト順に紹介していきます!まだ対策を始めてない人は、参考にしてください!
SPI
SPIは、Webテストの中で一番よく使われているテストです。
基礎能力を幅広く見るWebテストなので、このテストの対策は他のWebテストの対策にもなります。Webテストの対策は、まずSPIから始めていきましょう!
詳しい解説は以下の記事をチェック!
玉手箱
玉手箱は、SPIより難しいWebテストでこれも総合力が求められるテストになります。
SPIと違うのは、論理的な判断力がより重視される点です。SPIで安定して模試の点数が取れていたら玉手箱に取り掛かると両方しっかり対策ができます!
TG-Web
TG-Webは、Webテストの中でも即戦力のある就活生が欲しい企業が採用されるものです。
具体的には、作られた場面であなたならどうするかという判断問題が出題されます。このテストを対策するなら、早めに模試を使って思考を柔軟にしておくのが高得点を取りやすいです!
GAB
GABテストは、抽象的思考力が見られるWebテストになります。
抽象的思考力とは、事柄の細かいところではなく全体を認識することです。ビジネスではこういった能力も大切になるので、こちらも模試を通して練習が必要です。
CAB
CABは、企業や職種ごとに問題がカスタマイズされるWebテストになります。
具体的には、「状況判断テスト」という具体的な業務場面を想定した問題があります。これはもちろんあなたが志望する企業によって変わるので、企業の情報収集やOB訪問が効果的な対策になります。
CABの詳しい記事は以下をクリック!
Webテスト対策の心得5選
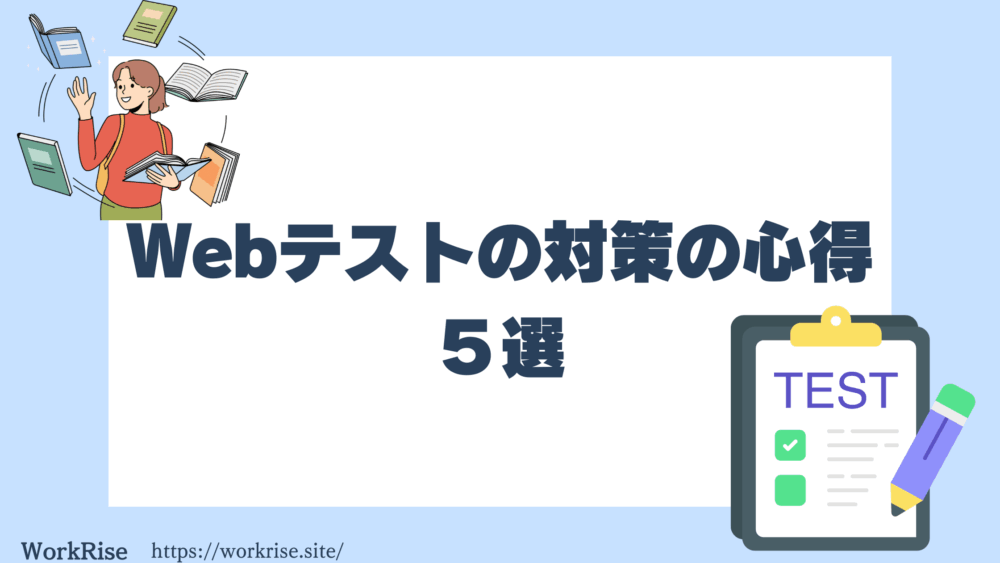

Webテストの勉強方法が分からない!

この勉強法でいいのかな?
と自分の勉強法に不安や悩みを持っている就活生が一定数いると思います。
なのでここからは、僕自身や後輩に教えて実際に点数があがったWebテストの対策で意識すべきところを5選紹介します!
勉強の量と質を意識する
勉強を長時間できたら、誰しも達成感を感じたり、頑張ったと思うのではないでしょうか?でも、

7時間で5ページ進んだ!

3時間で8ページ進んだ!
を比べた時、どっちが勉強してそうってなったら後者ですよね。
勉強時間は確かに見えやすいから意識しがちだけど、正しいやり方でやっていけば短い時間でも効率よく勉強できます!
問題集を最初から解かない
1ページから問題集を解くのが基本だと思いますがそこをあえて、違う順番で試してみてほしいです!おすすめは、
- 各章のまとめだけを読む
- 見出しや図、解答のコツを読む
- 冒頭から全て読む
この順番で理解できた後に問題を解くと普通に一周するよりもスッと頭に入ります。

余裕がある人は、4周目もやって固めていこう!
時間配分の練習
冒頭でも説明した通り、Webテストは時間配分が大切になってきます。
問題の正答率を上げた後は、それを制限時間内に正答率をキープする練習もしておくと、当日失敗が少ないです。
復習は選択と集中
Webテストは就活の序盤にありますが、他にもやるべきことがあるので時間が限られてきます。
正解して解き方までわかっている問題は時間に余裕がある時だけで「なんとなく解けた」・「解けなかった」問題を優先して復習するようにしましょう。
当日、解ける問題だけを解く
誰しも分野・問題の不得意があると思います。当日全部余裕持って解けることが理想ですが、なかなかそうはいきません。
本番でもし時間がかかそうな問題を見つけた場合は、一度飛ばしてサクッと解ける問題を優先して解くようにしましょう。
確実に取れるところを逃がすことがないので高得点の近道です!
Webテスト対策にかかる時間は?
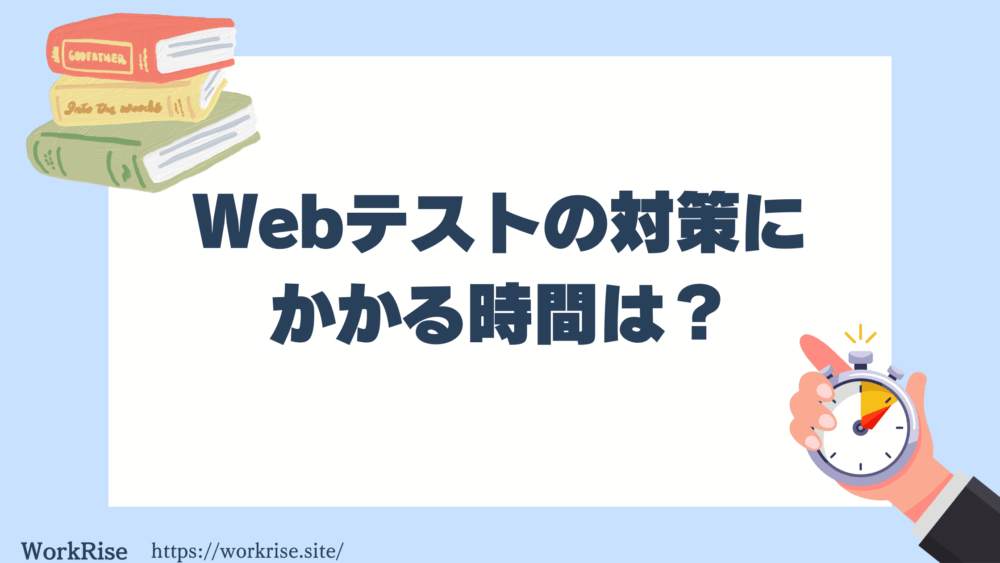
対策を始める時にどのぐらい時間をかけるべきか気になったことってありませんか?
合格している人の勉強時間がわかれば、だいぶ楽ですよね?
そこで合格者の平均時間を計画の立て方も含めて解説していきます!
合格者の平均時間
Webテストに合格している人は、最低でも30時間、平均では50~60時間ぐらい勉強しています。
ただ、人によって苦手分野があったり、テストによって時間配分が変わってくるのであなたに合わせた段階的な計画を立てることが大切になってきます。
マッチャーというサイトでは、SPIの勉強スケジュールを例にこんな計画の立て方があります。
Webテストの勉強を始める人は、参考にしてみてください!
【16選】テストセンターの分野別対策方法を問題傾向とともに解説 | MatcherDictionary
短期集中 vs コツコツ派、それぞれの勉強法
おすすめのWebテスト対策として「短期集中型」と「コツコツ型」があります。
短期集中型は、1日3時間~4時間を2週間から3週間の短期間で集中して勉強する。一方でコツコツ型は、1日1~2時間を2~3カ月と短期集中型とくらべて長期間で勉強します。
どちらの勉強法も共通して重要なのは、期間ごとに目標を設定することです。例えば、短期集中型なら1週目は基礎、2週目は応用、3週目は模試と細かく決めて段階的に勉強するとより効果的です。
レベル別!おすすめの勉強スケジュール
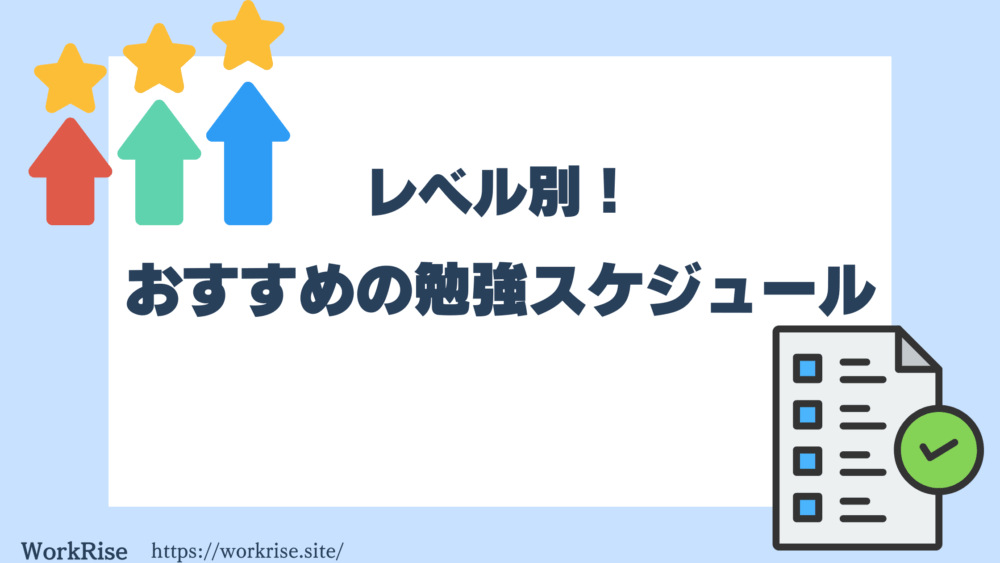
まだ何もしてない人向け
まだ対策を始めていない人は、1カ月〜3カ月ぐらいの計画スケジュールがおすすめです。短期集中型とコツコツ型に分けて参考例を説明していきます!
短期集中型
- 1週目は基礎固めの期間
- 2週目は応用力を高める期間として、より複雑な問題や実践的な問題
- 3~4週目は総仕上げとして、実際のテスト形式に近い条件で模試に取り組む
コツコツ型
- 1ヶ月目は基礎固めの期間
- 2ヶ月目は応用力を高める期間として、より複雑な問題や実践的な問題
- 3ヶ月目は総仕上げとして、実際のテスト形式に近い条件で模試に取り組む
少し対策を始めた人向け
まだ対策を始めたばかりの人は、1カ月〜2か月程度の期間で前半は苦手な分野の補強で後半は、総合演習を増やすと効率よく勉強できます。
直前対策したい人向け
テスト直前の1週間〜2週間という人は、とにかく効率と実践を重視していきましょう。
1週目は、頻出問題の解答パターンを徹底的に勉強して確実に解けるようにします。テスト5日~3日前からは模試を使って実践的な勉強をして、時間配分と集中力の維持をできるようにしましょう。
またどこかで自己分析をして性格検査の対策もやっておくと当日困ることが少ないです!
まとめ
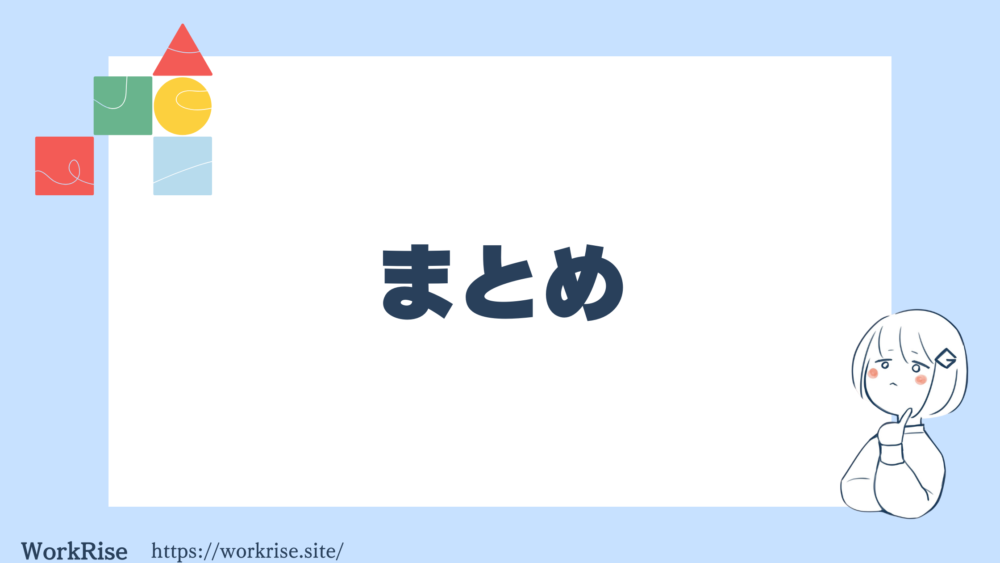
今回は、
- いつからWebテストを勉強するか
- どのテストを先に始めるか
- どのようなスケジュールを立てるか
について解説しました!
Webテストの勉強は、計画とやり方で決まります。直前になっても焦らず、テストの種類や日付・自分の今の進捗度など全体を把握してからどのような勉強をするかを計画していくことで高得点に繋がります。




