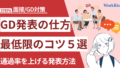こんにちは!27卒ライターのFujiです。
今回はグループディスカッションの練習方法について解説していきます!
近年、選考にグループディスカッション(GD)を取り入れる企業が増えてきました。

グループディスカッションって苦手……
そんな人は案外多いのではないでしょうか?
今回は、そんなグループディスカッションの練習方法を、一人でもできるものを中心に紹介していきたいと思います!
これを読めばグループディスカッションはもう怖くありません!ぜひ最後まで読んでくださいね♪
- グループディスカッション練習を行うメリット
- 一人でできる効果的な練習方法
- AIを活用したな練習方法と具体的なプロンプト例
- グループディスカッションで選考通過するためのコツ
グループディスカッションの練習に参加するメリット
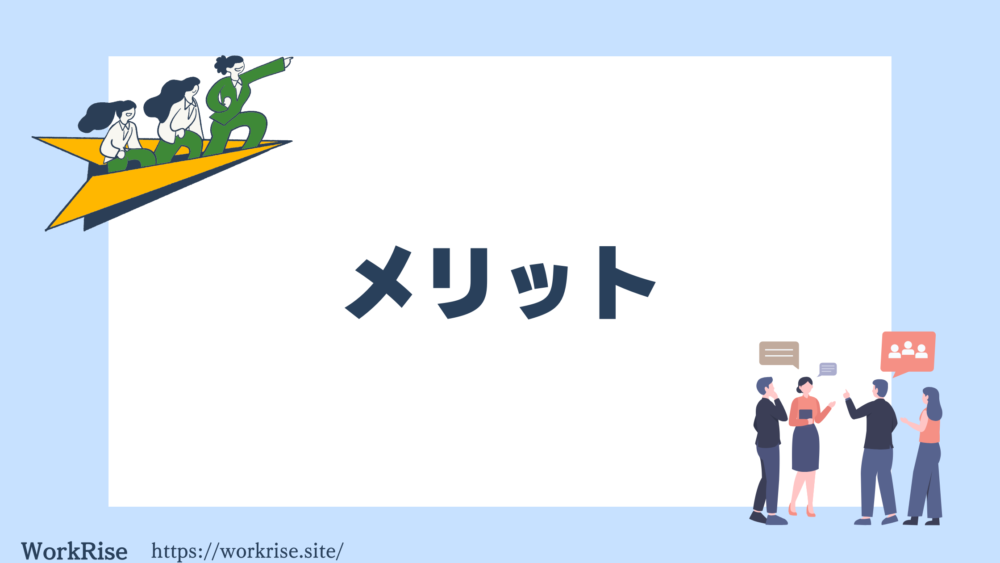
グループディスカッションは事前に練習することで確実に上達する選考方法です。
練習に参加することで得られるメリットを詳しく見ていきましょう。
実践的な経験を積める
グループディスカッションの練習に参加する最大のメリットは、実践的な経験を積めることです。
本番と同じような環境で何度も練習することで、緊張せずに自分の力を発揮できるようになります。
初めてグループディスカッションに参加する人は、時間配分がわからなかったり、どのタイミングで発言すれば良いかわからなかったりして、本来の実力を発揮できないことが多いです。
しかし、練習を重ねることで議論の流れが掴めるようになり、適切なタイミングで効果的な発言ができるようになります。
この経験の蓄積が自信と落ち着きに繋がり、本番でのパフォーマンス向上に直結するのです。
また、様々なテーマでの練習を通じて、幅広い分野の知識や考え方に触れることができるのも大きなメリットです。
役割の適性を見つけられる
グループディスカッションでは様々な役割がありますが、練習を通じて自分がどの役割に適しているかを発見できます。
リーダーシップを発揮するのが得意な人もいれば、アイデアを出すのが得意な人、他のメンバーをサポートするのが得意な人もいます。
練習の中で色々な役割を試してみることで、自分の強みを活かせるポジションを見つけることができるのです。
例えば、発言は多くないけれど的確な意見を述べるタイプの人は、タイムキーパーや書記といった役割で貢献度を高められるかもしれません。
逆に、アイデア豊富で発言力のある人は、議論を主導する役割が向いているでしょう。
自分の適性を理解することで、本番でより効果的に立ち回ることができるようになります。
フィードバックを通じて改善点を知れる
練習会では、他の参加者や運営スタッフからフィードバックをもらえることが多いです。
このフィードバックは、自分では気づかない癖や改善点を知る貴重な機会になります。
例えば、「発言内容は良いけれど、もう少し簡潔にまとめると伝わりやすい」「他の人の意見をもっと聞く姿勢を見せると良い」といった具体的なアドバイスをもらえます。
客観的な視点からの意見は、自己分析だけでは気づけない盲点を教えてくれるため、確実な成長に繋がります。
また、他の参加者の良い点を観察することで、自分に取り入れられる要素を見つけることもできます。
「あの人の発言の仕方は参考になる」「この進行方法は真似してみよう」といった学びを得ることで、総合的なスキルアップが期待できるのです。
一人でもできる!グループディスカッション練習方法3選
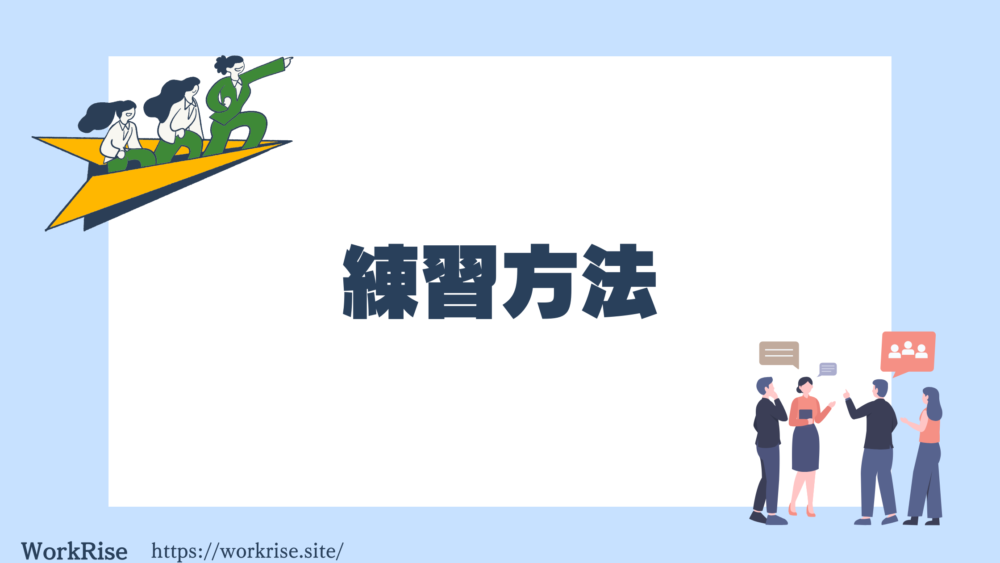
「練習したいけど一緒にやってくれる人がいない…」そんな悩みを持つ人も多いですよね。
でも大丈夫です!一人でもできる効果的な練習方法があります。
ニュースを見て疑問や意見を書き出す
最も手軽で効果的な練習方法が、日々のニュースを見て自分なりの疑問や意見を書き出すことです。
グループディスカッションでは時事問題や社会課題がテーマになることが多いため、普段からニュースに関心を持っておくことが大切です。
ニュースを見る際は、ただ情報を受け取るだけでなく「なぜこの問題が起きているのか?」「どんな解決策があるか?」「反対意見はどんなものがあるか?」といった視点で考えてみましょう。
これらの疑問や意見をノートやスマホのメモ機能に書き出しておくことで、論理的思考力と発言力の両方を鍛えることができます。
また、書き出した内容を後で見返すことで、自分の考えの変化や成長を実感できるのも大きなメリットです。
毎日10分程度でもこの練習を続けることで、確実にグループディスカッションでの発言力が向上します。
YouTubeなどの動画を見てGDの流れやコツを学ぶ
YouTubeには実際のグループディスカッションの模様を撮影した動画や、専門家によるコツ解説動画が数多く投稿されています。
これらの動画を見ることで、議論の進め方や効果的な発言のタイミング、チームワークの築き方などを学ぶことができます。
特に、実際の選考で使われたテーマでのグループディスカッション動画は非常に参考になります。
「こんな風に議論が進むんだ」「この人の発言の仕方は上手いな」といった気づきを得ることで、本番でのイメージを具体的に持つことができるでしょう。
動画を見る際は、単に視聴するだけでなく、「自分だったらここでどんな発言をするか?」「この場面でどう議論を軌道修正するか?」といった視点で能動的に観察することが重要です。
また、気に入った発言や進行方法があれば、メモを取っておいて実際の練習で試してみるのもオススメです。
SNSで様々なタイプの意見を集め、自分の意見と比較検討する
TwitterやInstagramなどのSNSは、多様な意見に触れる絶好の場です。
同じニュースや出来事に対しても、人によって全く異なる視点や意見を持っていることがわかります。
SNSで様々な意見を集めて、自分の考えと比較検討することで、多角的な視点を養うことができます。
「なるほど、こんな見方もあるのか」「この意見の根拠は何だろう?」といった形で、他者の意見を分析的に読む習慣をつけましょう。
また、炎上している話題などを観察することで、「なぜ意見が対立するのか」「どうすれば建設的な議論にできるか」を考える練習にもなります。
ただし、SNSの情報は必ずしも正確ではないため、信頼できるソースで事実確認を行う習慣も身につけることが大切です。
この練習を続けることで、グループディスカッションで様々な立場の意見を理解し、調整する能力が身につきます。
より実践的な経験が積めるグループディスカッション練習方法3選
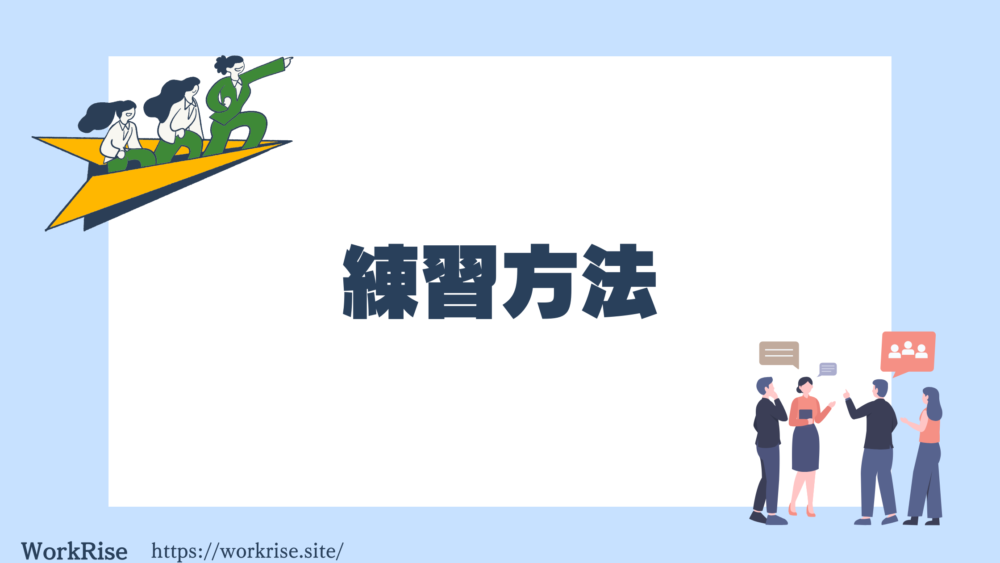
一人での練習も大切ですが、やはり実際に人と議論する経験も欠かせません。
より実践的な練習方法をご紹介します。
練習会やセミナーに参加する
最も確実で効果的な方法が、グループディスカッションの練習会やセミナーに参加することです。
大学主催のイベントもあるし、就活サービスが主催のもの、企業主催の練習会もあります。
大学のキャリアセンターでは、定期的にグループディスカッション対策講座を開催していることが多いです。
同じ大学の学生同士で練習できるため、気軽に参加しやすいのがメリットです。
就活サービスが主催する練習会は、他大学の学生とも交流できるため、様々なタイプの人との議論経験を積むことができます。
また、プロの講師からフィードバックをもらえることが多いのも大きな魅力です。
企業主催の練習会は、その企業の選考傾向を知ることができる貴重な機会でもあります。
「この企業はこんなポイントを重視しているんだ」といった気づきを得ることで、本選考での対策も立てやすくなります。
どの練習会に参加する場合でも、積極的に発言し、他の参加者からも学ぼうとする姿勢が大切です。
グループディスカッションが多い授業を積極的に受講する
大学の授業の中には、グループワークやディスカッション形式のものが多く含まれています。
これらの授業を積極的に受講することで、自然にグループディスカッションのスキルを身につけることができます。
特に、ゼミやプレゼンテーション系の授業、社会課題を扱う授業などは、就活のグループディスカッションに近い形式で議論が行われることが多いです。
普段の授業では緊張せずに発言できるため、自分の考えを整理して伝える練習を重ねることができます。
また、同じメンバーで複数回議論を行うことで、チームワークの築き方や役割分担のコツも自然に身につきます。
授業での経験を就活に活かすためには、議論の進め方や自分の発言を意識的に振り返ることが重要です。
「今日の議論で良かった点」「改善できる点」を毎回メモしておくと、着実にスキルアップできるでしょう。
友達と協力する
就活仲間や友達と協力してグループディスカッションの練習を行うのも効果的な方法です。
お互いに練習相手になることで、双方にとってメリットのある練習ができます。
友達同士での練習は、リラックスした雰囲気で行えるため、まずは「グループディスカッションに慣れる」という段階の人には特にオススメです。
また、お互いの性格や特徴を知っているからこそ、的確なフィードバックを交換することもできます。
ただし、馴れ合いだけは要注意です。
友達同士だからといって緊張感のない練習をしていると、本番で力を発揮できない可能性があります。
練習の際は、本番と同じような緊張感を持って取り組むことが大切です。
また、毎回異なるテーマで練習したり、役割をローテーションしたりすることで、より実践的なスキルを身につけることができるでしょう。
【一人で練習】AIを活用したグループディスカッションの練習方法
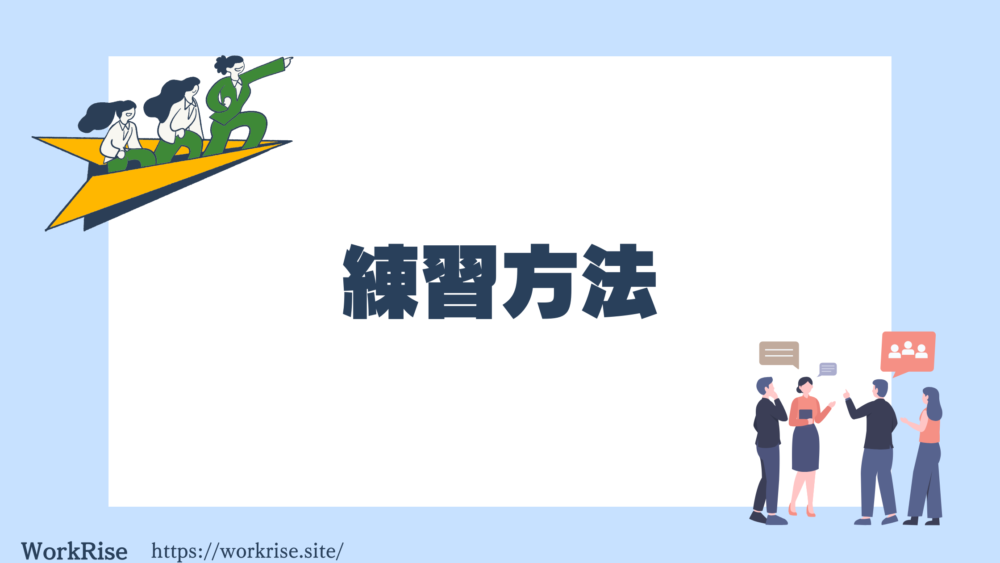
最近注目されているのが、AIを活用したグループディスカッションの練習方法です。
革新的で効果的なこの方法について詳しく解説していきます。
AIでグループディスカッションの練習はできる?
結論から言うと、AIを使ったグループディスカッションの練習はできます。
ChatGPTやGemini、Claude などの対話型AIを使えば、様々な役割を演じてもらいながら議論の練習を行うことが可能です。
特に、生成スピードが早く、無料でも利用できる回数の多いChatGPTやGeminiの利用がオススメです。
AIを使った練習の最大のメリットは、24時間いつでも練習できることと、恥ずかしさを感じずに思い切って発言できることです。
「こんなことを言ったら変に思われるかな?」といった心配をする必要がないため、普段は言えないような大胆な意見も試すことができます。
ただし、AIには人間特有の感情や非論理的な反応がないため、実際の人間同士の議論とは異なる部分もあることは理解しておきましょう。
それでも、論理的思考力や発言力の向上には十分効果的な練習方法です。
AIでグループディスカッションの練習を行うためのプロンプト
AIを使って効果的な練習を行うためには、適切なプロンプト(指示文)を使うことが重要です。
以下に、具体的なプロンプト例をご紹介します。
プロンプト例1:AIに議論の参加者になってもらう
「あなたは今から私のグループディスカッションの練習相手です。与えられたテーマについて、他の参加者として発言し、議論を進めてください。私の発言に対して質問をしたり、意見を述べたり、異なる視点を提供したりしてください。 テーマ: 『少子高齢化社会において、若者の社会貢献意欲を高めるにはどうすべきか』 議論を始めてください。」
このプロンプトを使うことで、AIが議論の参加者として様々な意見を提示してくれるため、多角的な視点で議論の練習ができます。
プロンプト例2:AIにファシリテーターになってもらう
「あなたは今からこのグループディスカッションのファシリテーターです。以下のテーマについて、私の発言を促し、議論の方向性を整理し、時間管理を行い、結論に導く役割を担ってください。 テーマ: 『リモートワークが普及する中で、チームの生産性を維持・向上させるための施策とは』 議論を始めてください。」
このプロンプトでは、AIが議論を進行してくれるため、参加者としてのスキルを重点的に練習することができます。
プロンプト例3:AIに特定の役割(例:反対意見の役割)になってもらう
「あなたは今から、このグループディスカッションにおいて、常に現状維持を主張し、変化に反対する立場を取る参加者として振る舞ってください。私の提案に対しては、慎重な姿勢で反論を試みてください。 テーマ: 『企業のDX推進を加速させるための具体的な戦略』 議論を始めてください。」
このプロンプトを使うことで、異なる立場の人との議論に慣れることができ、説得力のある論理展開の練習になります。
プロンプト例4:AIに複数の役割と評価をさせる
「あなたは今から、グループディスカッションのシミュレーションを行います。以下の役割を演じ、テーマについて議論を進めてください。 役割1: 主に賛成の立場から意見を述べる参加者 役割2: 主に反対の立場から意見を述べる参加者 役割3: 議論をまとめ、時間管理を行うファシリテーター 議論中は、私が発言するたびに、私の発言内容の論理性、協調性、具体性について簡単にフィードバックをしてください。最後に、ディスカッション全体の評価と改善点を教えてください。 テーマ: 『AI技術の発展が社会に与えるポジティブな影響とネガティブな影響、そしてその対策』 議論を始めてください。」
このプロンプトは最も高度で、複数の参加者がいる議論を疑似体験できるとともに、リアルタイムでフィードバックももらえる優れた練習方法です。
AIでグループディスカッションの練習を行うメリット
AIを使った練習には、従来の方法にはない独特のメリットがあります。
まず、フィードバックがもらえることです。
AIは客観的な視点から、あなたの発言の論理性や具体性、協調性などを評価してくれます。
人間からのフィードバックとは異なり、感情に左右されない冷静な分析を受けることができるのは大きなメリットです。
次に、ログが残るので、議論が停滞した部分や進展した部分がどこか分かりやすいことです。
チャット形式で議論が記録されるため、後から振り返って「この発言で議論が活性化した」「ここで論点がずれてしまった」といった分析ができます。
この振り返りを通じて、自分の議論スキルを客観的に評価し、改善点を見つけることができるのです。
そして最大のメリットは、一人でも気軽に練習が行えることです。
時間や場所を選ばず、思い立った時にすぐ練習できるため、継続的なスキルアップが可能になります。
「今日は少し時間があるから練習してみよう」といった気軽さで取り組めるのは、忙しい就活生にとって非常に便利な特徴です。
アプリを使ってグループディスカッションの練習相手を見つける
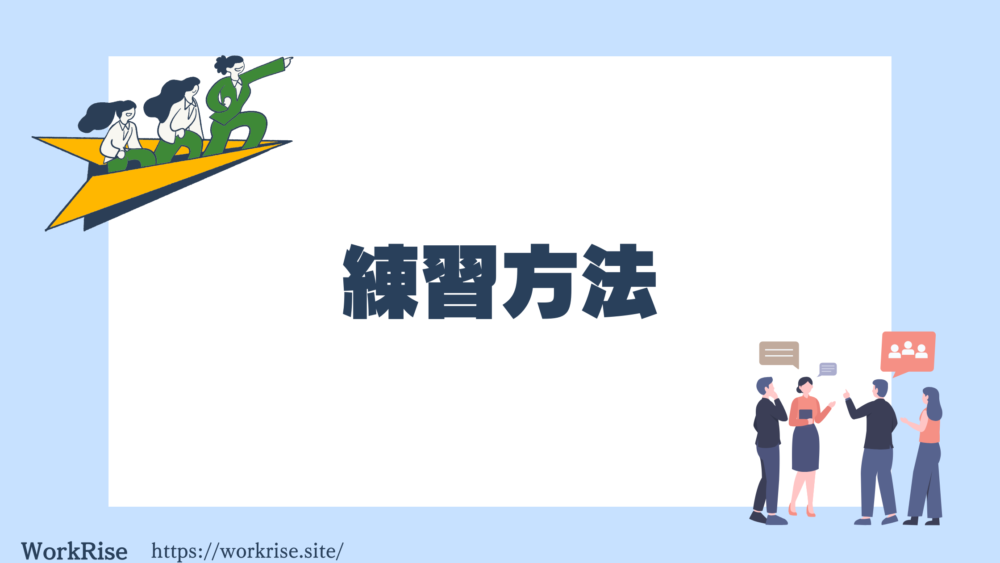
一人での練習も大切ですが、やはり実際の人との議論経験も積みたいですよね。
そんな時に便利なのが、アプリを活用した練習相手探しです。
OG/OG訪問アプリを活用
OB/OG訪問アプリは、練習相手を見つけるだけでなく、実際の選考情報を得ることもできる一石二鳥の方法です。
オススメは登録者数が国内で一番多いMatcherです。
Matcherには多くの社会人と学生が登録しているため、グループディスカッションの練習に協力してくれる人を見つけやすいのが特徴です。
OB/OG訪問をすると実際にGDで出題されたテーマが分かることも多く、より実践的な練習ができます。
「この企業では環境問題についてのグループディスカッションがあった」「時間配分はこんな感じだった」といった具体的な情報を教えてもらえることもあります。
また、社会人の視点から「企業はこんなポイントを見ている」といったアドバイスをもらえるのも大きなメリットです。
ただし、相手の時間を尊重し、事前にしっかりと準備をしてから訪問することが大切です。
国内最大級のOB・OG訪問支援サービス【Matcher(マッチャー)】
就活コミュニティのあるアプリを活用
同じように就活を頑張っている学生同士で練習相手を見つける方法もあります。
TwitterやInstagramなどのSNSで募集してみるのも一つの手です。
「#就活」「#グループディスカッション練習」といったハッシュタグを使って募集すると、同じように練習相手を探している学生と出会える可能性があります。
特にオススメなのが、Lognaviの学生コミュニティです。
Lognaviの学生コミュニティは招待制なので危険が少なく、意欲のある学生が集まっているのでより効果的な練習ができます。
招待制のコミュニティは、本気で就活に取り組んでいる学生が多いため、高い質の練習を期待できます。
お互いに真剣に取り組むことで、より実践的で効果的な練習ができるでしょう。
また、継続的に練習を行える仲間を見つけることで、長期的なスキルアップも期待できます。
【15万人が利用】適性診断で相性が良い企業が見つかる就活アプリ!【Lognavi】

グループディスカッションで選考通過するコツ3選
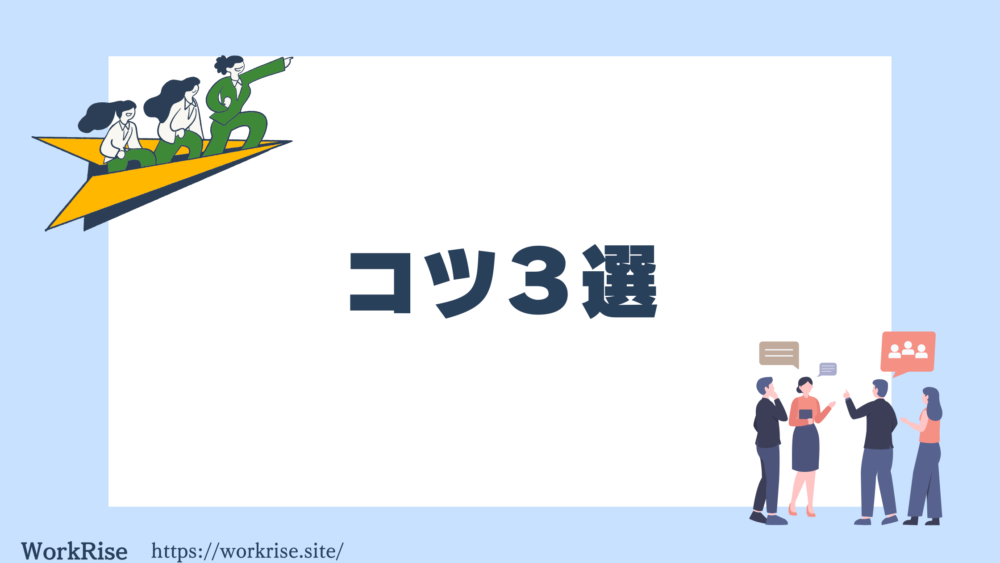
グループディスカッションで選考を通過するためには、戦略的なアプローチが必要です。
以下の3つのコツを実践することで、企業から高い評価を得られる可能性が大幅に向上します。
積極的に議論に貢献する
積極的に議論に貢献するといっても、ただ発言回数を増やせば良いというわけではありません。
大切なのは、議論の流れを意識して適切なタイミングを図ることです。
相手が話している最中に割り込んだり、同じような内容を繰り返し発言したりするのは逆効果になってしまいます。
特に効果的なのは、議論の冒頭で議題の前提確認をしたり、議論の進め方を提案するなど、議論を主導する姿勢を見せることです。
例えば、「まず今回のテーマについて、皆さんと認識を合わせてから議論を始めませんか?」といった提案や、「残り時間が少ないので、一度これまでの意見をまとめて、結論に向けて話し合いましょう」といった進行管理は高く評価されます。
このような発言は、リーダーシップと状況判断能力の両方をアピールできる効果的な方法なのです。
チームワークを重視し、協調性を示す
チームワークを重視する姿勢は、具体的な行動で示すことが大切です。
他のメンバーの意見に共感を示したり相槌を打つなど、理解を示す姿勢を見せることから始めましょう。
「なるほど、〇〇さんの視点は面白いですね」「その考え方は気づきませんでした」といった反応は、相手を尊重していることを表現できます。
さらに重要なのが、発言できていないメンバーに対して話を振ることです。
「△△さんはこの点についてどう思いますか?」と自然に話を振ることで、チーム全体の議論を活性化させる役割を果たせます。
また、意見が対立した時に論理的に解決策を探る姿勢も評価されます。
感情的になったり、自分の意見を押し通そうとしたりするのではなく、「両方の意見にメリットがありますが、今回の条件を考えると…」といった形で建設的に議論を進めることが大切です。
自分の役割を全うする
グループディスカッションでは、タイムキーパーや書記、発表者などの役割が設定されることが多いです。
自分に与えられた役割はきちんとこなし、議論を回すことに集中してしまって疎かになることが無いようにしましょう。
例えば、タイムキーパーに立候補した場合は、定期的に残り時間をアナウンスし、議論のペース配分を意識した発言をすることが求められます。
書記の場合は、議論の要点を的確にまとめ、必要に応じて確認を取りながら進めることが重要です。
役職は自分から先に立候補すると積極性がアピールできます。
「私がタイムキーパーを務めさせていただきます」「書記をやらせてください」といった形で積極的に手を挙げることで、責任感と主体性の両方を示すことができます。
ただし、役割を選ぶ際は自分の得意分野を考慮することも大切です。
人前で話すのが苦手な人が発表者に立候補すると、本来の能力を発揮できない可能性があるからです。
まとめ
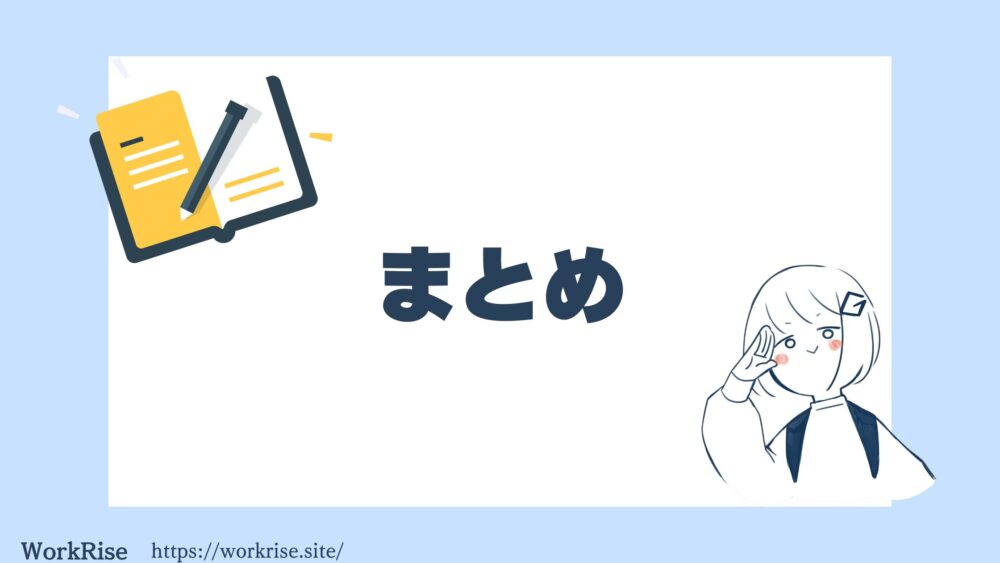
グループディスカッションの練習方法は多種多様で、一人でもできる方法から、AIを活用した革新的な方法まで様々な選択肢があります。
特に、ニュースを見て意見をまとめる練習や、AIを使った議論シミュレーションは、時間や場所を選ばずに行える便利な方法です。
より実践的な経験を積みたい場合は、練習会への参加や友達との協力、アプリを使った練習相手探しも効果的です。
どの方法を選ぶにしても、継続的に練習を重ねることが最も重要です。
そして本番では、積極的な貢献、チームワークの重視、役割の完遂という3つのコツを意識することで、企業から高い評価を受けることができるでしょう。
グループディスカッションは確かに難しい選考方法ですが、適切な練習を重ねることで必ず上達します。
今回紹介した方法を参考に、自分に合った練習方法を見つけて、ぜひチャレンジしてみてくださいね!