こんにちは!28卒ライターのMiaです。
「インターンでグループディスカッション選考があるけど上手く出来る気がしなくて不安…。」
「自分は大人しいタイプだから、グループディスカッションで喋れる気がしない…。」
「企業は、グループディスカッション選考でどんなところを見てるんだろう?」
という悩みを持つ方は多いのではないでしょうか!
本記事ではインターンでのグループディスカッションのあれこれを紹介していきます!
インターン選考でなぜグループディスカッション(GD)が行われるのか?
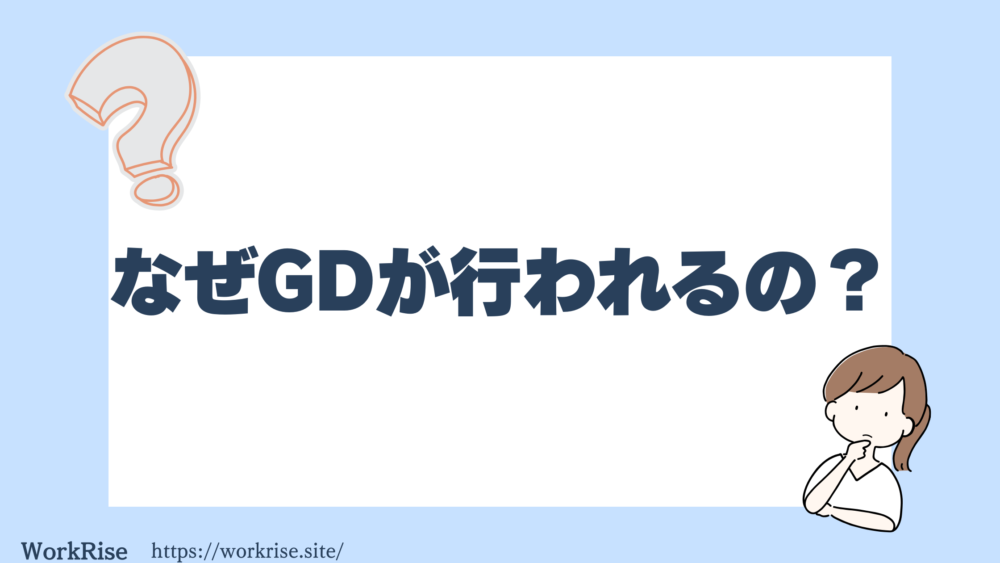
「なんでわざわざグループディスカッションなんてやるの?面接じゃダメなの?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?
企業がグループディスカッションを選考に取り入れるのには、面接だけでは見抜けない、あなたの「本当の力」を知りたがっているからなんです。
企業がグループディスカッションを実施する理由
企業がインターンシップの選考でグループディスカッションを取り入れるのには、明確な理由があるんです。
まず一番大きいのは、短時間で複数の学生を効率的に評価できるという点です。
面接だと一人ひとりに時間をかけなければいけませんが、グループディスカッションなら一度に4〜8人程度の学生を同時に見ることができます。
そして何より、実際の職場に近い環境での行動が観察できます。仕事って、チームで進めるものが多いです。
だからこそ、企業は「この学生は実際に働くときに、チームの中でどんな役割を果たしてくれるだろう?」ということを知りたがっています。
面接では見えない「協調性」や「思考力」を評価している
面接だと、どうしても用意した答えを話すことが多くなりますよね。
でも、グループディスカッションでは、その場で考えて、相手の話を聞いて、自分の意見を組み立てて…という、よりリアルな能力が求められるんです。
企業が特に注目しているのは、
- 他者の意見を聞いて、建設的に議論できるか
- 自分の考えを論理的に伝えられるか
- チーム全体のことを考えて行動できるか
- 限られた時間の中で、効果的に貢献できるか

こういった能力は面接だけでは測りにくいからこそ、多くの企業がグループディスカッションを選考に取り入れているよ!
インターンのグループディスカッション選考の流れと基本的な進め方
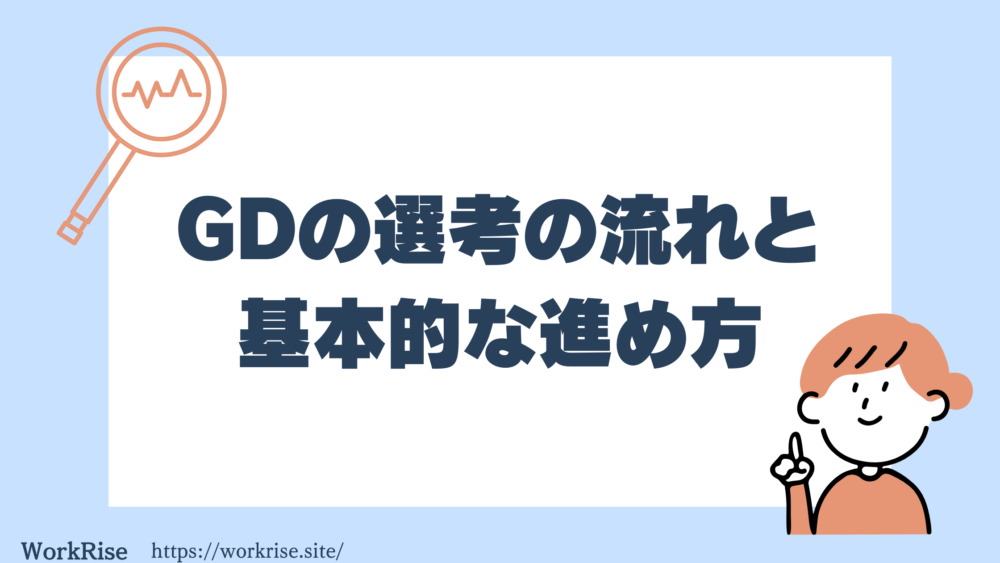
「グループディスカッションって、実際にはどんな流れで進むの?」
初めて参加する方にとって、全体の流れが分からないと不安ですよね。
でも大丈夫!基本的な進め方を知っておけば、当日も落ち着いて参加できますよ。
一般的な流れを順番に見ていきましょう!
役割や時間の配分を決める
グループディスカッションが始まったら、まず最初に「誰がどんな役割を担うか」「時間をどう使うか」を決めることが大切です。
よくある役割分担はこんな感じです。
- 司会・進行役:議論全体をリードし、時間管理をする
- 書記・記録係:意見をまとめて、最後の発表資料を作る
- タイムキーパー:時間を管理し、適切なタイミングで次の段階に進む
- アイデア出し:積極的に意見やアイデアを提供する
「私、司会とかできないし…」と不安に思う必要はありません。どの役割でも、しっかりと貢献できれば評価されます。

大事なのは、チーム全体のことを考えて、自分ができる形で参加すること!
語句の定義づけをする
意外と見落としがちなのが、この「語句の定義づけ」です。
例えば
「若者の働き方について議論してください」というテーマが出たとき、
「若者って何歳から何歳まで?」「働き方って、雇用形態のこと?それとも労働時間のこと?」といった基本的な定義を最初に決めておかないと、後でバラバラな議論になってしまいます。
この段階で大切なのは
- メンバー全員が共通の認識を持てるようにする
- 議論の範囲を明確にする
- 時間をかけすぎず、サクッと決める
「定義なんて細かいことより、早く本題に入りたい」と思うかもしれませんが、ここをしっかりやっておくことで、後の議論がグンとスムーズになります。
意見を出し合う
定義が決まったら、いよいよ本格的な意見交換の時間です。この段階では、とにかく多様な視点からアイデアを出すことが重要です。
効果的な意見出しのコツは、
- まずは量を重視して、たくさんのアイデアを出す
- 他の人の意見に「それいいですね!」と反応しながら、さらに発展させる
- 具体例や体験談を交えて話すと、説得力が増す
- 「なぜそう思うのか」という理由もセットで伝える
「私の意見なんて大したことない…」と遠慮する必要はありません。

異なる背景を持つメンバーだからこそ、多様な視点が生まれる!積極的に参加してみよう!
出し合った意見を整理する
たくさんの意見が出たら、今度はそれらを整理して、論理的な構造にまとめる必要があります。
整理の仕方としては、
- 似ている意見をグループ化する
- 重要度や優先順位をつける
- メリット・デメリットを整理する
- 因果関係や時系列を明確にする
この段階では、「全体を俯瞰して見る力」が特に評価されます。

「今出ている意見を整理すると、大きく3つのポイントに分けられそうですね」といった発言ができると、とても印象が良いよ!
結論を発表する
最後は、チームとしての結論を発表します。
ここでのポイントは、
- 議論の流れを簡潔に説明する
- なぜその結論に至ったかの理由を明確にする
- チーム全員が納得している結論であることを示す
- 時間内にキレイにまとめる

発表者になった場合は、
「私たちのチームでは…」という主語を使って、チーム全体の成果であることを強調するといいね!
グループディスカッションでよく出るテーマ例3選

「どんなテーマが出るか分からないから、準備のしようがない…」
そんな風に思っていませんか?
実は、グループディスカッションのテーマにはある程度のパターンがあります。
よく出るテーマの傾向を知っておけば、事前の準備もぐっとやりやすくなりますよ。
自由討論型のテーマ例
自由討論型は、幅広いテーマについて自由に意見交換するというタイプです。
よく出るテーマはこんな感じです。
- 「理想的な働き方とは何か」
- 「10年後の日本社会はどうなっているか」
- 「大学生活で最も大切なことは何か」
- 「コミュニケーション能力を高める方法」
自由討論型のコツは、抽象的なテーマを具体的な論点に落とし込むことです。

例えば「理想的な働き方」について話すなら、
「誰にとって理想的なのか」
「どんな価値観を重視するのか」
といった切り口から議論を深めていくといいね!
課題解決型のテーマ例
課題解決型は、具体的な問題に対して解決策を提案するというタイプです。
- 「大学生の読書離れを改善する方法を考えてください」
- 「地方の人口減少問題にどう対処するべきか」
- 「コロナ禍での学習効果を高める方法」
- 「SNSでの誹謗中傷をなくすには」
課題解決型のコツは、問題の原因分析から始めて、実現可能な解決策を提案するという流れに沿って進めることです。

「なぜその問題が起きているのか」をしっかり分析できれば、自然と効果的な解決策も見えてくるよ!
選択型・ディベート型のテーマ例
選択型・ディベート型は、複数の選択肢から一つを選んだり、賛成・反対に分かれて議論するというタイプです。
- 「リモートワークと出社勤務、どちらがより効果的か」
- 「大学の授業料は無料にするべきか」
- 「AIが発達した社会で、人間に求められる能力とは」
- 「終身雇用制度は維持するべきか、廃止するべきか」
選択型・ディベート型のコツは、両方の立場のメリット・デメリットを整理してから、チームとしての結論を出すことです。

一方的な主張ではなく、反対意見にも理解を示しながら議論を進められると、とても評価が高いよ!
グループディスカッションで見られているポイント
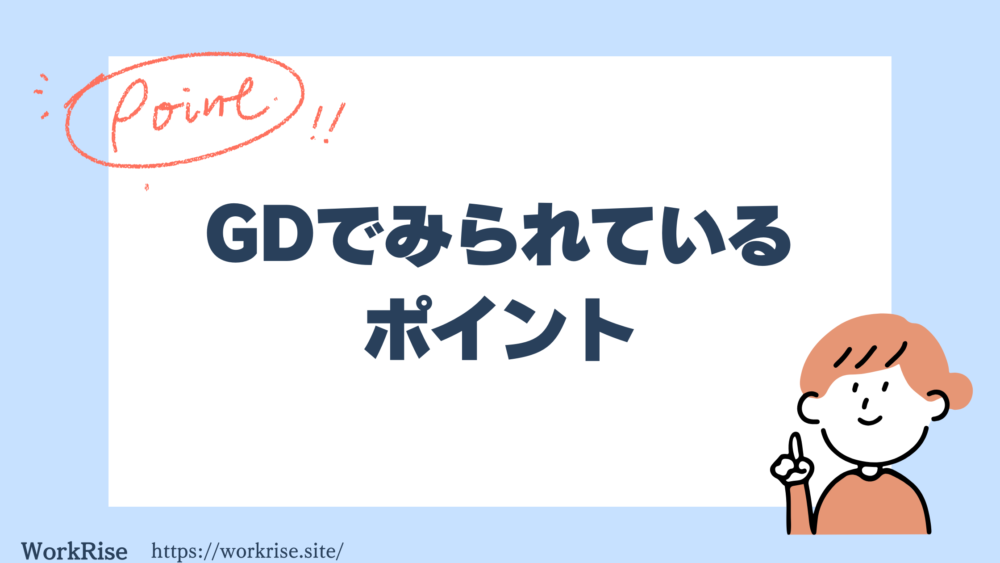
「企業の人は、一体何を見ているんだろう?」
これは多くの学生が気になるポイントですよね。
企業が注目している評価ポイントを理解しておくと、当日の行動も自然と変わってきます。
どのようなところを見られているか、しっかりと把握しておきましょう。
【関連記事はこちら!】
企業にとってのグループディスカッションのメリットは?選考通過のコツ3選
論理的思考力や構造化能力
企業が最も注目しているのは、あなたの論理的思考力です。
具体的には、
- 筋道立てて考えられるか
- 根拠と結論を明確に分けて話せるか
- 複雑な問題を整理して、分かりやすく説明できるか
- 因果関係や優先順位を考えて議論できるか
「論理的思考力なんて難しそう…」と思うかもしれませんが、実はそんなに特別なことではありません。

「なぜそう思うのか」
「具体的にはどういうことか」
「それによってどんな結果になるのか」といったことを意識して話すだけで、グンと論理的になるよ!
積極性と協調性のバランス
グループディスカッションでは、積極性と協調性の両方が求められます。
積極性というのは、
- 自分の意見をしっかりと発言する
- 議論をリードしようとする姿勢
- 新しいアイデアを提案する
協調性というのは、
- 他の人の意見をちゃんと聞く
- 異なる意見も尊重する
- チーム全体のことを考えて行動する
どちらか一方に偏ってしまうのはよくありません。
「自分の意見ばかり主張して、人の話を聞かない」のもダメですし、「人の意見に合わせてばかりで、自分の考えを言わない」のもよくないんです。

大切なのは、状況に応じてバランスを取ること!
傾聴力・周囲への配慮ができているか
意外と見落としがちなのが、この傾聴力と配慮です。
企業は以下のような行動を高く評価します。
- 発言していないメンバーに「○○さんはどう思いますか?」と振る
- 他の人の意見を要約して「つまり、こういうことですね」と確認する
- 時間を意識して「そろそろまとめに入りましょうか」と提案する
- 意見が対立したときに、建設的な方向に導く
こういった行動ができる人は、実際の職場でも「一緒に働きやすい人」として重宝されるんです。だからこそ、企業も注目しています。
グループディスカッションでやってはいけないこと
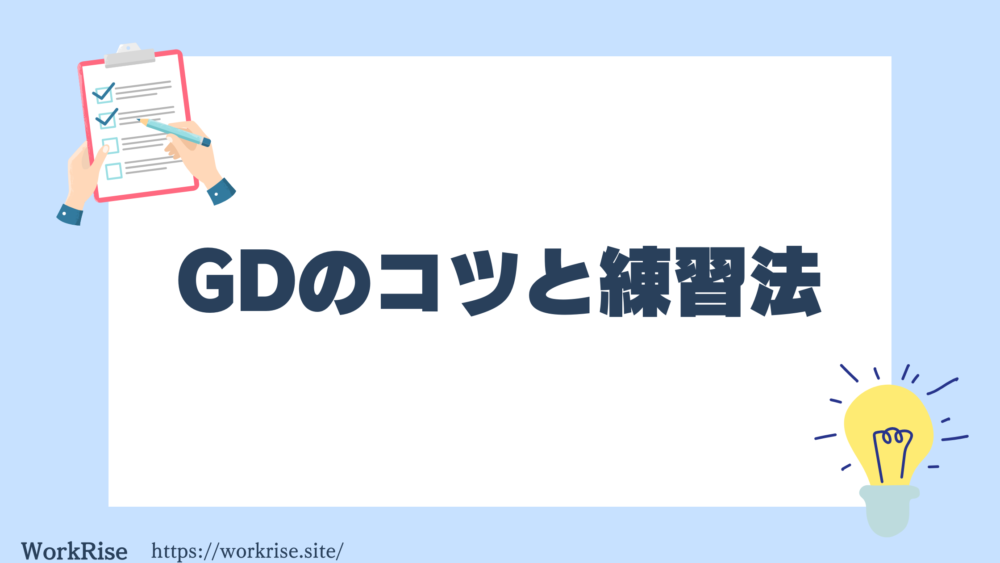
確かに注意点は多いのですが、実は「絶対にやってはいけない」ことってそんなに多くないんです。
これから紹介するNGパターンを避けるだけでも、評価は大きく変わります。
発言しない・参加しない
これは絶対にNGです。
「間違ったことを言ったら恥ずかしい」 「みんなの方が頭が良さそう」 「うまく話せる自信がない」
そんな風に思って黙ってしまう気持ちはとてもよく分かります。
しかし、企業側から見ると「この人は職場でもコミュニケーションを取らないのかな?」と思われてしまいます。
完璧な発言をする必要はありません。「○○さんの意見に賛成です」「具体例を挙げると…」といった簡単な発言からでも全然大丈夫です。
他者の意見を否定する・遮る
これもよくある失敗パターンです。
- 「それは違うと思います」
- 「でも、それって現実的じゃないですよね」
- 相手が話している最中に割り込む
こういった行動は、協調性がない人として評価を大きく下げてしまいます。
異なる意見があるときは、
- 「なるほど、○○という視点ですね。私は少し違う角度から考えていて…」
- 「○○さんの意見も分かります。加えて、こんな見方もあるかなと思うのですが…」
このように、相手の意見を一度受け止めてから、自分の考えを伝えるようにすると良いでしょう。
一人で話しすぎる/仕切りすぎる
積極性をアピールしたいあまり、一人で話しすぎるのも問題です。
- 長々と自分の体験談を話す
- 他の人に発言の機会を与えない
- 「私がまとめます」と勝手に仕切る
- 自分のペースで議論を進めようとする
グループディスカッションはチーム戦です。自分一人が目立てばいいわけではありません。
全員が活躍できるように気を配れる人が、最も高く評価されます。
雰囲気を壊すクラッシャー行動
最後に、これだけは絶対に避けてほしい「クラッシャー行動」があります。
- 他の参加者を見下すような発言
- 議論とは関係ない話題を持ち出す
- 感情的になって怒ったり、不機嫌になったり
- スマホをいじる、時計ばかり見る
- 明らかにやる気のない態度
こういった行動をしてしまうと、どんなに優秀でも一発でアウトです。
企業は「この人と一緒に働きたいか?」という視点で見ているからです。
初心者でもできる!グループディスカッションのコツと練習法
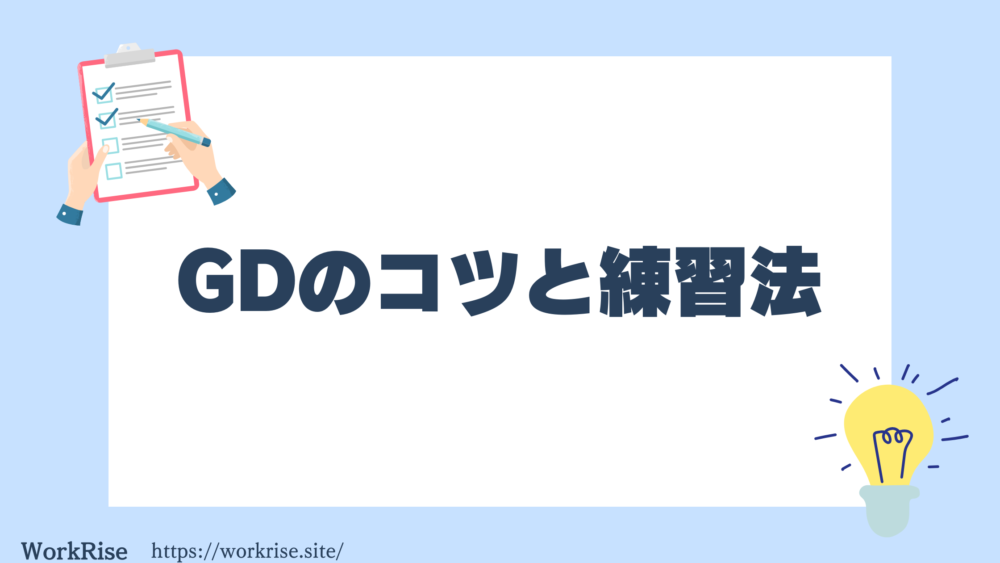
「理論は分かったけど、実際にはどうやって練習すればいいの?」
ここが一番気になるところですよね。グループディスカッションの上達には、適切な練習が欠かせません。
ここからは初心者の方でも無理なく始められる練習法を、段階別にご紹介します!
自己分析と業界研究が土台になる
「グループディスカッションの練習って、何から始めればいいの?」
実は、自己分析と業界研究が一番の基礎なんです。
なぜかというと、
- 自分の価値観や経験がはっきりしていると、説得力のある意見が言える
- 業界知識があると、現実的で具体的な提案ができる
- 自分の強みを理解していると、適切な役割を選べる
例えば、IT企業のインターンを受ける場合、「デジタル化が社会に与える影響」といったテーマが出る可能性が高いですよね。
そのときに、業界の動向や具体的な事例を知っていれば、深みのある議論ができるはずです。

まずは自分自身と志望業界について、しっかりと理解を深めることから始めてみよう!
【自己分析や業界研究についてはこちらの記事もチェック!】
・【質問例付き】自己分析のやり方を具体的に徹底解説!
・就活生必見!業界選びの重要性とその方法を徹底解説!
模擬GDやキャリアセンターを活用する
「実際の練習はどうすればいいの?」
一番効果的なのは、実際にグループディスカッションを体験することです。
活用できるリソースはこのようなものがあります。
- 大学のキャリアセンターの模擬GD
- 就活イベントでのGD練習会
- 友達同士での練習会
- 就活塾やスクールのGD対策講座
特に大学のキャリアセンターは無料で利用できることが多いので、積極的に活用しましょう。
キャリアアドバイザーからのフィードバックも受けられるので、自分では気づかない改善点も見つかります。

勇気を出して一歩踏み出してみよう!
一人でもできるグループディスカッション練習法を紹介
「周りに練習相手がいない」「まずは一人で基礎を固めたい」
そんな方におすすめの練習法を紹介します。
1. ニュースを見ながら意見をまとめる練習
毎日のニュースを見ながら、
・「この問題の原因は何だろう?」
・「どんな解決策があるだろう?」
と考える習慣をつけてみましょう。
スマホのメモ機能で、簡潔に意見をまとめる練習をするのも効果的です。
2. 鏡の前で話す練習
恥ずかしいかもしれませんが、鏡の前で実際に話してみることで、表情や話し方の癖が分かります。
・「結論から言うと…」
・「理由は3つあります」
といった構造化した話し方を意識してみてください。
3. タイマーを使った時間管理練習
グループディスカッションでは時間管理が重要です。
・「3分で問題の原因を考える」
・「5分で解決策をまとめる」
といったように、タイマーを使って短時間で考えをまとめる練習をしてみてください。
4. 様々なテーマで論点整理
・「大学生の学習意欲向上」
・「地域活性化」
・「働き方改革」
など、様々なテーマについて、論点を整理してみる練習も有効です。
「誰が」「何を」「なぜ」「どのように」という5W1Hで考える癖をつけると、論理的思考力が向上します。
【関連記事はこちら!】
一人でもできる!グループディスカッション練習方法・AIの活用法
グループディスカッションがうまくいかなかったときの対処法
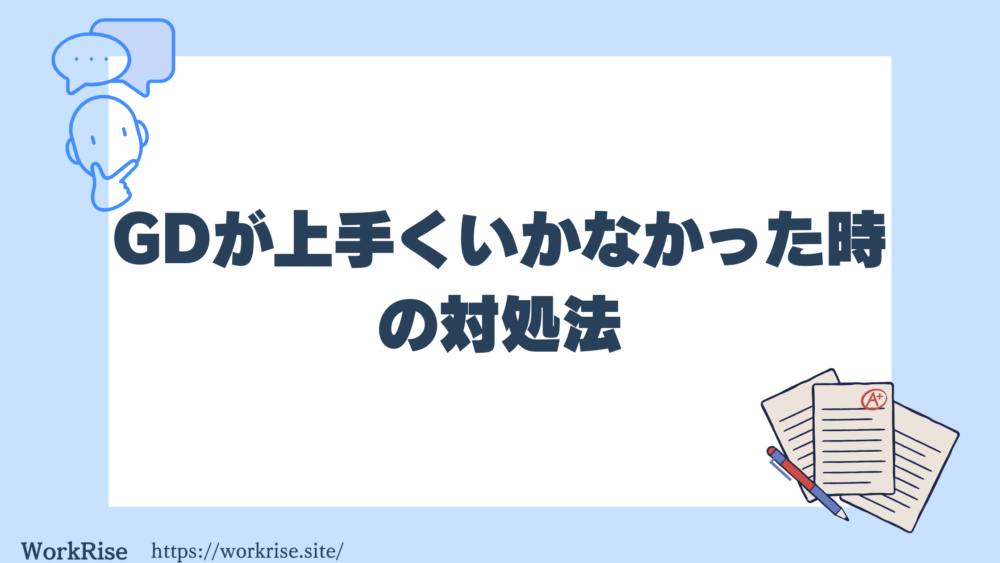
「今回のグループディスカッション、全然ダメだった…。」
そんな風に落ち込んでしまうことありますよね。
でも大丈夫です!失敗は成長のチャンス!
うまくいかなかった経験を、次回に活かす方法をお伝えします。
企業が重視しているポイントを再確認する
まずは、その企業が何を重視していたのかを改めて考えてみましょう。
- 業界特有の知識や視点が求められていたのか
- 特定のスキル(数字に強い、創造力など)が重要だったのか
- 企業文化に合う人柄を見られていたのか
- チームワークよりも個人の能力を重視していたのか
企業によって重視するポイントは結構違います。
IT企業なら論理的思考力、広告代理店なら創造力、金融機関なら慎重さと正確性…といった具合です。
次回に向けての振り返りと改善
失敗から学ぶためには、具体的な振り返りが欠かせません。
以下の項目をチェックしてみましょう。
発言について
- 発言回数は適切だったか?
- 論理的で分かりやすい話し方ができていたか?
- 相手に配慮した伝え方ができていたか?
傾聴について
- 他の人の話をちゃんと聞けていたか?
- 意見の要約や確認をしていたか?
- 発言していない人に配慮できていたか?
時間管理について
- 全体の時間を意識して行動できていたか?
- 適切なタイミングで次の段階に進めていたか?
チームワークについて
- 協調性を保ちながら積極性も示せていたか?
- 建設的な議論に貢献できていたか?

一つずつ振り返って、「次回はここを改善しよう」という具体的な目標を立ててみよう!
自分の意見が話せないときの対処法
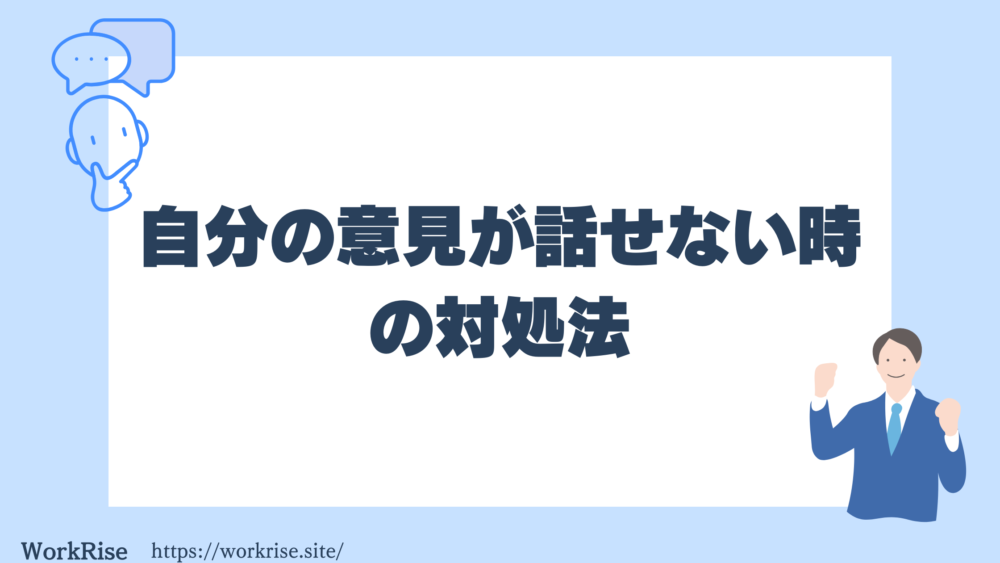
「みんなはスラスラ話しているのに、自分だけ何も発言できない…」
これ、本当によくある悩みなんです。しかし、意見が思い浮かばないのには必ず理由があります。
そして、それぞれに対応策もあります。
一緒に解決方法を見つけていきましょう!
事前にテーマの関連知識をインプットしておく
「グループディスカッションで自分だけ何も発言できない…。」

こんな悩みを抱えている方、実は多いんだ。でも安心して!対処法はちゃんとあるよ!
まず一番効果的なのは、事前の準備です。
よく出るテーマの関連知識を事前にインプットしておけば、当日も自信を持って発言できるようになります。
- ニュースアプリで社会問題をチェックする
- 志望業界の動向や課題を調べる
- 大学生活や就活に関する統計データを把握する
- 成功事例や失敗事例を集めておく
「そんなに覚えられない…」と思うかもしれませんが、完璧である必要はありません。
「確か、こんな事例があったな」
「この分野では○○が課題になってるよね」
といったような程度の知識があるだけでも、発言の材料になります。
他者の意見に共感や質問を加えて会話に入る
「いきなり自分の意見を言うのはハードルが高い…」
そんなときは、他の人の意見に反応するところから始めてみてください。
例えば、
- 「○○さんの『△△』という視点、とても面白いですね。具体的にはどのような場面を想定されていますか?」
- 「今の意見に賛成です。私も似たような経験があって…」
- 「なるほど、○○という課題があるんですね。それに加えて、△△という側面もあるのかなと思うのですが…」
こうした発言なら、プレッシャーも少ない上、自然に議論に参加できます。
そして徐々に慣れてきたら、自分から新しい論点を提起してみる…という段階的なアプローチがおすすめです。
話しやすいタイミングや役割を見つけて発言する
実は、グループディスカッションには発言しやすいタイミングがあります。
発言しやすいタイミング
- 議論が一段落したとき
- 意見をまとめる段階
- 具体例を求められているとき
- 時間管理の声かけが必要なとき
自分に合った役割を見つける:
- 記録係:書きながら「今の意見をまとめると…」と自然に発言できる
- 質問役:「○○についてもう少し詳しく教えてください」と議論を深められる
- 時間管理:「残り10分ですね」といった声かけで貢献できる
- 具体例提供:「例えば…」と事例を紹介することで議論に参加できる
大切なのは、無理して司会をやろうとしないことです。
自分が最も力を発揮できる役割で、しっかりと貢献することの方がよっぽど評価されます。
インターンのグループディスカッションでの正しい服装
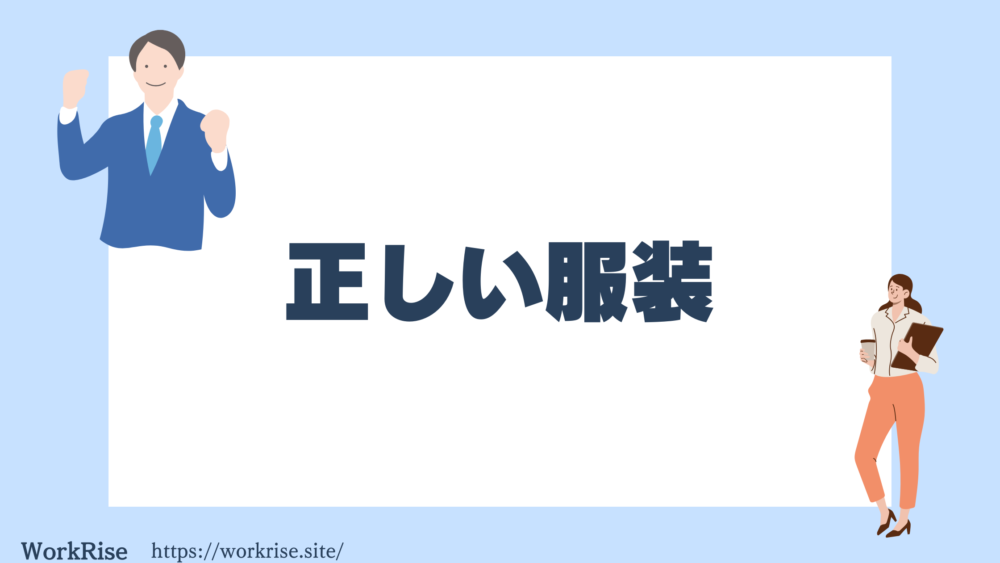
第一印象って本当に大切なので、服装について悩むことは多いですよね。
しかし、基本的なポイントを押さえておけば、服装で失敗することはありません。
スーツが基本!色や形は無難なものを選ぶ
「グループディスカッションって、どんな服装で行けばいいの?」
基本的にはスーツで行くのが安心です。企業から特に指定がない限り、スーツを選んでおけば間違いありません。
男性の場合
女性の場合
清潔感を最優先!髪型や靴もチェック
服装以上に大切なのが清潔感です。どんなに高級なスーツを着ていても、清潔感がなければ台無しになってしまいます。
チェックポイント
- 髪型:きちんと整えて、顔にかからないように
- 爪:短く切って、汚れがないように
- 靴:汚れを落として、できれば磨いておく
- シャツ:シワがないように、アイロンをかける
- 全体:毛玉や汚れ、ほつれがないかチェック
特に注意したいのが匂いです。
香水や整髪料の匂いが強すぎると、密室での議論に影響を与える可能性があります。「無臭」を心がけるのが一番です。
オンラインGDの場合の服装と映り方のポイント
最近はオンラインでのグループディスカッションも増えていますよね。
オンラインならではのポイントがあるので、ぜひチェックしてみてください!
服装について
- 上半身だけでも、きちんとしたシャツやジャケットを着用
- 画面に映る範囲は特に気をつける
- 色は画面映りを考えて、白や薄い色より濃い色の方が安定
環境について
- 背景はシンプルに(バーチャル背景でもOK)
- 照明は顔がはっきり見えるように
- カメラは目線の高さに設置
- 音声がクリアに聞こえるか事前チェック
「下はパジャマでも大丈夫でしょ」と思うかもしれませんが、もしかしたら恥ずかしい思いをするかもしれません。上下ともきちんとした服装にしておくことをおすすめします。
季節や企業文化に合わせた服装の工夫
夏の場合
- クールビズ指定があれば、ノーネクタイ・ノージャケットでもOK
- ただし、指定がなければスーツが安全
- 汗染みが目立たない色や素材を選ぶ
- 制汗スプレーなどで匂い対策も忘れずに
冬の場合
- コートは会場に入る前に脱いでおく
- 静電気でスーツにほこりが付着しないよう注意
- 室内の温度調整を考えて、脱ぎ着しやすい服装を心がける
企業文化による違い
- 金融業界:よりフォーマルな印象を心がける
- IT業界:比較的カジュアルでもOKな場合が多い
- アパレル業界:センスの良さも見られる可能性がある
- 公務員:最も保守的で無難な服装を選ぶ

迷ったときは、その企業の社員の方々がどんな服装をしているかを、企業のウェブサイトやSNSで確認してみると良いかも!
就活エージェントを使ったグループディスカッション対策の活用と注意点
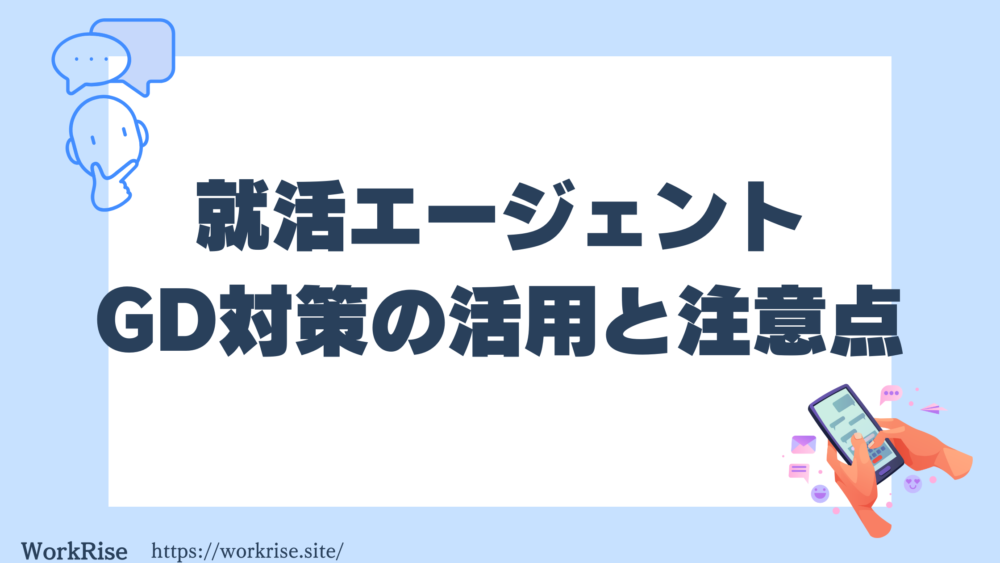
「一人での対策に限界を感じる…プロの力を借りたい」
そんなときに心強い味方になってくれるのが、就活エージェントです。
メリットと注意点を両方お伝えするので、参考にしてみてください!
就活エージェントのグループディスカッション対策のサポート内容
「一人での対策に限界を感じる…」「プロからアドバイスをもらいたい」
そんなときに頼りになるのが、就活エージェントのグループディスカッション対策です。
主なサポート内容
- 模擬グループディスカッションの実施
- 個別フィードバックとアドバイス
- よく出るテーマの傾向分析
- 業界別の対策ポイントの指導
- 他の就活生との練習機会の提供
- 本番直前の最終チェック
特に有効なのが、客観的なフィードバックです。自分では気づかない癖や改善点を、第三者の目で指摘してもらえるのはとても価値があります。
「話すスピードが速すぎる」「相手の話を最後まで聞けていない」「論点がずれやすい」といった具体的な指摘をもらえれば、効率的に改善できます。
相性が悪い担当者にあたったときの対処法
「担当者との相性がイマイチ…」
これ、実はよくあることなんです。
就活エージェントも人間ですから、どうしても相性の良し悪しはありますよね。
まず試してほしい対処法
- 具体的な要望を伝えてみる 「もう少し具体的なアドバイスが欲しいです」 「○○業界に特化したアドバイスをお願いします」
- 期待値を明確にする 「今日は△△について重点的に見てもらえますか?」 「次回までに○○を改善したいので、そこを中心にお願いします」
- 率直にコミュニケーションを取る 「私の理解が追いついていないので、もう少しゆっくり説明していただけますか?」
それでも改善されない場合は、担当者の変更を依頼するのも一つの手です。遠慮する必要はありません。
担当者を断っても就活に影響はある?
「担当者を変えてもらったり、エージェントを断ったりしたら、就活に悪影響があるのでは?」
こんな心配をする方もいますが、全く問題ありません。
就活エージェントと企業の選考は基本的に独立していますし、エージェントの担当者も「学生にとって最適なサポートを提供すること」が目的なんです。
相性が合わないのに無理して続けるより、変更してもらった方がお互いのためになります。
むしろ、自分に合わないサポートを我慢して続ける方がリスクです。貴重な準備期間を無駄にしてしまうかもしれません。
「申し訳ないのですが、もう少し違うアプローチでサポートしていただける担当者にお願いできればと思います」
こんな感じで、丁寧にお願いすれば大丈夫ですよ。
就活エージェントを断った後の連絡頻度や対応は?
「エージェントからの連絡がしつこくて…」
これも時々ある話ですね。エージェントとしては学生をサポートしたい気持ちが強いのですが、受ける側にとっては負担になることもあります。
連絡を減らしたいとき
- はっきりと意思表示をする 「現在は自分で就活を進めているので、連絡はしばらく不要です」 「必要になったらこちらから連絡します」
- 連絡手段を限定する 「メールでの連絡のみでお願いします」 「週1回程度の連絡にしていただけますか?」
- 完全に利用を停止する場合 「就活の方向性が変わったので、サービスの利用を停止させてください」
ほとんどのエージェントは、こうした要望に適切に対応してくれます。
もし対応が改善されない場合は、その会社のお客様相談窓口に連絡してみてください。
まとめ
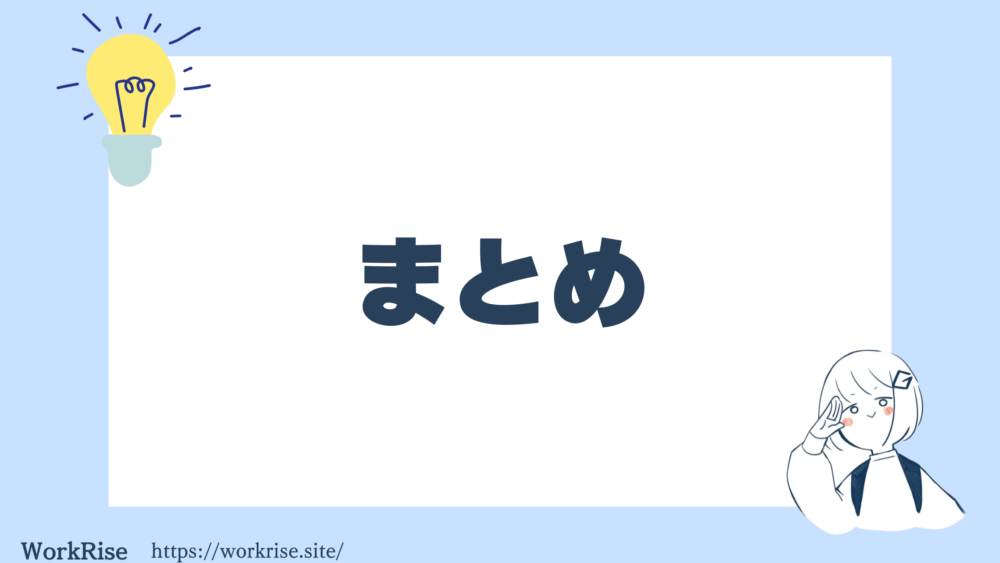
いかがだったでしょうか?
インターンのグループディスカッション選考は、確かに緊張するものですが、しっかりと準備をすれば必ず突破できます。
最後に、今回お伝えした重要なポイントをもう一度整理しておきます。
基本の心構え
実践のコツ
練習方法
「グループディスカッションなんて無理かも…」と思っていた方も、この記事を読んで少しは自信が湧いてきたのではないでしょうか?
大切なのは、今できることから一歩ずつ始めることです。
まずはニュースを見ながら自分の意見をまとめてみる、友達と時事問題について話し合ってみる…そんな小さなことから始めてみてください。



