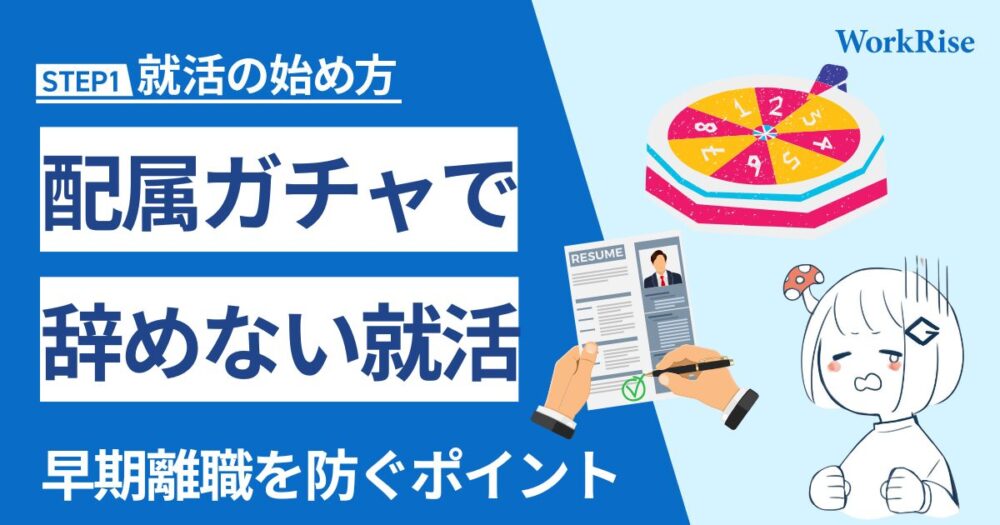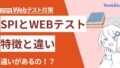こんにちは!27卒ライターのFujiです。
今回は、配属ガチャで辞めることを防ぐために、就活の時に気を付けるべきポイントを解説していきます。
皆さんは「配属ガチャ」という言葉を聞いたことがありますか?
配属ガチャとは、総合職で採用された場合、どの支社・部署・職種に配属されるかがわからないことを指した言葉です。
実はこの配属ガチャで、入社一年目で辞めてしまう人は多くいます。
せっかく苦労して掴んだ内定、手放したくないですよね?
そこで、この記事では、配属ガチャでハズレを引かない・辞めることがないようにするために、就活の時点から気を付けるべきポイントを解説していきます!
- 配属ガチャとは何かとその具体例
- 配属ガチャが起こる原因とタイミング
- 配属ガチャを回避するための就活での注意点
- 配属ガチャでハズレても辞めずに済む考え方
- ジョブ型採用を活用した配属ガチャの完全回避法
配属ガチャとは
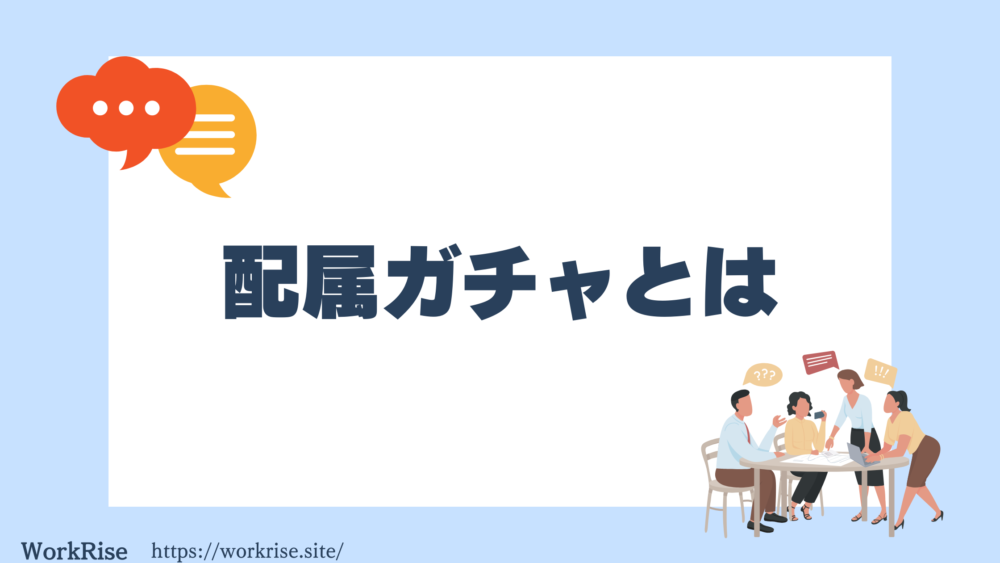
まず、配属ガチャについて詳しく説明していきます!
「配属ガチャ」とは、新入社員が自分の希望とは関係なく、会社側の都合で配属先(勤務地や部署)を決められてしまう状況を指す言葉です。
ガチャという言葉が使われているように、まさに運任せで自分の配属先が決まってしまうという意味が込められています。
総合職として一括採用されることが多い日本の企業では、この配属ガチャが起こりやすいのが現実です。
学生の間では「配属ガチャでSSRを引きたい」「配属ガチャでハズレを引いた」といった表現で使われることが多く、就活生にとって大きな不安要素の一つとなっています。
特に大手企業ほど全国に支社や事業所があるため、配属ガチャのリスクが高くなる傾向があります。
自分のキャリアプランやライフプランに大きく影響する問題なので、就活の段階からしっかりと対策を考えておくことが大切です。
配属ガチャの例
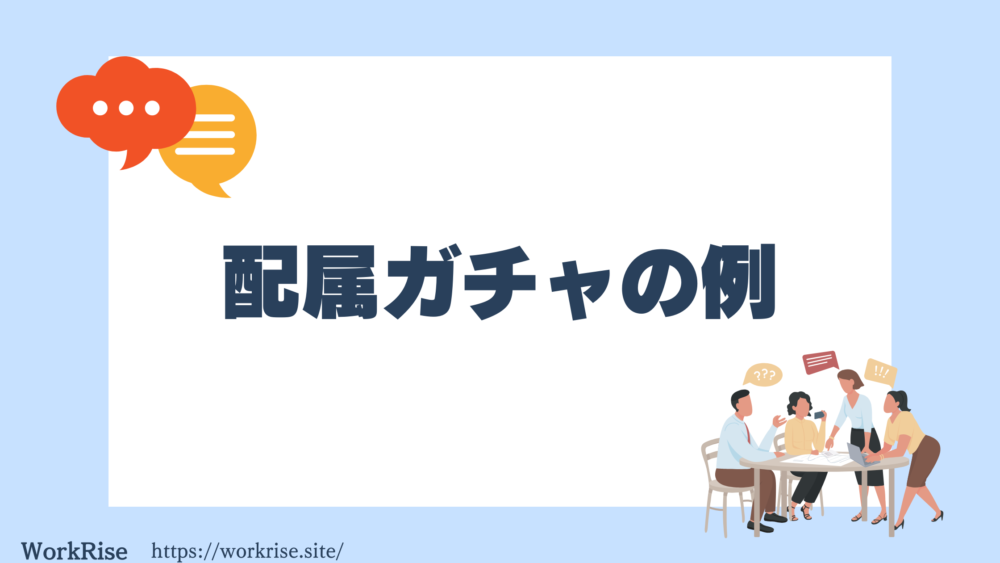
では、実際に配属ガチャの具体的な例を見ていきましょう!
実際にどんなことが起こるのかを知ることで、対策の必要性がより明確になります。
希望の職種につけない
まず一つ目は、希望していた職種とは全く違う部署に配属されてしまうケースです。
例えば、「企画職として新しい商品を開発したい!」という夢を持って入社したのに、営業部に配属されて毎日外回り…なんてこともあり得ます。
もちろん、営業の仕事が悪いわけではありませんが、自分のやりたいこととのギャップに悩んでしまう人は少なくありません。
会社としては、まず現場を知ってほしいという親心なのかもしれませんが、モチベーションの維持が難しくなり、早期離職の原因になってしまうこともあるんです。
自分の興味や得意なことを活かせない職種に配属されるのは、本当につらいですよね。
希望の勤務地にならない
そして二つ目が、今回のテーマでもある、希望の勤務地にならないケースです。
「地元で働きたい」「都会で刺激的な毎日を送りたい」など、勤務地に対する希望は人それぞれですよね。
それなのに、「地元での勤務を希望していたのに、全く知らない地方の支社に配属された」「東京本社勤務だと思っていたら、地方の工場勤務になった」という話は、本当によく聞きます。
特に全国に支社や工場がある大企業では、全国転勤が前提となっていることも多く、勤務地の希望が全く通らないことも珍しくありません。
プライベートの予定も立てにくくなりますし、慣れない土地での生活は精神的にも大きな負担になりますよね。
配属先が分かるのはいつ?
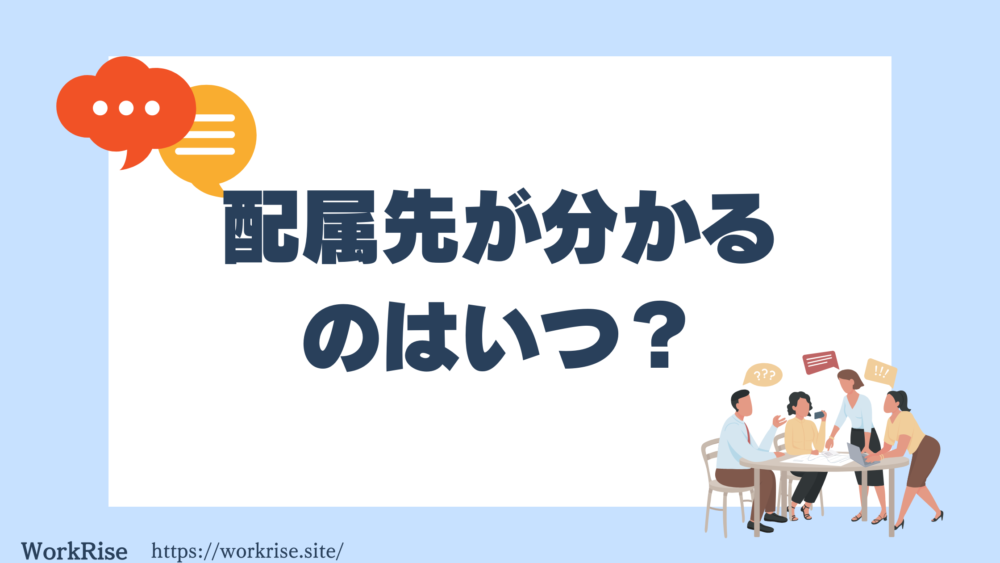
では、配属先は一体いつ分かるのかについて詳しく解説していきます。
タイミングを知ることで、心の準備もできるようになります。
配属先が分かるのは直前になることも
一番多いパターンは、入社後の新入社員研修の終盤に発表されるケースです。
多くの企業では、4月に入社した後、数週間から数ヶ月の新入社員研修があります。
その研修期間中に適性を見たり、会社の状況を確認したりして、最終的な配属先を決定することが多いです。
しかし、場合によっては配属の1週間前や数日前にいきなり言い渡されることもあります。
特に勤務地が大きく変わる場合は引っ越しの準備なども大変で、「もう少し早く教えてほしかった」という声をよく聞きます。
アパートの契約や引っ越し業者の手配、住民票の移転など、やらなければならないことがたくさんあるのに時間がないという状況になってしまいます。
また、家族や友人への報告、送別会の準備なども慌ただしくなってしまい、精神的にも負担が大きくなります。
【体験談】配属先が遠くなった例
以下、私の先輩たちの体験談を紹介します。
ある先輩は、研修期間中は全国各地の支社を巡って研修を受けていました。
配属先が決まったのは、研修が終わる1ヶ月前という直前のタイミングでした。
地元は関西で、希望も関西か関東で出していたのですが、実際の配属先は静岡の支社でした。
「関西にいたかったけど、せめて東京なら納得できた」と話していましたが、静岡は全く考えていなかった場所だったそうです。
また、別の先輩の場合、内勤を希望していたにも関わらず、営業に配属されました。
元々人と話すのが得意ではなく、データ分析や企画系の仕事を希望していました。
しかし配属されたのは法人営業で、毎日様々な企業を訪問する仕事でした。
慣れない営業活動と希望とのギャップによってストレスが蓄積し、そのまま心身を壊してしまって離職することになりました。
現在は転職して、希望していたデータ分析の仕事に就いているそうです。
配属ガチャはなぜ起きる?
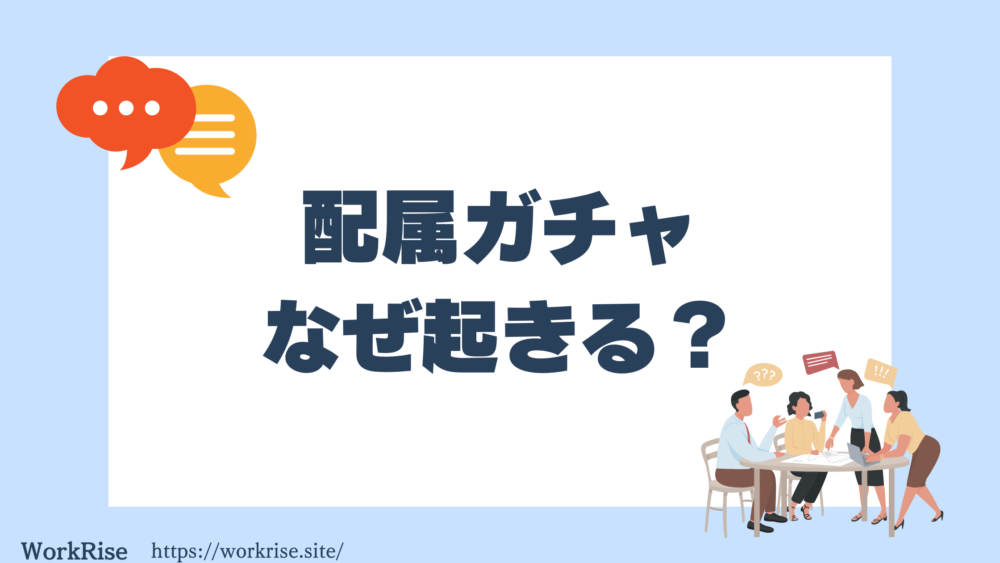
そもそも、なぜ企業は配属ガチャのような、学生にとって不安の大きい制度を続けているのでしょうか?
それには、日本の企業が長年続けてきた「新卒一括採用」という独特の採用システムが大きく関係しています。
内々定から入社までの期間が長い
配属ガチャが起こる一因として、内々定が出てから実際に入社するまでの期間が非常に長いことが挙げられます。
多くの学生は大学3年生の後半から就職活動を始め、4年生の春から夏にかけて内々定をもらいますよね。
しかし、実際に入社するのは翌年の4月。
この約1年という長い期間の間に、会社の事業計画や組織体制は変化する可能性があります。
そのため、企業側としては、内々定の段階で配属先を確約することが難しく、入社直前の会社の状況を見て、人員配置を最終決定したいという事情があるのです。
新卒一括採用のデメリット
日本の多くの企業が採用している「新卒一括採用」は、職種を限定せずにポテンシャルを重視して採用し、入社後に適性を見て配属先を決めるという考え方が基本です。
これは、会社側にとっては、事業計画の変更などに合わせて柔軟に人員を配置できるというメリットがあります。
しかし、学生側から見れば、自分の専門性や希望が考慮されず、会社の都合でキャリアが決まってしまうという大きなデメリットになります。
まさに、この新卒一括採用というシステム自体が、配属ガチャを生み出す温床となっているのです。
会社にとっては合理的でも、私たちにとってはたまったもんじゃないですよね!
配属ガチャでハズレないために気を付けるポイント
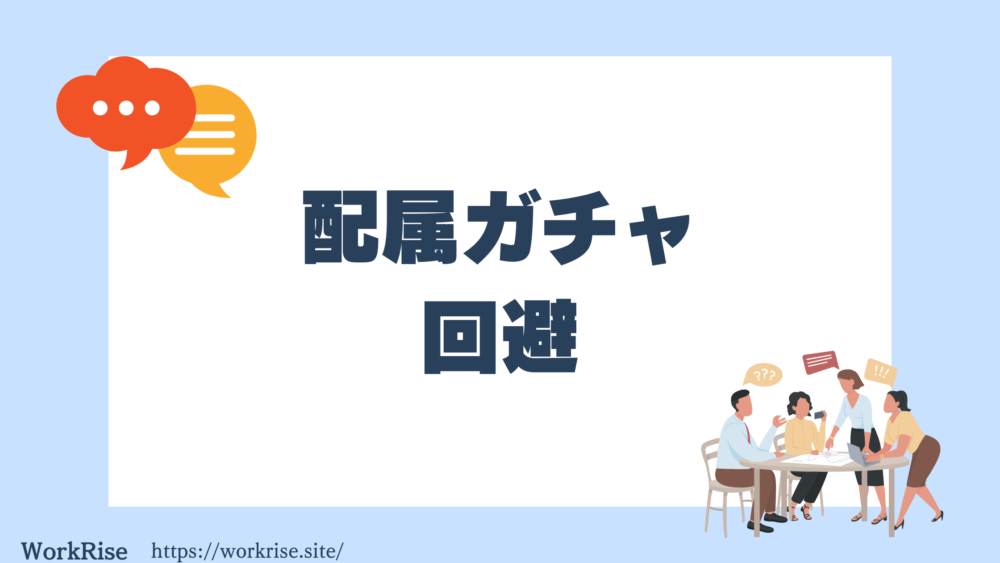
いよいよ、配属ガチャでハズレを引かないための具体的な対策を紹介していきます!
就活の段階からこれらのポイントを意識することで、配属ガチャのリスクを大幅に減らすことができます。
面接で希望をしっかり伝えておく
面接の段階で自分の希望する職種や勤務地をはっきりと、そして具体的に伝えておくことが重要です。
単に「営業をやりたいです」というのではなく、「なぜ営業をやりたいのか」「営業の中でもどんな分野に興味があるのか」まで詳しく説明しましょう。
「なぜその勤務地を希望するのか」という理由も、自分のキャリアプランやライフプランと結びつけて具体的に説明することが大切です。
例えば、「地元での勤務を希望します。理由は、高齢の両親の近くにいて介護が必要になった時にサポートしたいからです」といった具合に、相手が納得できる理由を示すことが重要です。
また、「絶対に譲れないポイント」と「ある程度柔軟に対応できるポイント」を明確に分けて伝えることも効果的です。
すべてを絶対条件にしてしまうと企業側も困ってしまいますが、優先順位を付けて伝えることで、企業側も配慮しやすくなります。
座談会やOB訪問で配属の仕組みを聞いておく
実際にその会社で働く先輩たちに、「勤務地の希望はどのくらい通りますか?」「若手のうちは地方勤務が多いですか?」など、具体的な質問をぶつけてみましょう。
人事担当者からは聞けないリアルな情報を得ることができます。
私は、実際に、ある企業の座談会で「勤務地の希望は出せますか?」と質問したことがあります。
その企業は関東、関西、九州に拠点があったのですが、社員の方からは「大半の社員は関東勤務で、少なくとも入社5年程度は関東での勤務になります。希望する関西に行けるのはベテランの管理職になってからですよ」というリアルな答えが返ってきました。
この情報があったおかげで、「関西での勤務を希望していたけど、この会社では難しそうだ」と判断して、別の企業を選ぶことができました。
OB訪問では、さらに踏み込んで「実際にどんな配属パターンがあるのか」「希望が通らなかった人はどう感じているのか」なども聞いてみると良いでしょう。
求人票をよく確認しておく
求人票には配属ガチャのリスクを判断するための重要な情報が記載されています。
総合職の場合はまず配属ガチャのリスクが高まると考えて良いでしょう。
逆に「営業職」「技術職」など職種が限定されている求人の方が、配属ガチャのリスクは低くなります。
勤務地に関しては、「全国の各事業所」や「全国転勤あり」といった記載がある場合は、配属ガチャのリスクが高いと判断できます。
また、「転勤の頻度」「転勤時の条件」「単身赴任の可能性」なども確認しておくと良いでしょう。
求人票だけでは分からない部分も多いので、説明会や面接で積極的に質問することも大切です。
「転勤は何年に一度くらいありますか?」「新卒の場合、最初の配属先はどのように決まりますか?」といった質問をすることで、より具体的な情報を得ることができます。
ジョブ型採用の求人を利用する
最も確実な配属ガチャ回避法は「ジョブ型採用」の求人に応募することです。
ジョブ型採用とは、あらかじめ職務内容や勤務地を明確に限定して募集する採用方法です。
近年、日本でもジョブ型採用を導入する企業が増えてきており、配属ガチャを避けたい学生には非常に有効な選択肢となっています。
ジョブ型採用では入社前に具体的な業務内容が分かるため、「こんなはずじゃなかった」というミスマッチが起こりにくくなります。
ただし、ジョブ型採用では専門性やスキルが重視される傾向があるので、自分の強みや経験をしっかりとアピールできるよう準備しておくことが重要です。
配属ガチャでハズレても辞める必要はない
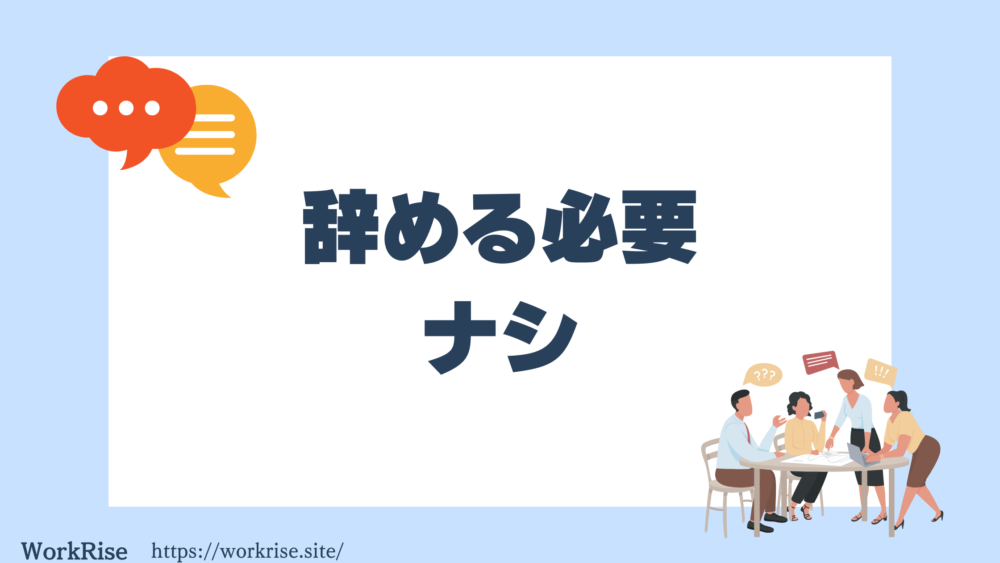
もし配属ガチャでハズレを引いてしまっても、すぐに辞める必要はありません!
考え方を変えることで、その状況を成長のチャンスに変えることができます。
自分の成長機会と捉える
自分の専門性が低い仕事になった場合、自分の得意を増やすチャンスと捉えてみましょう。
最初は「こんな仕事、自分には向いていない」と思っても、数年間働くうちに、「自分にできない仕事」ではないと見えてくる場合も少なくありません。
例えば、技術職を希望していた人が営業に配属された場合、技術的な知識を活かした営業として活躍できる可能性があります。
お客様の技術的な課題を理解できる営業担当者は非常に重宝されるため、思わぬキャリアの可能性が開けることもあります。
また、異なる職種を経験することで、将来的に管理職になった時により広い視野を持つことができます。
営業と技術の両方を理解している管理職は、部門間の調整や意思決定において非常に価値の高い存在になれます。
短期的には希望と違う配属でも、長期的なキャリア形成を考えると大きなプラスになる可能性があることを忘れないでください。
必ずしも「ハズレ」ではないケースもある
花形ではない地方支社や工場に配属されてしまった、と落ち込む人は多くいます。
しかし、忙しくない場所の方が丁寧に仕事を教えてもらえる可能性は高いのも事実です。
本社の忙しい部署では、先輩社員も余裕がなくて十分な指導を受けられないことがありますが、地方の支社では時間をかけてしっかりと育成してもらえることが多いです。
また、人間関係が良いなど、職種や勤務地だけでは見えないその職場の良さもあります。
地方の職場では地域密着型の仕事ができ、お客様との距離も近く、やりがいを感じやすいという面もあります。
さらに、地方勤務では生活費が安く、都市部よりも豊かな生活を送れるというメリットもあります。
通勤時間が短い、自然が豊か、地域のコミュニティとのつながりが深いなど、都市部では得られない良さがたくさんあります。
意外と「ハズレ」ではないケースも少なくないので、まずはその環境で頑張ってみることをオススメします。
転職や異動の希望を出す方法も
どうしても現在の配属先が合わないと感じる場合は、人事部に異動の希望を出すこともできます。
多くの企業では年に1〜2回、異動希望を申告できる制度があります。
ただし、異動が実現するまでには時間がかかることが多いので、長期的な視点で考えることが大切です。
また、新卒一年目の場合、まだ第二新卒として転職できる可能性もあります。
第二新卒は企業からの需要も高く、新卒時よりも有利な条件で転職できることもあります。
ただし、転職を考える前に、現在の職場で得られる経験やスキルがないか、もう一度検討してみることをオススメします。
早期離職は履歴書上でマイナスに見られることもあるので、慎重に判断することが重要です。
転職を検討する場合は、転職理由を明確にし、次の職場では同じ問題が起こらないよう、しっかりとした企業研究を行うことが大切です。
ジョブ型採用の求人を利用して配属ガチャを回避しよう

さて、ここまで読んで、「配属ガチャを回避したい!」と感じた方も多いのではないでしょうか。
ここでは、配属ガチャ回避の切り札とも言えるジョブ型採用について、さらに詳しく解説していきます。
ジョブ型採用とは
改めて説明すると、「ジョブ型採用」とは、企業が特定の職務(ジョブ)を遂行できるスキルや経験を持った人材を採用する手法です。
採用の段階で、担当する仕事内容、役職、勤務地、そして給与などが明確に定められています。
つまり、入社後に「こんなはずじゃなかった…」というミスマッチが起こる可能性が非常に低いのが特徴です。
自分の専門性を活かしたい、やりたい仕事が明確に決まっている、そして何より希望の勤務地で働きたい、という人にとっては、まさに理想的な採用方法と言えますね!
ジョブ型採用のメリット
ジョブ型採用には、私たち就活生にとってたくさんのメリットがあります。
最大のメリットは、やはり配属ガチャの心配が一切ないこと!
勤務地も職務内容も、応募した求人票に書かれている通りなので、安心して入社日を迎えることができます。
また、自分の専門分野や得意なスキルを直接仕事に活かせるため、高いモチベーションを維持しながらキャリアをスタートさせることができます。
自分のキャリアプランを主体的に描きたい、と考えているあなたにぴったりの働き方です!
ジョブ型採用サービス:仕事塾
ジョブ型採用サービスとして一番おススメなのが「仕事塾」です。
仕事塾の強みは、何と言っても配属ガチャを避けることができる点です。
実は、新卒の早期離職で最も多い理由が『仕事が自分に合わなかった』というもの。
この原因の一つとして考えられるのが、就職した後に自分がどの部署に配属されるか分からない「配属ガチャ」です。
一般的な求人である、総合職求人ではこの「配属ガチャ」を避けることは難しいです。
しかし、仕事塾では、初期配属を確約したポジション確約求人のみ掲載されているため、配属ガチャの心配がありません。
企業は求職者のスキルや経歴を確認することができるため、自分の持つ力を最大限発揮できる職とマッチングできる確率も上がります。
また、初期配属先が分かっているため、勤務地がどこになるか分からない・希望の職種に就くことができるか分からないという不安を抱えることがないのも魅力的です。
仕事塾登録はコチラ!
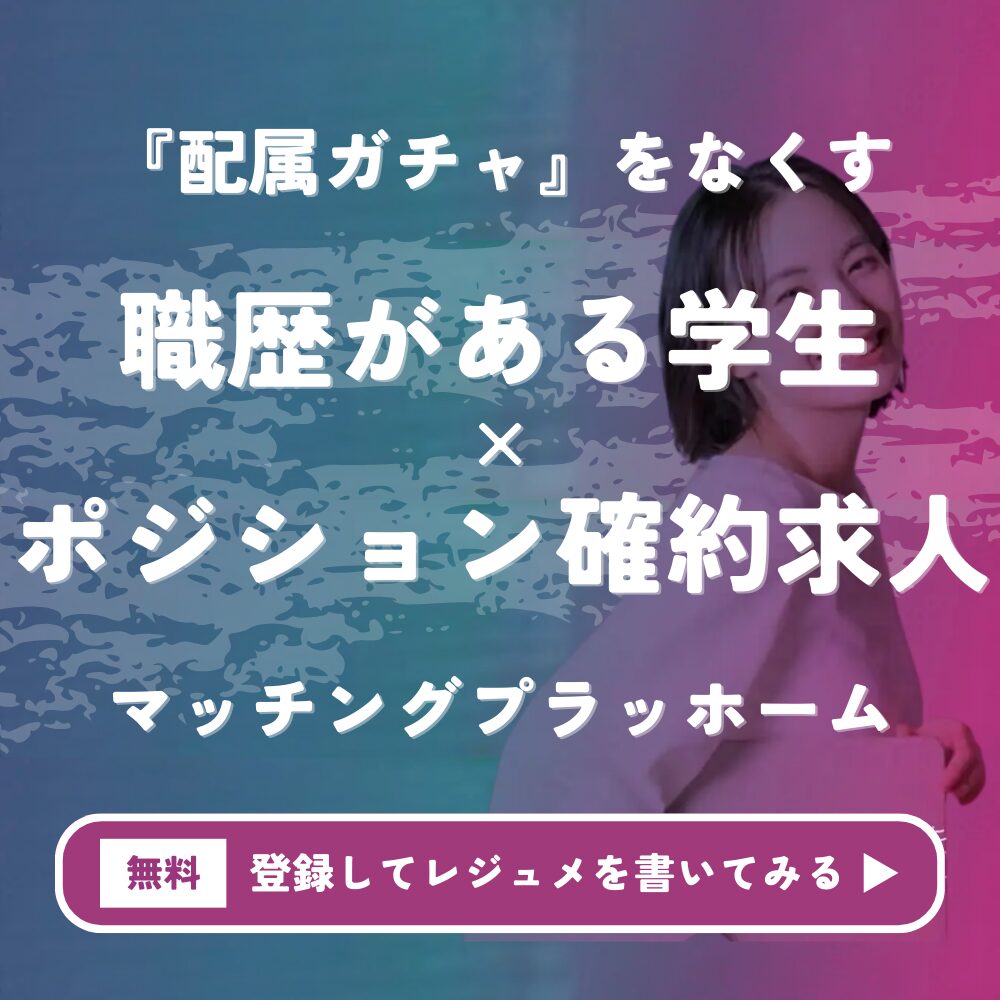
まとめ
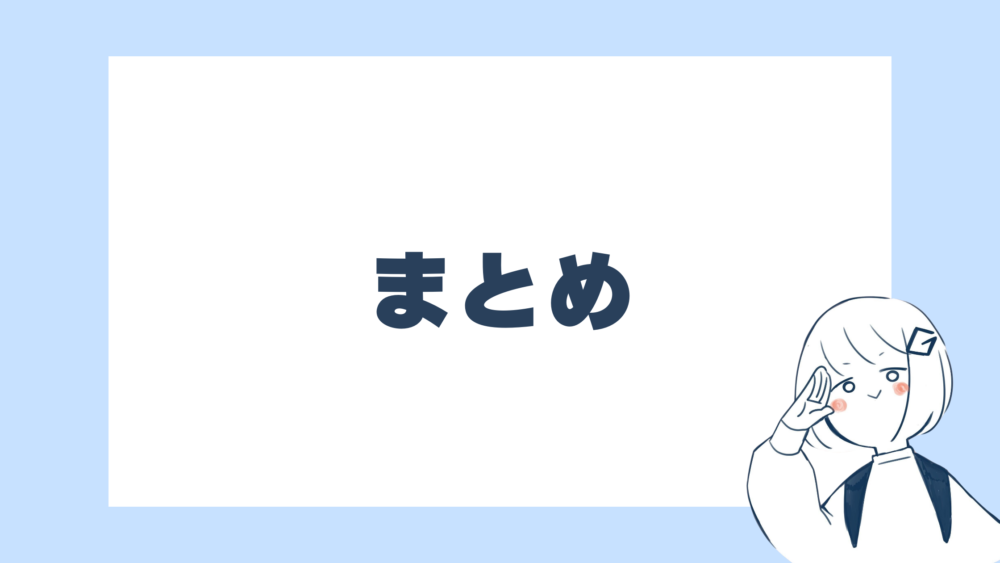
さて、今回は配属ガチャについて詳しく解説してきました!
配属ガチャは、総合職採用において自分の希望とは関係なく配属先が決まってしまう現象で、多くの新卒社員が直面する問題です。
希望の職種につけなかったり、予想していない勤務地に配属されたりすることで、早期離職につながってしまうケースも少なくありません。
配属ガチャが起こる主な原因は、内々定から入社までの期間が長いことと、日本特有の新卒一括採用制度にあります。
しかし、就活の段階からしっかりと対策を取ることで、配属ガチャのリスクを大幅に減らすことができます。
面接で希望をしっかり伝える、OB訪問で配属の仕組みを確認する、求人票を詳しくチェックするなど、できることはたくさんあります。
最も確実な方法は、ジョブ型採用の求人を活用することです。
ジョブ型採用なら職務内容と勤務地が事前に確定するため、配属ガチャの心配がありません。
もし配属ガチャでハズレを引いてしまっても、すぐに辞める必要はありません。
その状況を成長のチャンスと捉えたり、異動や転職という選択肢もあります。
大切なのは、配属ガチャのリスクを理解した上で、自分に合った就活戦略を立てることです。
皆さんが理想のキャリアをスタートできるよう、心から応援しています!