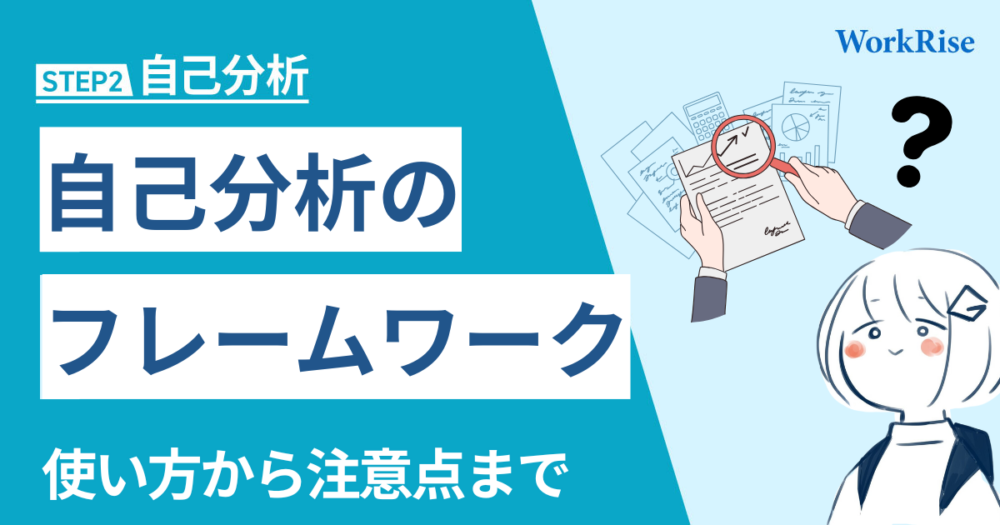こんにちは!27卒のnamiです。
就活をしていると…

自己分析ってどうすればいいんだろう…?
という悩みを抱えることってありますよね。
実は、フレームワークを利用することで自己分析がやりやすくなるんです!
今回はそんな自己分析のフレームワークについて、
- フレームワークを利用した自己分析のやり方
- フレームワークで自己分析をする際の注意点
- 自己分析を就活に活かす方法
を解説していきます!
最後まで読んで、自分に合った企業を見つけるための一歩を踏み出しましょう!
【そもそも】自己分析をする理由って?

自己分析って何のためやる必要があるの?
そんな疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか?
ここでは主な3つの理由を解説していきます。

企業の意図を知ることでより適切な回答にも繋がるよ!
自分の適性や強みを知るため
自己分析は、自分の経験や行動パターンを体系的に分析することで、他の人には真似できない自分だけの強みを発見できる重要な取り組みです。
自己分析によって発見した適性や強みは、面接での自己アピールだけでなく、入社後のキャリア形成においても重要な判断材料となります。特に、自分の強みと企業が求める人材要件が合致している場合、その企業でより大きな成果を出せる可能性が高まります。
今後のキャリアを明確にするため
就職活動において、自己分析は将来のキャリアパスを具体的にイメージするための不可欠なプロセスになります。
キャリアの方向性を決める際には、過去の経験から得られた価値観や、仕事に対する考え方が重要な判断基準となります。
選考の通過率を上げるため
面接官を説得力のある回答で魅了するには、自己分析で得られた具体的なエピソードと、その経験から導き出された自己理解が必要不可欠です。
採用面接では「学生時代に力を入れたこと」や「自己PR」などの質問が頻出します。これらの質問に対し、自己分析で整理した具体的なエピソードを交えながら、自分の強みや価値観を論理的に説明できれば、面接官に強い印象を残すことができます。
【おすすめ10選】自己分析のフレームワーク
就職活動において自己分析は最も重要な準備の1つです。自己分析の仕方は多様で、様々な分析フレームワークを組み合わせることで、自分自身の特徴や価値観をより深く理解することができます!
ここでは、特に 効果的な10個のフレームワーク を紹介します。
①自分史
幼少期から現在までの経験を時系列で整理する自分史は、自己分析の基礎となるフレームワークです。進学や部活動の選択、アルバイト経験など、人生の重要な出来事を年表形式で書き出すことで、自分の価値観や興味の変遷を体系的に把握することができます。
具体的な作成方法として、まずは、A4用紙を横向きに使用し、中央に時間軸となる線を引きます。その上に学校生活での出来事を、下に学校以外での経験を記入していきます。たとえば、高校時代のバスケットボール部でのキャプテン経験や、大学でのボランティア活動など、自分にとって印象的な出来事を書き出します。
自分史の作成は、単なる経歴の整理ではなく、自分の行動パターンや価値観を発見するための重要なステップとなります。

自分の人生の中で作り上げてきた価値観を再確認することができるんだね!
②人生曲線(モチベーショングラフ)
人生曲線は、過去の経験に対する感情の変化を視覚的に表現するフレームワークです。自分史で整理した出来事に対して、そのときの充実度や満足度を曲線で表現することで、自分がどのような経験に強い感情を抱いたのかを明確にすることができます。
横軸に時間、縦軸にモチベーションや充実度をとり、-5から+5などのスケールで感情の起伏を記録します。たとえば、部活動での大会優勝は+5、進路選択で悩んだ時期は-3というように、各経験に数値をつけながら曲線を描いていきます。
人生曲線を作ることで、自分がどのような状況で高いモチベーションを保てるのか、逆にどのような環境でモチベーションが低下するのかを客観的に理解することができます。また、困難な状況をどのように乗り越えてきたのかも明確になり、自己PRや面接での具体的なエピソードとしても活用することができます。
③SWOT分析
SWOT分析は、自分の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を4つの象限に分けて分析するフレームワークです。このフレームワークを用いることで、自分の経験や変化など内面と社会や環境などの外的な要因の両面から自己理解を深めることができます。
強みの分析では、「他者から評価された特徴」や「成果を上げられた場面」など、具体的な経験に基づいて書き出します。弱みについては、「改善すべき点」として捉え、それを克服するための方策も同時に考えます。機会と脅威は、就職市場の動向や業界の変化など、外部環境の分析を通じて見出します。
このフレームワークは、強みと機会を組み合わせて新たな可能性を見出したり、弱みと脅威から回避すべきリスクを特定したりできるという特徴があります。自己PRのポイントや、志望する業界・職種の選定に活用することができるでしょう。
④自己分析表(自己分析シート)
自己分析表は、複数の観点から自分自身を体系的に分析するためのフレームワークです。職務経験、学業成績、資格、性格特性など、就職活動で必要となる要素を網羅的に整理することができます。
具体的な項目として、「学歴・学業成績」「課外活動での実績」「アルバイト経験」「保有資格」「技術スキル」「性格特性」「価値観」などがあります。各項目について、具体的なエピソードや数値・データを記入することで、自己アピールの材料を整理することができます。
このフレームワークの利点は、面接での質問に対して、具体的なエピソードを即座に引き出せるようになるという点です。また、項目ごとに自己評価を行うことで、より成長が必要な分野も見えてくるでしょう。

ESを書く時や面接の時にも自己分析で振り返った細かいエピソードが役立ちそう!
⑤Will, Can, Mustの3つの輪
Will(やりたいこと)、Can(できること)、Must(すべきこと)の3つの要素を分析するフレームワークは、キャリアの方向性を見出すために効果的です。3つの輪が重なる部分を見つけることで、理想的なキャリアパスを設計することができます。
Willの分析では、「興味のある仕事」「情熱を感じる分野」などを書き出します。Canでは、「学んできたスキル」「経験を通じて獲得した能力」を整理します。Mustについては、「社会的な要請」「家族への責任」など、外部からの期待や条件などを書き出します。
3つの要素が重なる部分を見つけることで、自分にとって最適な職種や業界が明確になります。このフレームワークは、単なる理想追求ではなく、現実的な条件も考慮した実現可能なキャリアプランを考える際に役立ちます。
⑥マインドマップ
マインドマップは、中心に置いたキーワードから連想を広げていく発想法を活用したフレームワークです。自己分析においては、「自分」を中心に置き、関連する要素を広げて書き出すことで、様々な分野・経験から多角的に自己理解を深めることができます。
作成方法として、A4用紙の中央に「自分」と書き、そこから「学業」「課外活動」「趣味」「将来の目標」など枝状に要素を広げていきます。各要素からさらに具体的な項目を派生させ、連想を広げていきます。たとえば、「課外活動」から「サークル」「ボランティア」「インターン」などを派生させます。
このフレームワークは、思考の流れを視覚的に表現でき、関連する要素を自由に書き出すことで、自分自身の興味や価値観の傾向を発見することができます。また、就職活動における自己PRのポイントを見つけることにも役立ちます。
⑦自己分析1000問
自己分析1000問は、多数の質問に答えることで、自分自身の特徴や価値観を掘り下げていくフレームワークです。幅広い質問に回答することで、普段は意識していない自分の特徴や考え方のパターンを発見することができます。
質問の例として、「最も打ち込んだことは何か」「困難を乗り越えた経験は何か」「10年後どうなっていたいか」「仕事で大切にしたい価値観は何か」などが挙げられます。これらの質問に対して、具体的なエピソードや理由を交えながら回答を記述していきます。
多角的な質問を通じて、自分の特徴や価値観を網羅的に理解することができ、回答の過程で見つかった重要なエピソードは、面接での具体例として活用することもできます。
⑧ジョハリの窓
ジョハリの窓は、自己認識と他の人からの評価を4つの領域で分析するフレームワークです。「開放の窓」「盲点の窓」「秘密の窓」「未知の窓」の4つの領域から、自己理解を深めることができます。
「開放の窓」は自分も他人も知っている特徴、「盲点の窓」は自分は気づいていないが他人は知っている特徴、「秘密の窓」は自分は知っているが他人は知らない特徴、「未知の窓」は自分も他人も知らない特徴を表します。周囲の人からのフィードバックを得ながら、各領域の理解を深めていきます。
このフレームワークを通じて、自己認識と他者評価のギャップを把握することができます。

他人から自分を評価してもらうことで、
自分の強みや改善点を客観的に理解することができるね!
⑨ベン図を用いた分析
ベン図を用いた分析は、複数の要素の関係性を視覚的に表現するフレームワークです。例えば、「自分の興味」「市場のニーズ」「自分の能力」などの要素を円で表し、その重なり合う部分を分析することで、キャリアの方向性を見出すことができます。
具体的な作成方法として、3つの円を描き、各円に「得意なこと」「やりたいこと」「社会のニーズ」などの要素を割り当てます。それぞれの円の中に具体的な項目を書き出し、重なり合う部分に注目して分析を進めます。
フレームワークの特徴は、複数の要素の関係性を一目で把握でき、重なり合う部分から自分にとって最適な職種や業界を分析する事が出来ます。
⑩自己分析ノート
日々の気づきや成長を継続的に記録する自己分析ノートを作成することも効果的です。定期的な振り返りを通じて、自己理解を深め、キャリアプランを具体化することができます。
ノートの構成として、「今日の出来事」「学んだこと」「感じたこと」「今後の課題」などのセクションを設けます。これらの項目に沿って、日々の経験や気づきを記録していきます。特に印象的な出来事については、具体的なエピソードとして詳しく記述します。
自己分析ノートを通して、時間の経過とともに自分の変化や成長を可視化することができます。記録を積み重ねることで、自己PRや面接での具体例として活用できる材料が蓄積されていきます。

自己分析って難しく聞こえるけど、特別な活動だけじゃなくて、普段の経験・学びからも自分を分析することができるんだね!自己分析ノートだったら日記のように気軽に自己分析できそう!
その他に企業との面接や専門家との面談も自己分析に活用することもできます!
その他①企業の選考(面接/GD)
企業の選考プロセスそのものが、効果的な自己分析の機会となります。面接やグループディスカッションを通じて、自分の強みや改善点を具体的に把握することができます。
面接での質問に対する回答を準備する過程で、自分の経験や価値観を深く掘り下げることができます。また、グループディスカッションでは、他者との関わりの中で自分の特徴や行動パターンを観察することができます。
これらの選考プロセスで得られたフィードバックは、自己分析をさらに深めるための重要な材料となります。面接官からのコメントや、グループディスカッションでの他者の反応を、自己理解の機会として活用することが重要です。
その他②キャリアアドバイザーとの面談
キャリアアドバイザーとの面談は、プロフェッショナルな視点から自己分析を深める機会です。客観的なフィードバックを得ることで、自己認識の偏りを修正し、より実践的なキャリアプランを立てることができます。
アドバイザーとの面談では、自分の経験や志望動機について深く掘り下げていきます。また、業界の動向や求められる人材像についての詳しい情報も得ることができます。これらの対話を通じて、自己分析の方向性を確認することができます!
より詳しい相談や個別のアドバイスが必要な場合は、LINEでのキャリア相談も実施しています。経験豊富なアドバイザーが、あなたの自己分析とキャリアプランの策定をサポートします。
【フレームワークを利用】自己分析のやり方7STEP
STEP① 自分を客観的に判断する材料を自己分析ツールなどを用いて用意する
自己分析を効果的に進めるためには、まず自身を客観的に判断する材料を用意することが大切です。主観的な視点だけでは、自分の本当の強みや適性を正しく理解できないことがあるため、自己分析ツールを活用し、多角的な視点を取り入れることが重要です。

ここでは、先ほど紹介した人生曲線やジョハリの窓などを使うと良さそう!
STEP② 自分史を作成して過去の自分の出来事を洗い出す
自己分析を深めるためには、まず自分のこれまでの経験を整理することが重要です。その方法の一つとして、「自分史」を作成することが挙げられます。自分史を作ることで、過去の出来事を時系列で振り返り、自分の成長や価値観の変化を把握できます。
自己分析の基盤となる作業なので、時間をかけて丁寧に取り組むことが大切です。
STEP③ 人生曲線(モチベーショングラフ)を作成して過去の動機や感情を思い出す
自己分析を深めるためには、過去の出来事に対する自分の感情やモチベーションの変化を振り返ることが重要です。そのために有効な方法が、「モチベーショングラフ」の作成です。モチベーショングラフを活用すると、どのような状況でやる気が高まり、逆にどのような場面で意欲が低下したのかを可視化できます。こうした分析をもとに、自分に合った仕事やキャリアの方向性を考えることができるため、モチベーショングラフの作成は自己分析において大切なプロセスの1つです。
- 高校時代の部活動で大会優勝を経験したときにモチベーションが高まった
- 大学受験で失敗したときに大きく下がった
といった具体的なエピソードを振り返ることがポイントです!
STEP④ 過去の出来事を深掘りして経験や結果を思い出す
自己分析をより具体的に進めるためには、過去の出来事を表面的に捉えるのではなく、深掘りして経験や結果を振り返ることが重要です。単に「成功した」「失敗した」と結論づけるのではなく、なぜその結果になったのか、どのようなプロセスを経たのかを明確にすることが求められます。
例えば、受験や部活動での挫折経験についても、「どのような要因で失敗したのか」「その経験から何を学んだのか」「次に活かしたことは何か」と振り返ることで、成長の過程が見えてきます。
これによって、自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)をより説得力のある形で伝えられるようになります。
STEP⑤ 過去の出来事に対して自分がとった行動を洗い出す
経験を深掘りしたあとは、それぞれの出来事に対して自分が具体的にどのような行動を取ったのかを整理することが大切です。同じ経験をしても、人によって行動パターンは異なります。その行動の特性を理解することで、自分の強みや課題をより明確にできます。
また、結果が成功に終わった場合だけでなく、うまくいかなかった場合についても、自分がどのように行動したのかを振り返ることが重要です。困難に直面した際の対応を分析することで、自分の弱みを知るだけでなく、成長のヒントを得ることができます。

失敗した経験や困難を乗り越えた経験から学んだことも自己分析では重要なんだね!
STEP⑥ 過去の出来事の共通点を見つけ出す
これまでの出来事を深掘りし、行動を整理したら、それらの共通点を見つける作業に進みます。共通点を見つけることで、自分の価値観や得意なこと、モチベーションがどこから来ているのかが明確になります。
例えば、「努力を続けることで成果が出る場面でモチベーションが上がる」「人と協力して何かを成し遂げるときに達成感を感じる」など、複数の経験を通じて一貫した傾向を発見することができるでしょう。
この共通点を見つけることで、自分に適した職種や企業の社風を考える際の指針となります。より自分に合ったキャリア選択をするための重要なステップです。
STEP⑦ 共通点や自分の強み/弱みから企業や業界選びの軸を選定する
過去の経験から見えてきた共通点や、自分の強み・弱みをもとに、企業や業界選びの軸を決めます。自分の価値観や適性に合った環境を選ぶことで、働く上での充実感や成果を出しやすくなります。
例えば、「マルチタスクが苦手」という特性がある場合、複数の業務を同時にこなす必要がある職種よりも、一つの業務に集中できる環境を選ぶ方が向いている可能性があります。

単に「有名だから」「待遇が良いから」といった理由ではなく、自分に合った企業を選ぶことが、長期的なキャリア形成において重要なポイントなんだね!
>>就活の軸についてもっと知りたい方はこちら!
フレームワークで自己分析をする際の注意点8選
自己分析を効果的に進めるためには、フレームワークを正しく活用することが重要です。ここでは、自己分析を行う際に注意すべきポイントを8つご紹介します。
① 自己分析で分かった内容は言語化して保存する
自己分析を行って得た気づきや結論は、必ず言語化して記録しておきましょう。頭の中で考えただけでは、時間が経つと忘れてしまったり、情報が曖昧になったりすることがあります。ノートやExcel、スマートフォンのメモアプリなどを活用することもおすすめです。
② 短所や弱みなどネガティブな部分も考える
自己分析を行う際は、自分の強みだけでなく、短所や苦手なことも正直に振り返ることが大切です。自分の弱みを理解することで、どのように克服するかを考えたり、弱みを補える環境を選んだりすることができます。
例えば、「計画を立てるのが苦手」という弱みがある場合、細かいスケジュール管理が求められる職種よりも、柔軟に動ける環境の方が向いているかもしれません。また、短所をどのように改善しようとしているのかを考えておくと、面接での自己PRにもつなげやすくなります。
③ 主観以外の客観情報を重視する
自己分析は主観的なものになりがちですが、客観的な視点を取り入れることで、より正確な自己理解ができます。友人や家族、先輩など身近な人に自分の強みや弱みを聞いてみたり、自己分析ツールや適性診断を活用してみたりすることも有効です。
④ 経験だけでなく「想い」や「感情」も考える
自己分析をする際は、出来事の事実関係だけでなく、「そのとき自分がどう感じたのか」「何を大切にしたのか」といった感情の部分も深掘りしましょう。
例えば、「チームでプロジェクトを進めた経験」を振り返るとき、「チームワークを通じてどんな気持ちになったのか」「どんな瞬間にやりがいを感じたのか」を考えることで、自分の価値観やモチベーションが発揮される場面・状況が明確になります。
⑤ 結果だけではなく過程やきっかけも思い出す
自己分析では、「成功した」「失敗した」といった結果だけでなく、その過程やきっかけにも目を向けることが大切です。リーダー経験がある場合、「なぜリーダーになろうと思ったのか」など流れを整理すると、より具体的な自己PRにつながります。
⑥ 一度作成して終わりにしない
自己分析は一度やれば終わりというものではありません。就職活動が進むにつれて、新しい気づきや視点が増えていくため、定期的に見直すことが重要です。
例えば、面接を受けた後に「自分の伝え方がうまくいかなかった」「企業の評価ポイントが予想と違った」といった経験をした場合、自己分析を見直して修正を重ねることで、より具体的で精度の高いアピールができるようになります。
自己分析を定期的に振り返り、必要に応じてアップデートすることで、就職活動をよりスムーズに進めることができます。
⑦ 企業が求める人物像を意識しすぎない
企業の求める人物像を参考にすることは大切ですが、それを意識しすぎるあまり、自分を偽るような自己分析にならないよう注意が必要です。
企業が求める人物像に無理に合わせようとすると、本来の自分とズレが生じ、入社後にミスマッチが起こる可能性があります。自己分析の目的は、自分に合った企業を見つけることなので、企業に合わせるのではなく、まずは自分自身の価値観や適性を正しく理解することが大切です。
⑧ 業界・企業研究も同時におこなう
自己分析だけでなく、業界・企業研究を並行して行うことで、自分に合った企業をより具体的に見つけることができます。
自己分析を進めると、「自分はどんな環境で働きたいのか」「どんな仕事にやりがいを感じるのか」といった軸が明確になります。その軸をもとに、業界・企業研究を行うことで、より納得感のあるキャリア選択が可能になります。
また、業界や企業の特性を理解したうえで自己分析を行うと、「この企業では自分の強みが活かせる」「この職種は自分の価値観に合っている」といった発見が生まれ、志望動機をより明確にすることができます。
業界分析のやり方を知りたい方はこちら>>
【重要!】自己分析の就活での活かし方
自己分析はやってみたけれど、

就活の時にどうやって自己分析を活かしたらいいんだろう…
と悩んでしまいますよね。
でも大丈夫です!
ここでは、自己分析の就活での活かし方を詳しく解説していきます!
最後まで読んで、是非参考にして見てください!
自己分析から就活の軸を見出し企業を選ぶ方法
自己分析は、就活の軸を定めるために有効な方法です。自己分析を通じて自分の価値観や強み、将来のキャリアの方向性を明確にし、就活の軸を定めます。そして、それに基づいて企業選びを行います。
企業選びにおいて大切なのは、自分の強みややりたいことに合った企業文化や業務内容を持つ企業を選ぶことです。自己分析から見えてくる自分の価値観や仕事に求めるものを反映させることで、より自分にマッチした企業選びができます。
自己分析シートから選考対策をする方法

自分の強みや過去の経験を振り返り、それを企業が求める人材像にどのように活かせるかを考えることで、選考における説得力を高めることができます!
具体的には、①志望動機、②ガクチカ、③自己PRの3つの項目で活かす方法をそれぞれ解説していきます!
自己分析を基にした選考対策は、自己理解を深めつつ、企業とのマッチングをしっかり行うため、とても重要なステップです。
①志望動機に説得力を持たせる
志望動機に説得力を持たせるためには、自己分析から得た自分の価値観や強みを企業の求める人物像に合わせて表現することが重要です。例えば、自分が大切にしている価値観や経験を踏まえて、その企業でどのように自分の強みを活かせるかを具体的に述べると、より説得力が増します。自己分析を行い、自分がその企業で何を成し遂げたいのかを明確にすることで、志望動機に説得力を持たせることができます。
②ガクチカをより深く話す
ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)をより深く話すためには、自己分析でその経験から得たスキルや成長を具体的に振り返ることが大切です。ガクチカを話す際、単に活動内容を伝えるのではなく、その経験からどのようなスキルを得て、それがどのように企業で役立つのかを説明できるように練習することが必要です。その際に、自己分析を通じて自分の強みを理解しておけば、その強みをガクチカに絡めて話すことで、より深い印象を与えることができます。
③自己PRに厚みを持たせる
自己分析を元に自分の強みや特技、価値観を整理し、それらを具体的なエピソードを交えて表現することで、自己PRに厚みを持たせることができます。自己PRは自分の特長をアピールする場であり、自己分析を行って自分の強みや過去の成功体験を明確にすることで、アピールポイントが強化されます。
例えば、困難な状況をどのように乗り越えたか、その過程で学んだことを活かしていける点を強調することで、面接官に強い印象を与えることができます。
自己分析におすすめの本7選!
自己分析を深めるためには、書籍を活用するのも有効な方法です。ここでは、自己理解を深めたり、就職活動に役立てたりするのにおすすめの本を7冊紹介します。
メモの魔力 The Magic of Memos (NewsPicks Book)
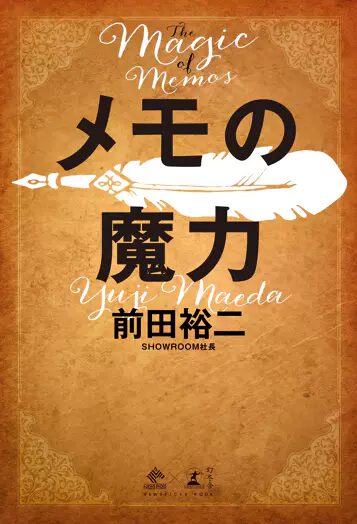
引用:メモの魔力 The Magic of Memos (NewsPicks Book) 前田裕二 幻冬舎
「メモの取り方」を通じて、自己分析の力を養うことができる一冊です。著者の前田裕二氏が提唱する「メモを使って思考を深める方法」は、自己分析だけでなく、日常の気づきを大切にする習慣作りにも役立ちます。特に、書籍の中にある「自己分析1000問」を活用すると、自分の価値観や考え方が明確になります。
おすすめポイント
✔ メモを活用した自己分析法が学べる
✔ 「自己分析1000問」で自分を深く掘り下げられる
✔ 仕事や人間関係にも応用できる
ハーバードの自分を知る技術 悩めるエリートたちの人生戦略ロードマップ
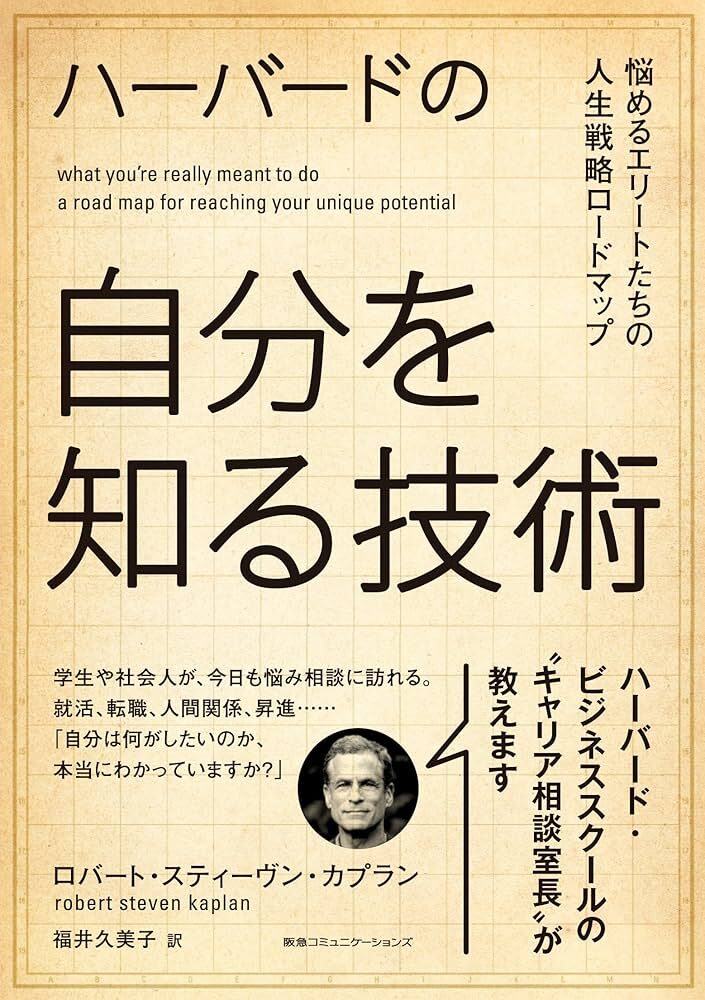
引用:ハーバードの自分を知る技術 ロバート・スティーブン・カプラン CCCメディアハウス
ハーバード・ビジネススクールで学んだ自己分析の方法をもとに、「自分の価値観」や「人生で大切にしたいこと」を明確にする方法を解説しています。特に、キャリアや人生の選択に迷っている人におすすめです。
おすすめポイント
✔ 世界最高峰の自己分析メソッドが学べる
✔ 「価値観マップ」を使って、自分の大切にしたい軸を明確にできる
✔ 人生戦略を立てるための実践的なワークが充実
受かる! 自己分析シート
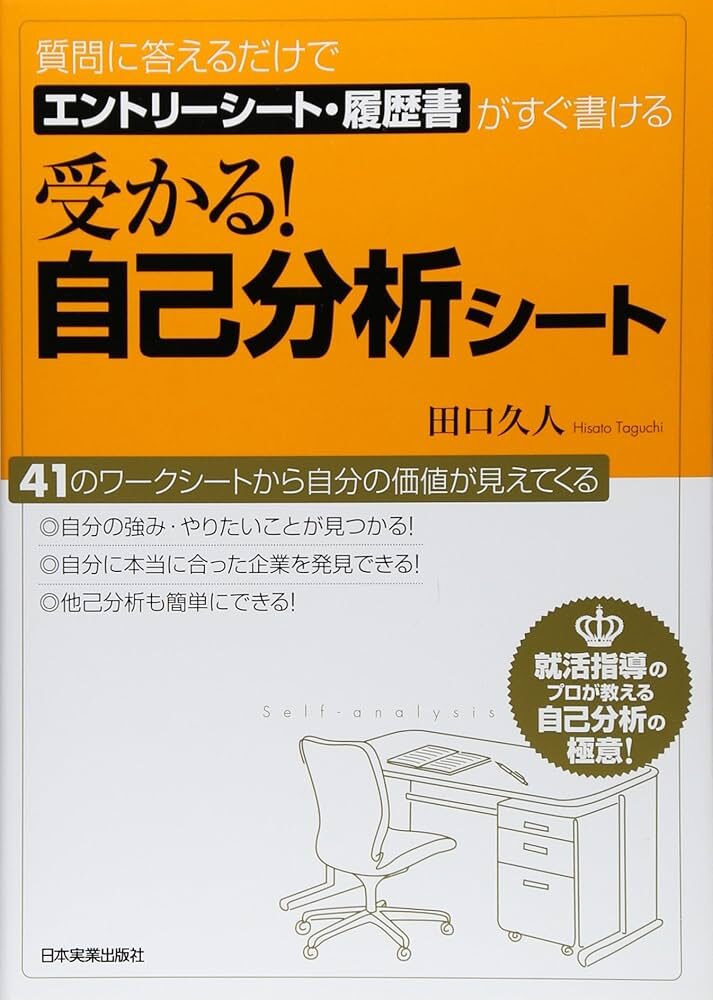
就職活動に特化した自己分析本で、エントリーシートや面接対策に活用できます。特に、「強み・弱みの見つけ方」や「志望動機の作り方」が具体的に解説されているので、就活準備を進める人にぴったりです。
おすすめポイント
✔ 就活向けに特化した自己分析のフレームワークが学べる
✔ エントリーシートや面接対策に直結する内容
✔ 実践的なワークシートが豊富
絶対内定2026 自己分析とキャリアデザインの描き方
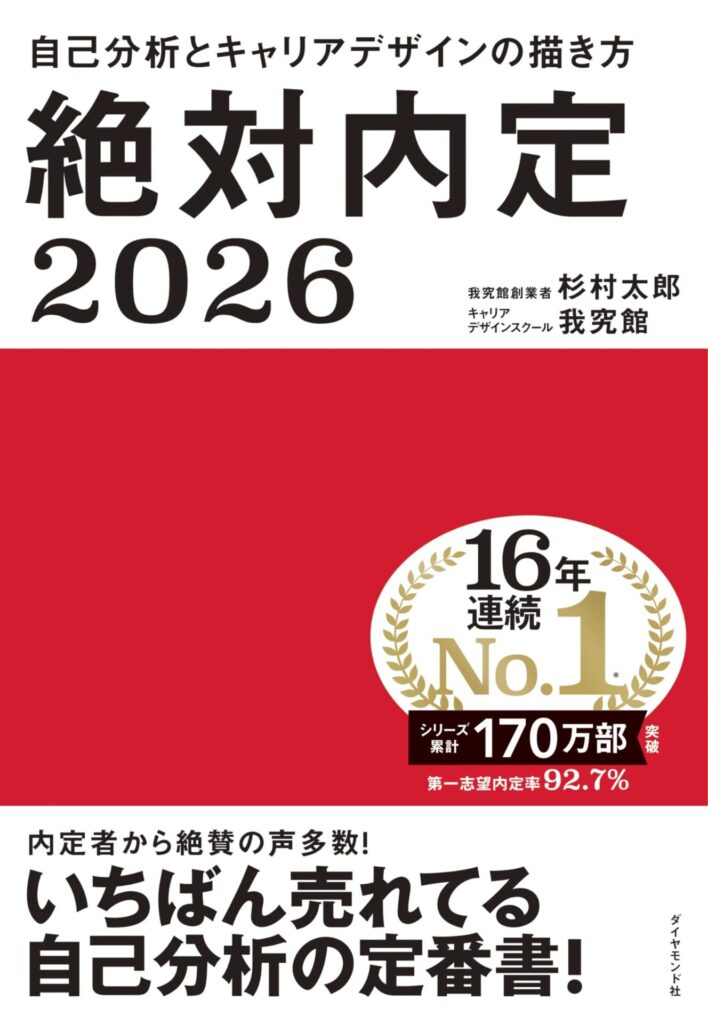
引用:絶対内定2026 自己分析とキャリアデザインの描き方 杉村太郎・我究館 ダイヤモンド社
自己分析からキャリアデザインまでを一貫して学ぶことのできる就活生向けのロングセラー本です。「なぜ働くのか?」という本質的な問いから始まり、自己分析シートを活用して「自分に合った企業」を見つける方法を学べます。
おすすめポイント
✔ 就活の軸を明確にできる
✔ 自己分析シートで具体的に自分を分析できる
✔ キャリア選択の考え方を深められる
さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 最新版 ストレングス・ファインダー2.0
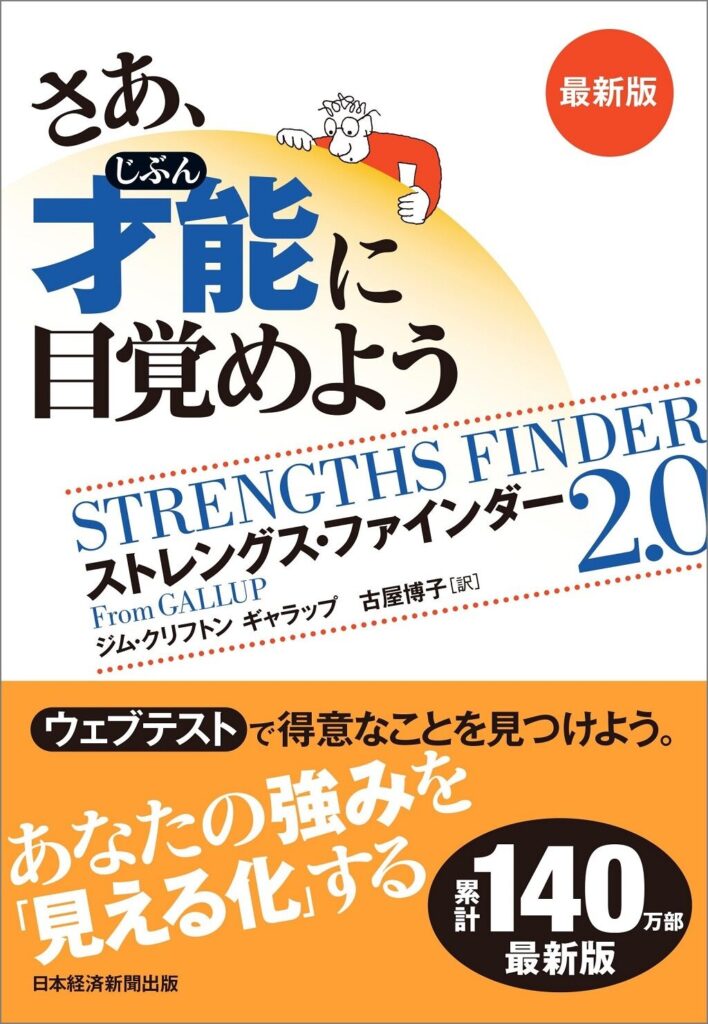
引用:さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 最新版 ストレングス・ファインダー2.0 ジム・クリフトン 日経BOOK PLUS
世界的に有名な自己分析ツール「ストレングス・ファインダー」を活用して、自分の強みを明確にすることができる本です。本の中に付属されているアクセスコードを使うことで、オンラインの診断テストを受けることができ、34の資質の中から「自分の強みトップ5」が分かります。
おすすめポイント
✔ 科学的な診断で「自分の強み」が分かる
✔ 強みをどのように活かせばよいか具体的に解説
✔ 就活だけでなく、長期的なキャリア形成にも役立つ
世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 人生のモヤモヤから解放される自己理解メソッド
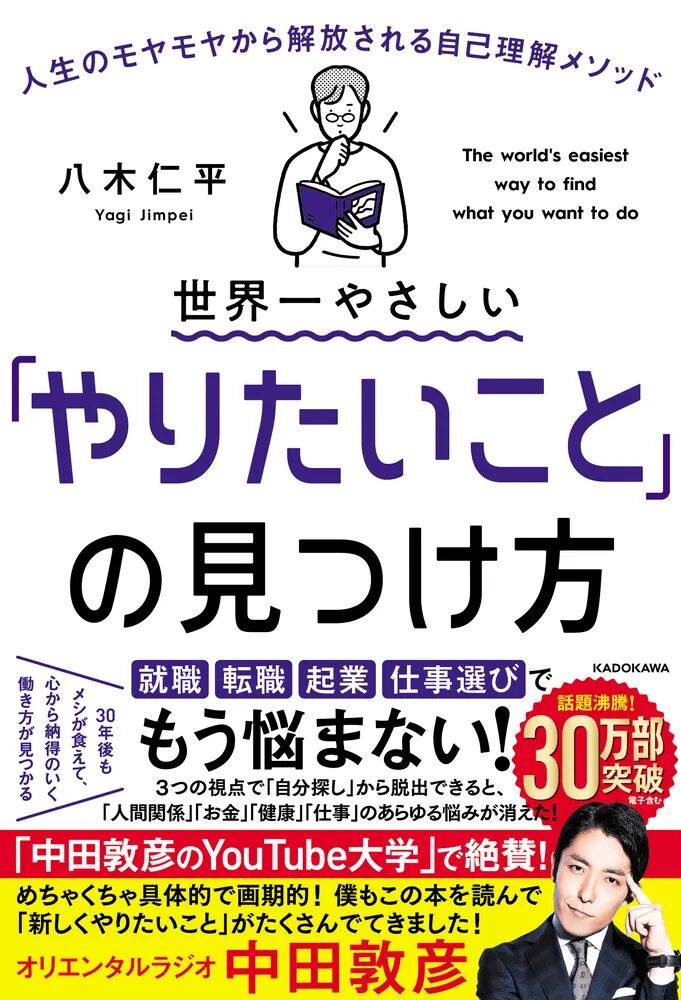
引用:世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 人生のモヤモヤから解放される自己理解メソッド 八木仁平 KADOKAWA
「自分のやりたいことが分からない…」という人向けに、自己理解の方法を分かりやすく解説している本です。心理学やコーチング理論をベースにしており、感覚的ではなく論理的に自己分析を進めることができます。
おすすめポイント
✔ 「やりたいことが分からない」人に最適
✔ 科学的なフレームワークで自己分析できる
✔ 仕事選びだけでなく、人生全般に活かせる
Microsoft Wordを開発した伝説のプログラマーが発見した「やりたいことの見つけ方」がすごい!
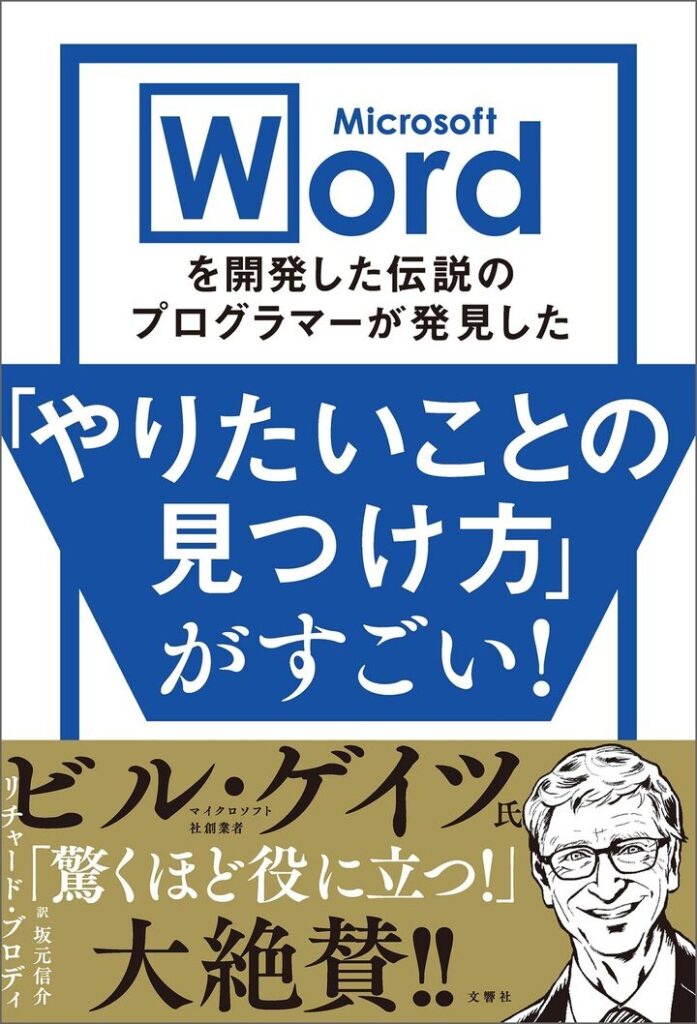
引用:Microsoft Wordを開発した伝説のプログラマーが発見した「やりたいことの見つけ方」がすごい! リチャード・ブロディ 文響社
タイトル通り、Microsoft Wordを開発したプログラマーが実践していた「自分の本当にやりたいことを見つける方法」を解説した本です。「人生の目的を明確にする」「情熱を持てる仕事を見つける」など、実用的なアプローチが紹介されています。
おすすめポイント
✔ 「やりたいことを見つける」ための実践的な手法を学べる
✔ 著者の経験に基づいた具体的なアドバイスが満載
✔ 仕事だけでなく、人生全般の目標設定にも役立つ
自己分析に関するよくある質問
自己分析は就活の中でも大切なプロセスで悩む人も多いはず…
自己分析を上手く進めるにはどうしたら良いのかについて解説していきます。
自己分析が上手くいかない人の原因は?
自己分析が上手くいかない人にはいくつかの原因があります。
- 自己分析を進める際に自分の経験や感情をうまく掘り下げられない
- 自己分析を行う際に、過去の経験にとらわれ過ぎて、未来のキャリアに活かせる視点が欠けている
- 客観的な視点を欠けている
- 他者からのフィードバックを無視している
自己分析は自己だけでなく、他者との対話やフィードバックを反映させることが重要です。自己分析を上手く進めるには、まずは無理に全てを一度に解決しようとせず、小さなステップから始めることが大切です。自身の経験をじっくり振り返り、感情や動機を整理することを心がけると、より深く自己理解が進みます。
自己分析と企業/業界研究はどちらを先にすべきなの?
自己分析と企業・業界研究は、どちらも就活において重要な作業ですが、どちらを先に行うべきかは一概に言うことはできません。しかし、自己分析を先に行う方が、企業や業界研究の際に自分に合った選択ができるため、効果的です。自己分析を通じて自分の強みや価値観、キャリアの方向性を明確にすることで、企業や業界研究の際に自分が何を重視すべきかが見えてきます。自分の適性や興味を知ることで、企業選びや業界選びがより具体的で確実なものになります。
まとめ
自己分析は、就活中、頭を悩ませるプロセスの一つかもしれせん。しかし、就活を成功させるための重要なステップであり、自己分析をしっかりと行うことで、志望動機や自己PRを説得力のあるものにし、選考を有利に進めることができます。
ここで、自己分析をフレームワークで行う際の注意点について振り返りましょう!
①自己分析で分かった内容は言語化して保存する
②短所や弱みなどネガティブな部分も考える
③主観以外の客観情報を重視する
④経験だけでなく「想い」や「感情」も考える
⑤結果だけではなく過程やきっかけも思い出す
⑥一度作成して終わりにしない
⑦企業が求める人物像を意識しすぎない
⑧業界・企業研究も同時におこなう
フレームワークを利用して自分自身を知ることで、企業とのマッチングを最大化し、就職活動を有意義に進めていきましょう!