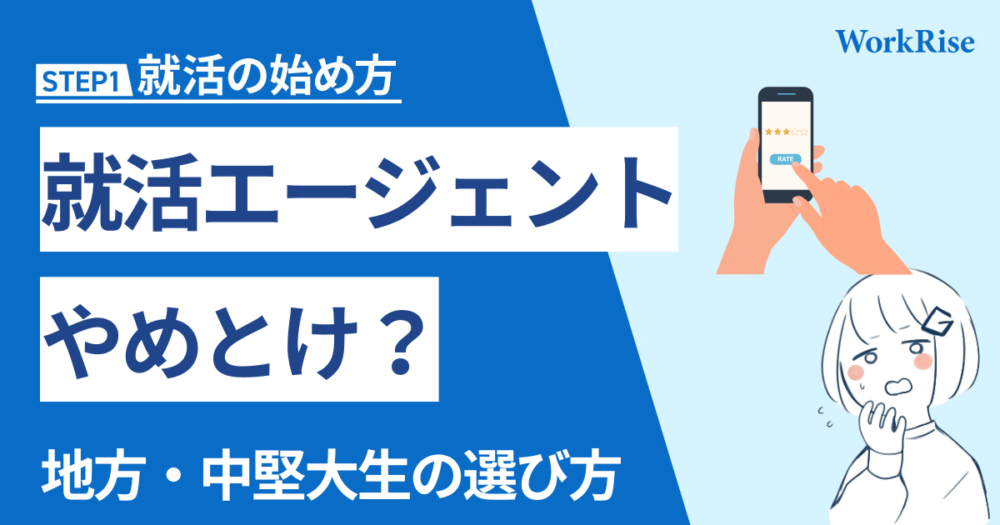こんにちは!28卒ライターのMiaです。
「就活エージェントはやめとけ」なんて話、聞いたことありませんか?
でも実は、ちゃんと選べば地方・中堅大学生の強い味方にもなるんです。
この記事では、エージェントがやめとけって言われる理由や、うまく使うコツ、自分に合ったサービスの選び方まで、わかりやすく紹介していきます!
就活エージェントって実際どうなの?
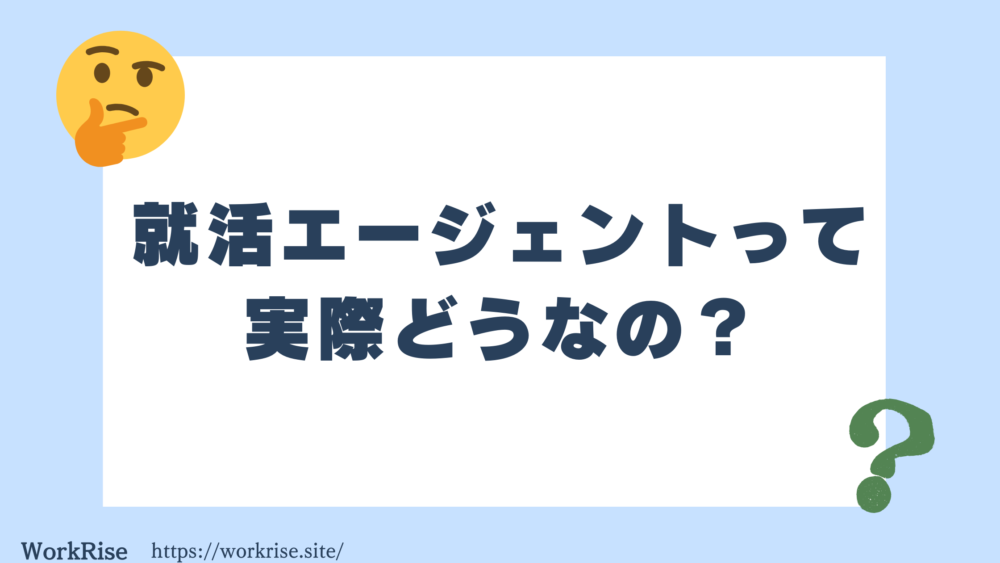
就活エージェントは、就活生に対して企業紹介や選考対策を無料で提供するサービスですが、その評価は学生によって大きく分かれています。
このように就活エージェントの評価が分かれる現状を踏まえると、利用前に仕組みやメリット・デメリットを正しく理解することが重要です。
単純に「良い」「悪い」で判断するのではなく、自分の就活スタイルや状況に合うかどうかを見極める必要があります。
ネットでは「やめとけ」と言われがち
就活エージェントは、インターネット上の口コミサイトや掲示板において「やめとけ」「使わない方がいい」といった否定的な意見が目立つサービスです。
否定的な意見が多く見られる背景には、就活エージェントの利用で失敗した学生が積極的に体験談を投稿する傾向があるためです。
満足した学生はわざわざ口コミを書かないことが多い一方で、不満を抱いた学生は警告の意味を込めて詳細な体験談を共有します。
たとえば、以下のような具体的な失敗体験が数多く投稿されています。
これらの投稿は検索上位に表示されやすく、就活生の目に触れる機会が多いため、就活エージェント全体に対する印象が悪化しがちです。
ネット上の「やめとけ」という声は一部の実体験に基づいているものの、すべての就活エージェントや担当者に当てはまるわけではありません。
否定的な意見だけでなく、多角的な情報収集を行うことで、より客観的な判断を下すことが可能になります。
でも、実際に使ってる人の声はさまざま
就活エージェントを実際に利用した学生の声を詳しく調べてみると、ネット上の「やめとけ」という意見とは異なり、肯定的な体験談も数多く存在します。
利用者の声が分かれる理由は、就活エージェントの品質が担当者や利用する時期、学生自身の準備状況によって大きく変わるためです。
同じサービスでも、経験豊富な担当者に当たった学生は手厚いサポートを受けられる一方で、新人の担当者に当たった学生は満足度が低くなる傾向があります。
たとえば、以下のような感謝の声も多数報告されています。

重要なのは、自分の状況や目的に合った使い方ができるかどうかを見極めることだね!
地方・中堅大学生だからこそ使うメリットもある?
地方大学・中堅大学の就活生にとって、就活エージェントは都市部の有名大学生よりも活用価値が高いサービスと言えます。
地方・中堅大学生が就活エージェントを活用すべき理由は、情報格差や人脈不足といった構造的な不利を補える可能性があるためです。
都市部の学生は大学のキャリアセンターや先輩のネットワークから豊富な企業情報を得られますが、地方学生はそうした情報源が限られています。
就活エージェントを利用することで、自分では調べきれない企業の詳細情報や選考スケジュールを効率的に収集できます。また、面接練習の機会が少ない地方学生にとって、プロのキャリアアドバイザーによる模擬面接は貴重な経験となります。
私自身も大学が地方なので情報格差を感じることがよくあります。

地方・中堅大学生こそ、就活エージェントの持つ情報網とサポート体制を戦略的に活用することで、就活の成功確率を高められるよ!
就活エージェントの仕組みを知っておこう
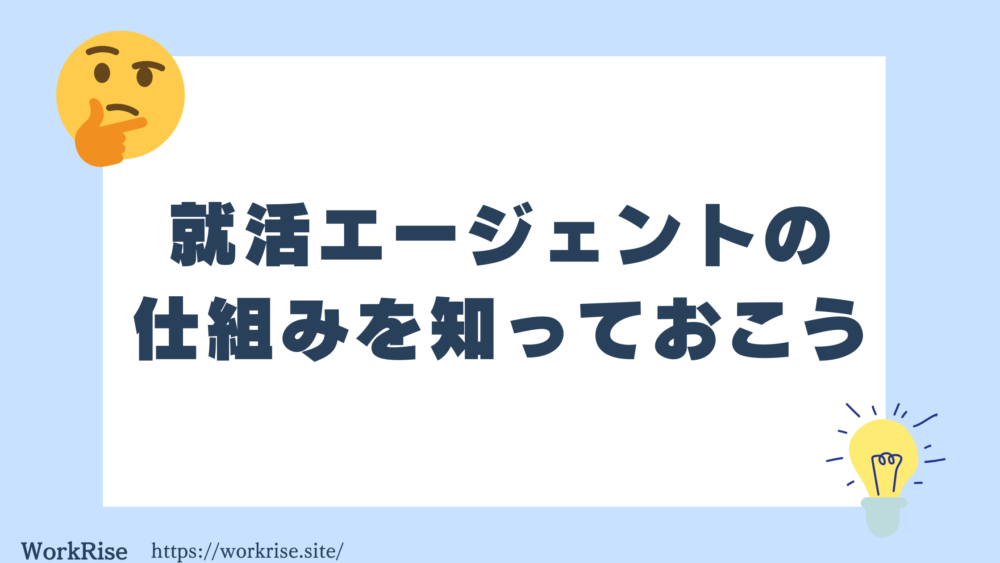
就活エージェントを効果的に活用するためには、サービスがどのような仕組みで運営されているかを正しく理解することが重要です。
就活エージェントの仕組みを理解することで、サービスの恩恵を最大化しながらリスクを最小化する使い方が可能になります。
決して悪用するためではなく、お互いにとって良い関係を築くための知識として活用することが大切です。
企業からの紹介料で成り立っている
就活エージェントのビジネスモデルは、学生の内定が決まった際に採用企業から支払われる成功報酬型の紹介料によって成り立っています。
一般的に、紹介料は採用された学生の年収の30%から35%程度に設定されており、年収400万円の場合は120万円から140万円程度が企業からエージェントに支払われます。
たとえば、就活エージェントが積極的に面接対策を行ったり、企業との調整を代行したりするのは、学生の内定獲得が直接的な売上に繋がるためです。
さらに、担当者が内定承諾を急かすような発言をする背景には、内定辞退されると紹介料が得られなくなるリスクが存在するというものがあります。
この仕組みを理解することで、担当者の発言や行動の意図を客観的に判断できるようになり、自分にとって本当に有益な提案なのかを見極められるようになります。
就活生は無料で使えるけど、ビジネスモデルを理解しておこう
就活エージェントは学生にとって完全無料のサービスですが、そのビジネスモデルの特性を理解することで、より戦略的な活用が可能になります。
就活エージェントは学生と企業の間に立つ仲介業者であり、両者の利益を調整する役割を担っていますが、最終的な収益源は企業側にあるため、微妙な利益相反が発生する可能性があります。
たとえば、学生が希望する大手企業よりも、エージェントと取引関係の深い中小企業を優先的に紹介される場合があります。また、学生の長期的なキャリア形成よりも、短期的な内定獲得を重視した提案がなされることもあります。
一方で、学生の満足度が低いと悪い評判が広まり、結果的にエージェントの事業継続に影響するため、学生の利益を無視することもできません。
このような複雑な関係性を理解した上で、担当者の提案を鵜呑みにするのではなく、自分なりの判断基準を持って活用することが重要です。

無料だからといって受け身になるのではなく、能動的にサービスを利用する姿勢が大切!
担当者の評価基準が「内定」ベースなことも
就活エージェントの担当者は、多くの場合、学生の内定獲得数や成約率によって評価される仕組みになっており、この評価基準が提案内容に影響を与えることがあります。
担当者の評価基準を理解すべき理由は、担当者の提案が学生にとって本当に有益な提案かどうかを判断する材料になるためです。
たとえば、月末や四半期末になると担当者からの連絡が増えたり、内定承諾を急かされたりするケースが報告されています。
また、内定の取りやすい企業や業界を優先的に紹介したり、学生の希望よりも成約の確実性を重視した提案をしたりする場合もあります。
「やめとけ」と言われる主な理由
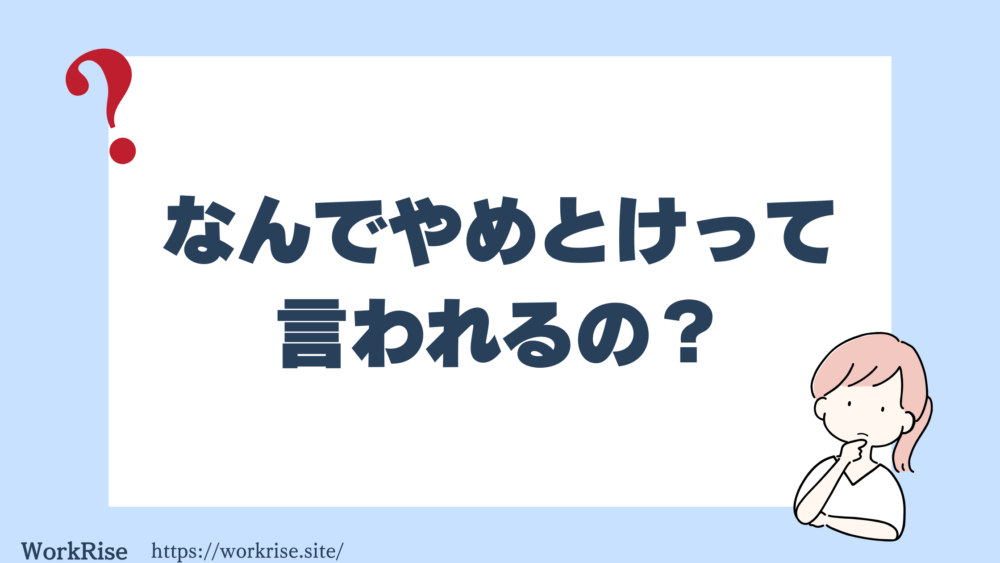
就活エージェントが「やめとけ」と言われる背景には、利用者が実際に体験した具体的な問題やトラブルが存在しています。
就活エージェントに対する否定的な意見が生まれる根本的な理由は、サービスの仕組み上、就活生の利益よりも企業からの紹介料獲得が優先される場合があるためです。
希望していない業界をゴリ押しされる
就活エージェントの利用で最も多く報告される問題の一つが、学生の希望とは異なる業界への就職を強引に勧められるケースです。
この問題が発生する背景には、就活エージェントが特定の業界や企業との強いパイプを持っており、そこに学生を送り込むことで安定した収益を確保したいという事情があります。
特に人手不足が深刻な営業職や接客業、IT業界などは、エージェント側にとって紹介しやすい職種となっているため、学生の志望に関係なく提案される傾向があります。
たとえば、以下のような体験談が数多く報告されています。
このような業界のゴリ押しは、学生の将来のキャリアプランを無視した対応であり、就活エージェントへの不信感を生む大きな要因となっています。

でも、担当者に対してしっかりと意思表示することで、このような問題は回避できる場合が多いよ!
連絡がしつこい、合わない担当者もいる
就活エージェントの利用者から頻繁に寄せられる苦情として、担当者からの過度な連絡頻度や相性の悪さによる不快感があります。
この問題が起きる原因は、担当者に課せられるノルマや業績評価の仕組みにあり、短期間で多くの学生を内定に導く必要があることから、連絡を密にして進捗管理を徹底しようとするためです。
また、担当者の経験不足やコミュニケーション能力の差により、学生との関係構築がうまくいかないケースも存在します。
たとえば、「1日に何度も電話やメールが来て勉強に集中できなかった」「断っても何度も同じ企業を勧められた」「担当者の話し方が高圧的で相談しづらかった」といった体験談が報告されています。
さらに、「年齢が近すぎて頼りなく感じた」「業界知識が浅くて的確なアドバイスをもらえなかった」「価値観が合わずに話が噛み合わなかった」という相性の問題も指摘されています。
しかし、担当者の変更は多くの就活エージェントで可能であり、連絡頻度についても最初の面談で希望を伝えることで調整できます。

合わない担当者に我慢して付き合い続けずに、積極的に改善を求めることが大切!
ブラックっぽい企業を紹介されることも
就活エージェントの利用者から深刻な問題として報告されるのが、労働環境に問題がある企業や、いわゆる「ブラック企業」を紹介されるケースです。
この問題が発生する理由は、就活エージェントが企業の労働実態を十分に調査せずに紹介を行ったり、紹介料を重視して企業選定の基準が甘くなったりするためです。
また、人材確保に苦労している企業ほど就活エージェントに高い紹介料を支払う傾向があり、結果として労働条件の良くない企業が紹介されやすくなる構造的な問題も存在します。
たとえば、以下のような事例が報告されています。
紹介先が限られていて選択肢が狭まる
就活エージェントの利用で学生が感じる大きな不満の一つが、紹介される企業の種類や業界が限定的で、就活の選択肢が狭められてしまうことです。
この問題が起こる背景には、就活エージェントが得意とする業界や企業規模に偏りがあり、幅広い選択肢を提供できない構造的な限界があるためです。
たとえば、以下のような体験談が多数報告されています。

こういった選択肢の狭さは、就職活動の大きなリスクになるね…。

でも、
・複数のエージェントを併用
・自分でも並行して企業研究を行う
このようにすると、そういった問題は解決できるよ!
就活エージェントを使うべきか迷ったら
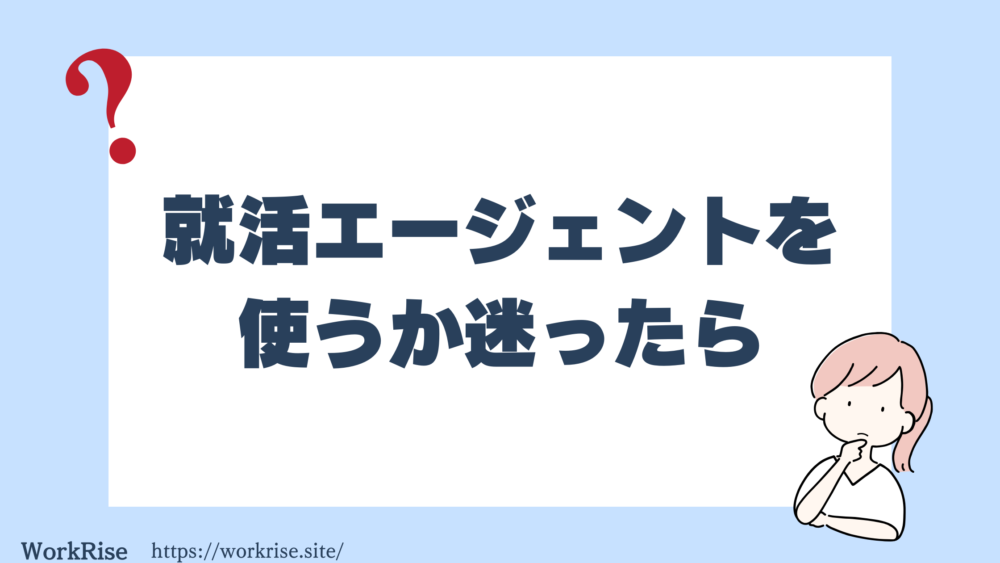
就活エージェントの利用を検討している学生にとって、自分の状況や目標に照らし合わせて判断することが最も重要なポイントになります。
就活エージェントはすべての学生に等しく有効なサービスではなく、特定の状況や課題を抱えた学生により大きなメリットを与えてくれるサービスです。
逆に、既に明確な志望業界や企業が決まっており、自分で情報収集や選考対策ができる学生には必要性が低い場合もあります。
自分の就活軸がブレている人は使うべき
就活の方向性や価値観が定まらず、どの業界や職種を目指すべきか迷っている学生こそ、就活エージェントの活用を検討すべきです。
就活軸がブレている学生にエージェントが有効な理由は、客観的な視点からのアドバイスと豊富な企業情報により、自分では気づかなかった適性や可能性を発見できるからです。
多くの学生は自分の強みや興味の対象を正確に把握できておらず、一人で考え込んでも埒が明かなかったりします。そのような場合には、経験豊富なキャリアアドバイザーとの対話を通じて、新たな視点や選択肢を得ることができます。
たとえば、「文系だから営業しかない」と思い込んでいた学生が、実は企画職や人事職に適性があることを発見したり、「安定志向だから大手企業一択」と考えていた学生が、成長性の高いベンチャー企業の魅力を知ったりするケースがあります。

でも、エージェントの意見を鵜呑みにするんじゃなくて、自分なりの判断基準を持つことも重要だね!

そうだね!
複数の視点を参考にしながら、最終的には自分で納得できる選択をしよう!
情報収集力に自信がないなら就活エージェントを活用すべき
企業研究や業界分析、選考情報の収集に苦手意識がある学生は、就活エージェントの専門知識とネットワークを積極的に活用すべきです。
情報収集が苦手な学生にとってエージェントが有効な理由は、個人では入手困難な企業の内部情報や選考データを効率的に得られるためです。
現代の就活では膨大な情報の中から自分に必要な情報を選別し、整理する能力が求められますが、すべての学生がこのスキルを持っているとは限りません。
一方で、就活エージェントは長年の経験から蓄積されたデータベースと企業との直接的なつながりを持っており、学生一人では到達できない情報源にアクセスできます。
情報収集に時間をかけるよりも、選考対策や自己分析により多くの時間を割きたい学生にとって、エージェントの情報提供サービスは就活の効率を上げてくれます。

でも、提供された情報を鵜呑みにせずに、自分なりの視点で検証することも忘れてはいけないよ!
地方の就活生は選択肢を広げる手段としてアリ
地方在住の就活生にとって、就活エージェントは都市部の企業との接点を作る貴重な手段として活用価値が高いサービスです。
地方学生がエージェントを活用すべき理由は、物理的・情報的な制約により生じる就活格差を埋める効果的な方法であるためです。
地方の学生は都市部でのインターンシップや企業説明会への参加が困難で、地元以外の企業情報を得る機会が限られています。
また、大学のキャリアセンターでも地方企業の情報が中心となりがちで、全国規模の企業選択肢を知る機会が少ないのが現実です。
たとえば、
といった課題を抱える地方学生は多くいます。
地方学生こそ、就活エージェントの全国ネットワークとサポート体制を戦略的に活用することで、地理的なハンディキャップを乗り越えて理想的な就職を実現できる可能性が高まります。
就活エージェントを選ぶときのコツ
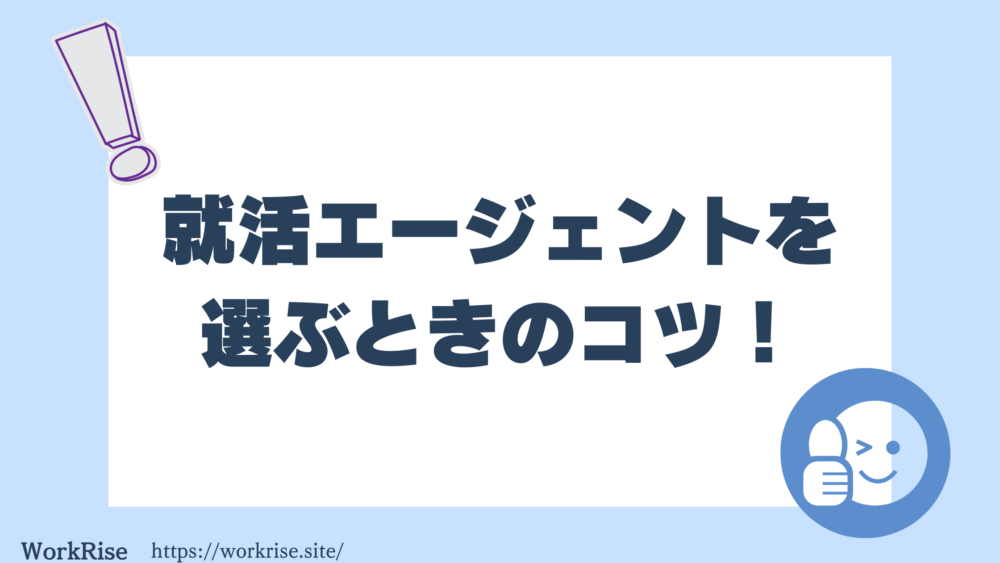
就活エージェントの選択は就活の成功を左右する重要な決断であり、適切な選び方を知っておくことで失敗のリスクを大幅に減らすことができます。
賢いエージェント選びをするためには、事前の情報収集と複数社の比較検討が欠かせません。

一社だけに頼らず、複数エージェントを活用することで、就活の成功確率を最大化することができるよ!
口コミや実績を事前チェック!
就活エージェントを選ぶ際には、インターネット上の口コミサイトや公式サイトの実績情報を必ず確認してから利用を開始することが重要です。
事前チェックが必要な理由は、実際の利用者の体験談や数値データから、そのエージェントの本当の実力や特徴を把握できるからです。
公式サイトの宣伝文句だけでは分からない実態を知ることで、期待と現実のギャップを最小限に抑えることができます。
また、自分と似た属性の学生がどのような体験をしているかを知ることで、利用後の結果をある程度予測することができます。
たとえば、「内定獲得率95%」と謳っているエージェントでも、口コミを調べると「希望しない業界への内定ばかり」という声が多い場合があります。
ただし、口コミ情報にも偏りがあることを理解し、複数の情報源から総合的に判断することが大切です。
複数登録して、自分に合う担当者を選ぶ
就活エージェントを利用する際には、一社だけでなく複数のエージェントに登録して、最も相性の良い担当者を見つけることが成功の鍵となります。
複数登録が有効な理由は、エージェントごとに得意分野や保有求人が異なり、担当者との相性も人それぞれ違うため、選択肢を広げることでより良いサービスを受けられる可能性が高まるためです。
また、一社だけに依存すると、そのエージェントの方針や限界に縛られてしまい、本来の可能性を狭めてしまうリスクがあります。
たとえば、A社は大手企業に強いがIT業界の求人は少ない、B社はベンチャー企業が充実しているが選考対策が手薄、C社は面接対策が丁寧だが求人数が限られている、といったような特徴の違いがあります。
複数のエージェントを比較することで、それぞれの長所を活かしながら短所を補完する使い方が可能になります。

ただし、管理が大変になる可能性があるから、3社程度に絞って集中的に活用するのが良いかも!
エージェントが合わないと思ったらすぐに切り替えよう
就活エージェントや担当者との相性が悪いと感じた場合は、遠慮せずに早めに切り替えることが重要です。
すぐに切り替えるべき理由は、合わない担当者との関係を続けることで生じる時間的・精神的なロスが、就活全体に悪影響を与える可能性があるからです。
就活は限られた時間の中で効率的に進める必要があり、相性の悪い担当者に時間を奪われることは大きな機会損失となります。
以下のような問題が続く場合は、改善を求めるか別の担当者への変更を依頼すべきです。
多くの就活エージェントでは担当者の変更が可能であり、遠慮する必要は全くありません。
【関連記事はこちら!】
【タイプ別に厳選!】就活エージェント
おすすめ22選
まとめ
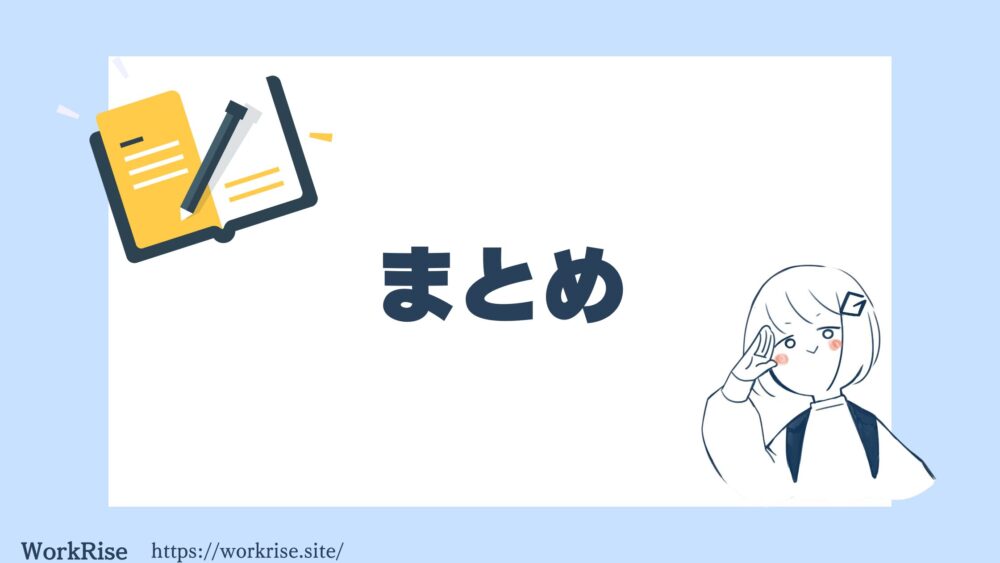
いかがだったでしょうか?
この記事では
- 就活エージェントって実際どうなの?
- 就活エージェントを「やめとけ」と言われる主な理由
- 就活エージェントを選ぶときのコツ
について説明しました。

就活エージェントの「やめとけ」という声を一方的に信じるのではなくて、自分の状況に応じて冷静に判断することが大切だね!