こんにちは!27卒ライターのFujiです。
今回はWebテストのボーダーを一覧で解説していきます!
数多くの企業で採用されているWebテスト。
自分が受験する企業のボーダーがどのぐらいなのか、気になったことはありませんか?
今回は、そんなWebテストの各社ボーダーを一覧でご紹介します!
- それぞれのWebテストの難易度
- 各社のWebテストボーダー
- Webテスト免除を受ける方法
Webテストの一般的なボーダーとは
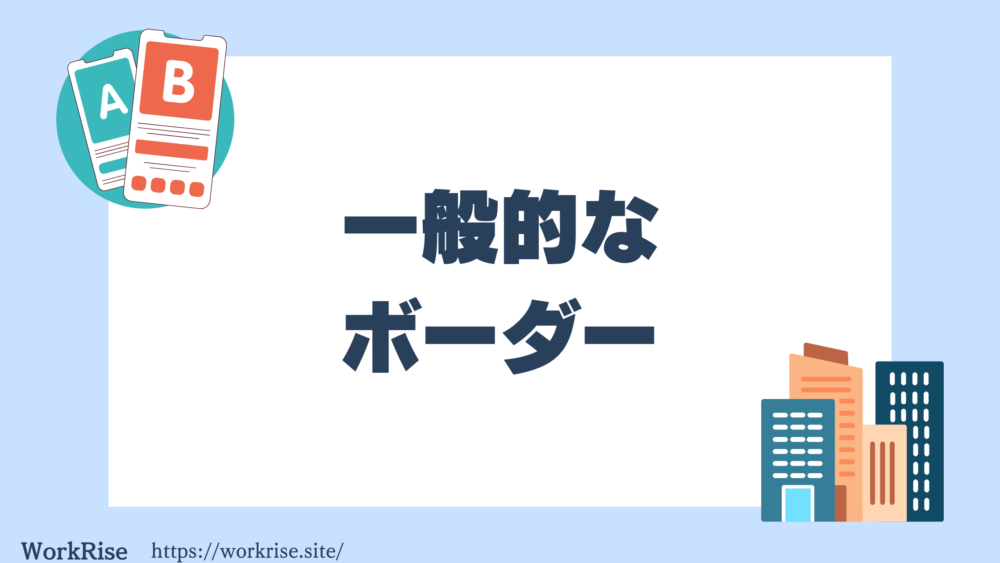
Webテストのボーダーは、企業やテストの種類によって大きく異なりますが、一般的には6割〜7割程度が目安とされています。
大手企業や人気企業では7割以上の得点が求められる傾向があり、中小企業では6割程度がボーダーラインとなることが多いです。
一部の難関企業、特に外資系コンサルティングファームや投資銀行などでは8割〜9割という非常に高い得点が求められることもあります。
重要なポイントは、ボーダーが正答率だけでなく、受験者全体の中での相対評価(偏差値)で判断される場合が多いということです。
そのため、同じ正答率でも受験者のレベルによって合否が変わることがあります。
また、企業によっては言語分野と非言語分野で異なるボーダーを設定している場合もあり、総合的な判断が行われることが一般的です。
Webテスト別難易度
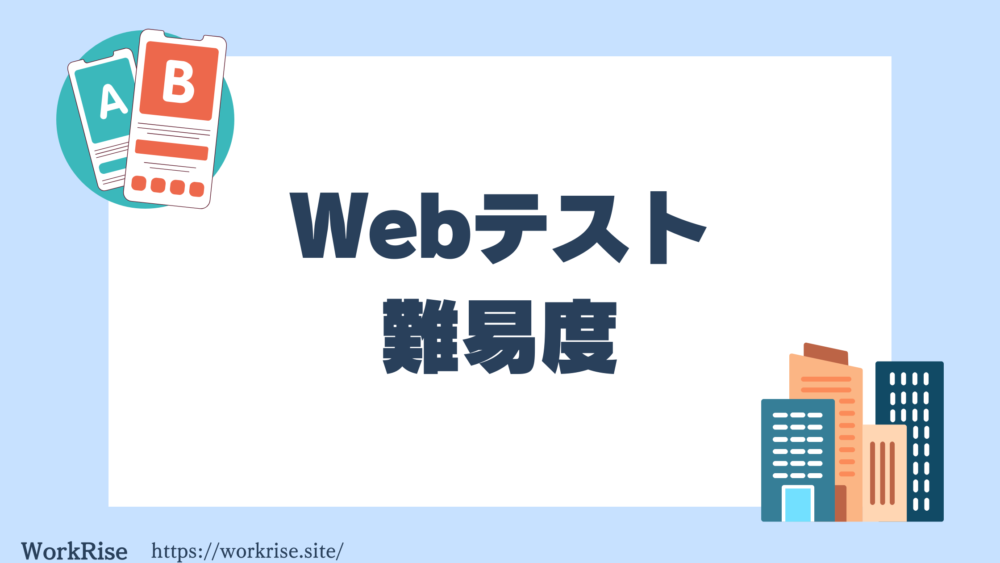
まず、よく実施されるWebテストはSPI・玉手箱・TG-WEBの3種類です。
難易度としては、SPI<玉手箱<TG-WEBです。
SPIは最も多くの企業で採用されているWebテストで、基礎的な問題が多く対策しやすいとされています。
しかし、外資系企業やコンサルティング系の一部企業では、同じSPIでも非常に高い得点が求められるため、難易度が高くなります。
玉手箱は長文読解や計算問題が中心となっており、問題の難易度よりもスピードと正確性が求められます。
TG-WEBはSPIや玉手箱よりも問題自体の難易度が高く、特に旧型(従来型)は難関とされており、論理的思考力や数学的能力がより深く試されます。
SPIのボーダー一覧

SPIは日本で最も広く採用されているWebテストです。
しかし、SPIのボーダーは、業界や企業の競争率によって大きく異なります。
ここでは、企業の難易度レベル別にSPIのボーダーラインを一覧で紹介します!
各レベルの特徴と代表的な企業を確認して、自分が志望する企業がどの程度の水準を求めているかを把握しましょう。
最難関企業(9割以上)
最難関企業では9割以上という極めて高い得点が求められます。
具体的には以下の企業です。
- ゴールドマン・サックス
- ボストンコンサルティンググループ
- 日本銀行
- デロイトトーマツコンサルティング
- PwCコンサルティング など
これらの企業は世界トップレベルの金融機関やコンサルティングファームであり、高い論理的思考力と問題解決能力が求められます。
9割以上という基準をクリアするためには、徹底的な対策と継続的な練習が不可欠です。
単純な暗記ではなく、問題の本質を理解し、様々なパターンに対応できる応用力が必要となります。
これらの企業を志望する場合は、早期からの対策開始と専門的な問題集の活用をおすすめします。
難関企業(8割)
難関企業レベルでは8割程度の得点が求められます。
具体的には以下の企業です。
- アビームコンサルティング
- 野村総合研究所(コンサル部門)
- 政策投資銀行
- 国際協力銀行
- みずほ銀行(GCF部門)
- 野村證券(投資銀行部門)
- 三菱総合研究所
- 電通
- 博報堂
- キーエンス
- AGC
- 商船三井 など
これらの企業は各業界のトップ企業であり、高い競争率と厳しい選考基準で知られています。
8割という得点を確実に取るためには、基礎問題での取りこぼしを完全になくし、応用問題にも対応できる実力が必要です。
特に時間管理能力が重要となり、限られた時間内で正確に問題を解く練習を重ねることが成功の鍵となります。
平均よりやや難しい(7割)
以下の企業では、平均より少し高めの7割程度がボーダーになっています。
- KDDI
- ソフトバンク
- ヤフー
- NTTデータ
- NTT東日本
- NTTコミュニケーションズ
- 中部電力
- 東北電力
- サッポロビール
- 大正製薬
- 三井住友海上 など
これらの企業は安定した大手企業が多く、就活生にとって人気の高い企業が並んでいます。
7割というボーダーは決して低くありませんが、適切な対策を行えば十分に到達可能な水準です。
基礎問題を確実に正解し、応用問題でも一定の得点を確保することで、このレベルをクリアすることができます。
継続的な学習と模擬試験での実践練習が重要となります。
平均的(6割)
最も多い6割程度のボーダーなのは、以下の企業です。
- 三井不動産リアルティ
- キヤノン
- 住友倉庫
- 武田薬品
- 住友生命
- ファーストリテイリング
- 明治製菓
- ベネッセ
- 豊田通商
- 明治安田生命
- 日鉄ソリューションズ など
これらの企業も十分に魅力的な企業ばかりで、安定した経営基盤を持つ会社が多く含まれています。
6割というボーダーは基礎的な学力があれば到達可能な水準ですが、油断は禁物です。
基礎問題を確実に正解し、ケアレスミスを避けることが重要となります。
短期間の対策でも成果が出やすいレベルですが、継続的な練習により確実性を高めることをおすすめします。
SPIの評価方法

SPIは単純な正答率ではなく、受験者全体の中での「偏差値」によって評価される仕組みになっています。
偏差値は20〜80の範囲で算出され、全国平均は50に設定されているため、自分の相対的な位置を把握することができます。
SPIでは偏差値による7段階評価(1〜7)が採用されており、上位2.3%の受験者が段階7、下位2.3%の受験者が段階1という評価を受けます。
段階6以上が高得点とされ、多くの難関企業ではこのレベルが求められます。
言語分野・非言語分野はそれぞれ独立して評価され、企業はこの両方の評価をもとに合否を判断します。
そのため、どちらか一方が得意でも、もう一方が極端に低い場合は不合格となる可能性があります。
バランスの取れた対策が重要となり、苦手分野の克服に重点を置いた学習計画を立てることが成功への近道です。
SPIで高得点かどうかを知る方法

自分のSPIの結果がどの程度なのかを知ることは、今後の対策を立てる上で非常に重要です。
しかし、実際の試験結果は開示されないため、間接的な方法で自分の実力を把握する必要があります。
ここでは、SPIの得点レベルを知るための具体的な方法について解説します。
Webテストの結果は基本的に不明
SPIやその他のWebテストの結果は、基本的に受験者本人には開示されない仕組みになっています。
企業側は詳細な結果を把握していますが、受験者は合否の結果のみを知ることができるのが一般的です。
そのため、自分が高得点を取れているかどうかは直接知ることができず、多くの就活生が不安を感じる要因となっています。
この不透明さが、Webテスト対策の難しさの一因でもあります。
結果が分からないため、自分の実力を客観的に把握し、適切な対策を立てることが重要です。
複数企業での結果を総合的に判断したり、模擬試験での成績を参考にしたりすることで、ある程度の実力把握は可能です。
Webテストの偏差値を知れるアプリを使ってみよう
SPIの模擬試験や練習問題を通じて、自分の偏差値や正答率を知ることができるアプリもあります。
代表的なアプリが「Lognavi」です。
Lognaviは本格的な適性検査を受けることができ、企業の選考で実際に使用されるレベルの問題が出題されます。
受験後に自分の偏差値が分かるので、自分がどのぐらいの実力があるのか、志望する企業に合格することができるのかを判断することができます。
Webテストの偏差値を知りたいときはLognavi!

lognaviのレビュー記事はコチラ!
Webテストで高得点を取る方法

Webテストで高得点を取るためには、戦略的かつ継続的な対策が必要です。
単純な暗記や一夜漬けでは対応できない問題が多いため、計画的な学習アプローチが重要となります。
ここでは、効果的な高得点獲得のための具体的な方法を紹介します。
繰り返し問題を解く
Webテストはどんなものでも、毎回似たような問題が出題されます。
なので、頻出問題や過去問を繰り返し解くことで、出題パターンや解法に慣れ、高得点が期待できます。
同じような問題を何度も解くことで、問題を見た瞬間に最適な解法が思い浮かぶようになり、解答時間の短縮につながります。
繰り返しの演習により、解答スピードと正確性が飛躍的に向上し、本番での安定した得点につながります。
特に計算問題や論理問題では、パターン認識能力が重要となるため、たくさん問題に触れることが大切です。
間違えた問題については、なぜ間違えたのかを分析し、同じミスを繰り返さないよう注意深く復習することが重要です。
毎日少しずつでも継続することで、確実に実力が向上していきます。
時間制限を本番通りに行う
Webテストは時間制限がタイトなものばかりです。
そこで、本番と同じ時間制限で練習することで、実際の試験における時間配分の感覚を身につけておきましょう。
実際の制限時間内で問題を解く練習を繰り返すことで、本番で焦らずに冷静に対応できるようになります。
時間を意識した練習では、どの問題に時間をかけるべきか、どの問題を素早く処理すべきかの判断力も身につきます。
また、時間が足りない場合の優先順位付けや、効率的な解答順序についても学ぶことができます。
タイマーを使用した模擬試験を定期的に実施することで、本番環境に近い状況での練習が可能になります。
問題集やアプリを活用する
Webテスト対策用の問題集やアプリを効果的に活用し、最新の出題傾向や苦手分野を効率的に対策しておきましょう。
市販の問題集は体系的に構成されており、基礎から応用まで段階的に学習を進めることができます。
アプリは、分野別の復習機能やランキング機能なども利用できるため、モチベーション維持にも大いに役立ちます。
また、アプリはスマホで手軽に学習できるので、通学時間や休憩時間などのスキマ時間を有効活用できます。
問題集とアプリを併用することで、理論的な理解と実践的な演習の両方を効率的に進めることができます。
定期的に新しい問題に挑戦することで、様々な出題パターンに対応できる柔軟性を身につけることが可能です。
Webテスト免除になる就活アプリ7選
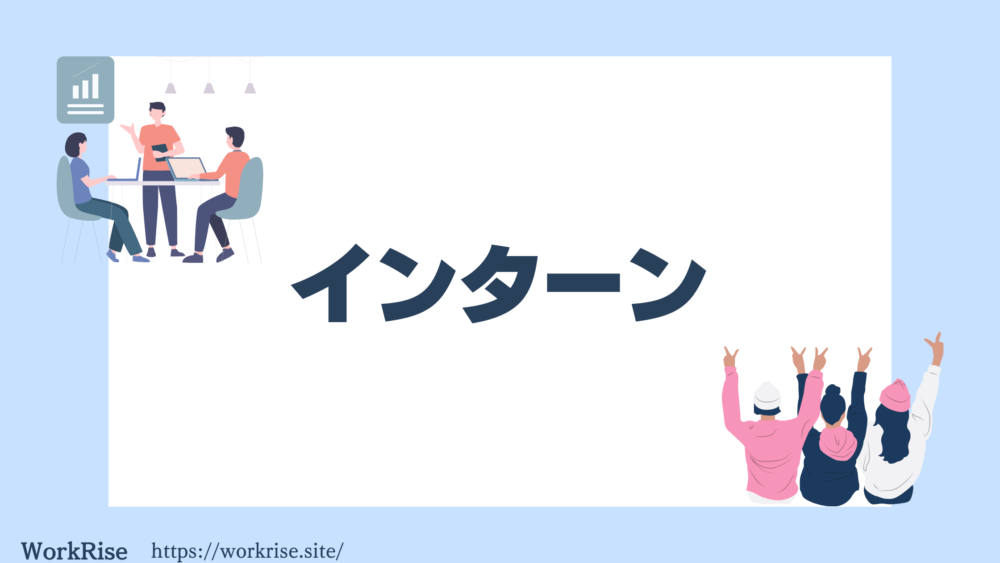
ここまで、Webテストのボーダーについて、対策方法も含めて解説してきました。
ですが、もしそもそもWebテストを受けずに済む方法があれば知りたいですよね。

Webテストが免除される方法ってあるの?

インターンに参加すればWebテスト免除を受けられるかもしれません!
SPIをはじめとしたWebテスト免除の選考優遇を受けたい場合、インターンに参加することは必須です。
また、志望する企業のインターンに参加することができなくても、他の企業のインターンを経験し、働くことや業務に対しての理解を深めておくことはとても重要です。
ここでは、インターンに参加する場合におススメな就活サイトを7つご紹介します!
ビズリーチ・キャンパス
ビズリーチ・キャンパスは、OB・OG訪問に強い就活サイトです。
人気の大手企業の職業インターンシップの案内が数多く届くほか、難関企業の内定者による就活対策講座やサポートを受けることができます。
自分が参加したいインターンの詳しい情報や、選考通過のコツを、自分のOG・OBという身近な先輩に聞くことができるため、生の体験談を知ることができるサービスです。
同じ大学出身の先輩に話を聞けるOB/OG訪問ネットワーク「ビズリーチ・キャンパス」
就活会議
就活会議は、企業情報が確認できるだけでなく、内定者のESや面接情報が口コミで確認できる就活サイトです。
また、従業員からの社内の評価や、実際の雰囲気なども確認できるため、自分に合わない企業の回避にもつなげることができます。
インターンシップの案内やスカウトも数多く届くサイトです。
インターンの雰囲気や内容、選考に通るコツなどを知りたい人にオススメのサイトです!
Lognavi
LognaviはWebテストの対策や自己分析を行うことができる就活サイトです。
自己分析の結果をもとに相性が良い企業を紹介してくれます。
また、同じ学校や同じ企業を志望する人とコミュニティで繋がることができるため、情報共有にも有利な就活サイトです。
【15万人が利用】適性診断で相性が良い企業が見つかる就活アプリ!【Lognavi】

キャリアチケット・スカウト
キャリアチケット・スカウトは、スカウト型の就活サイトです。
まず自分の自己診断をアプリで行い、自己診断結果をもとに、自分の価値観と合う企業からのオファーがやってきます。
誰もが知る有名企業からのオファーやインターンの案内も数多く届きます。
本選考直結のスカウトも届くので、インターンに参加せずに選考優遇を受けられる可能性もあるサイトです。
キミスカ
キミスカはスカウト型の就活サイトです。
スカウト型の就活サイトは数多くありますが、中でもキミスカは、スカウトにランクがあり、企業の本気度が分かるようになっています。
SPIの対策問題集の配布や、就活対策講座など、就活そのものへのサポートもとても充実しているサイトです。
インターン情報も数多く配信されるので、スカウトを受動で気に受けるだけでなく、自分で情報集めと就活対策も同時に行うことができます。
ベストマッチな企業との出会いがある就活は新しいフィールドへ【キミスカ】
ABABA
ABABAは最終面接まで進んだ実績が評価される、スカウト型の就活サイトです。
もし志望の企業に落ちてしまっていても、最終面接へ進んだ経験があれば、その経験を買って他の企業からスカウトが届きます。
既に就活をある程度進めている26卒向けのサービスです。
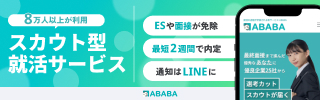
Offer Box
Offer Boxはスカウト型の就活サイトです。
非常に多くの就活生が登録しているサイトで、その分企業の登録数も多いです。
インターン情報が最も多く手に入るスカウト型就活サイトです。
企業はスカウトを送れる量に限りがあるため、学生一人一人のプロフィールを確認して、本気度の高いスカウトを送ってきます。
企業が学生にオファーする新卒就活サイト【OfferBox<オファーボックス>】

まとめ
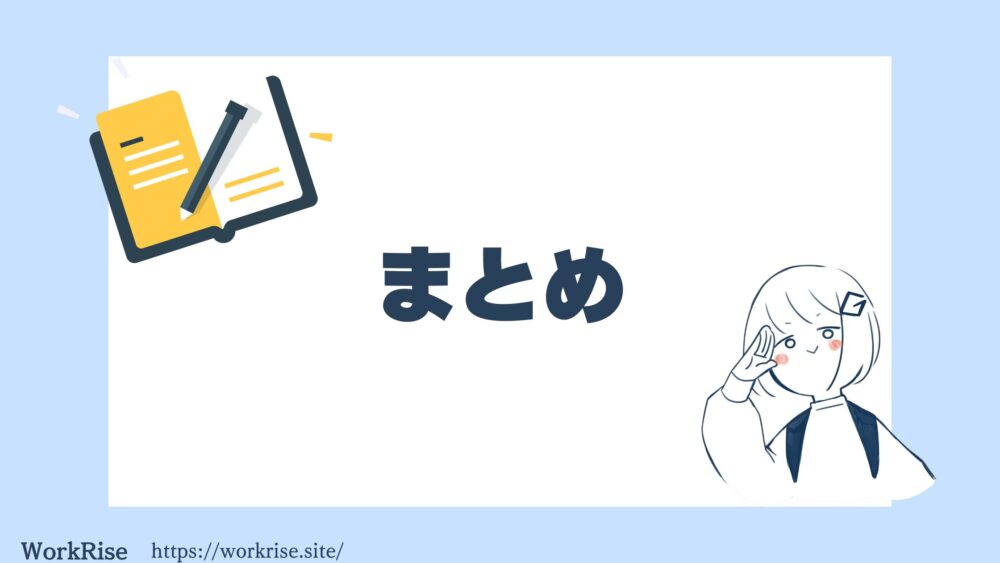
Webテストのボーダーは企業によって大きく異なり、最難関企業では9割以上、難関企業では8割、平均的な企業では6〜7割程度が目安となっています。
SPIは偏差値による相対評価で判定されるため、単純な正答率だけでなく、他の受験者との比較で合否が決まります。
自分の実力を把握するためには、Lognaviなどのアプリを活用して模擬試験を受け、偏差値や順位を確認することが有効です。
高得点を取るための対策としては、繰り返し問題を解くこと、本番と同じ時間制限で練習すること、問題集やアプリを効果的に活用することが重要です。
志望企業のボーダーラインを把握し、それに応じた適切な対策を継続的に行うことで、Webテストでの成功確率を大幅に向上させることができます。
早期からの計画的な対策で、希望する企業への内定獲得を目指しましょう!





